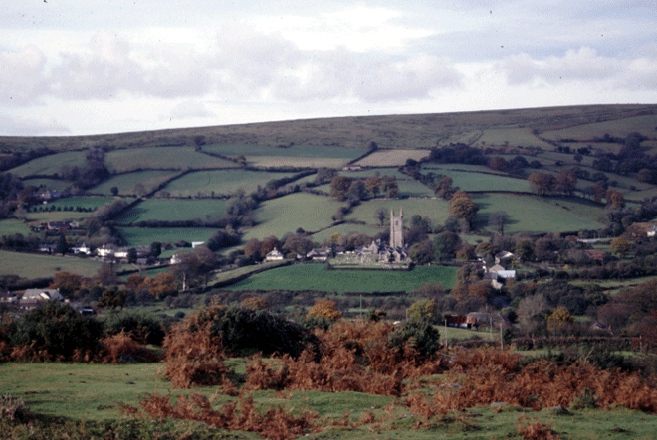イギリス田園紀行ノート Notes for Traveling in the Countryside of the UK
8 Field
1 神のフィールドコテージが集まったヴィレッジやファームハウスの周辺には広大なフィールドFieldつまり圃場が広がる。そのほとんどがヘッジやウォールで区切られながら、なだらかに起伏する地形のまま牧草に覆われている。あたかも緑の大海原のように、地の果てまで、見渡す限り広がるフィールドを高台から眺めたときの姿は壮観そのものである。 そのフィールドでよく見かけるのは無心に草を食んでいる羊の群である。平和とはこのような風景をいうのか ― 七つの海を支配しようと戦争に開け暮れしてきたこの国の歴史を忘れてしまいそうな景色だ。春先の旅なら、生まれたばかりの子羊も混じり、じつに愛らしい。もちろん、ときには乳牛の姿もあれば、馬もいる。いずれにしても牧場か、牧草地がほとんどだ。 家畜が草を食むから、牧草の背丈はつねに短い。採草地なら、当然短く刈り込まれる。平板で、じつに単調な形状である。芝生もそうだが、イギリスの牧草は、夏はもちろん冬でも緑のまま、ただ季節によって太陽の光や気温が変化するから、輝いたり、暗く沈んで見える。 イングランドから北のスコットランドまで、あるいは西のウェールズまで足を伸ばそうと、景色は同じ。そこで、飽きもせず、イギリスの田園風景を求めて旅する私に対し、当のイギリス人が、「カントリーサイドはどこへいっても同じじゃないか」といってからかう。しかし、彼ら自身、この、単調な田園風景が自慢でたまらないのだ。 フィールドで実感する静かで平和な時間 ― 止まっているのではないかと錯覚するほどゆっくりとした、特別な時間だ。だから、イギリス人は、よくこんな言葉を引用する。 「田園は、神が造りたもう。」 原語ではもう少し先があって、 God made the country, and man made the town. という。18世紀の詩人ウィリアム・クーパーWillium Cowper (1731ー1800)の詩の一節だ。どこまでも続く風景だからこそ、そして、時代を超えて受け継がれる景色だと思ったからこそ、神の思し召しを感じたのだろう。 2 経済空間としてのフィールドはたして、この田園風景は、時を超え、変わらぬ風景だったか。 もちろん、18世紀後半の田園風景も美しく、クーパーも感動したに違いない。が、現在の風景とはかなり違っていたはずだ。いまのように、牧草地ばかりになったのはつい最近、20世紀に入ってからのことだから … 。 クーパーが田園風景を眺めていた18世紀後半といえば、囲い込み運動がほぼ完了し、ほとんどの農地をジェントルマンが占有するようになっていた。この運動を正当化してみせたのは、『市民政府論』を著したジョン・ロックJohn Locke(1632ー1704)、「土地は、より高い経済効果を成し遂げられる者によってこそ占有されるべきだ」とし、囲い込みはもとより、植民地における土地の占有も正当化した。ジェントルマンら新興勢力にとって、こんな都合のよい論理はなかった。 法学系のテキストはそんな彼を「近代所有権の父」と持ち上げているらしいが、立場を変えて考えれば、じつに身勝手な主張ではないか。囲い込みによって、共有地から追い出された労働者は、ジェントルマンに雇ってもらうしか生きる道がなくなってしまった。 田園風景に対して、ジェントルマンなら「神が造り賜うた」と幸福感に酔いしれることができたかもしれない。しかし、労働者にとってみればかつては自分たちの共有地、そこで労働を強制されては「神」を恨みこそすれ、はたして、どれだけ感動する気になれただろうか。法学者は「両者は対等な契約関係にあった」とその近代性を評価するが、19世紀半ば、かの、ヨーロッパ大陸からロンドンへやってきた革命家が「労働者よ、団結せよ」と煽動したくなった気持ちの方が理解できる。20世紀後半、われわれ日本人はエコノミック・アニマルと揶揄されたが、18世紀、19世紀のジェントルマンや新興資本家、そして彼らのお先棒を担いだ御用学者こそ、元祖エコノミック・アニマルだったのではないか。 3 そして、羊だけが残った …クーパーが生きた18世紀後半から19世紀といえば産業革命の真っ最中で、毛織物の材料となる羊毛生産は成長産業だったかもしれない。が、それにもまして国民の胃袋を満たさなければならなかったから、農業の主目的は食糧生産にあった。 当時は小麦の栽培が主で、あとはジャガイモやトウモロコシ、からす麦 … 、さきのクーパーと同じ18世紀の詩人で、辞書編集者でもあったサミュエル・ジョンソンSamuel Johnson(1709ー1784)が、からす麦とは「イングランドでは普通馬の飼料であるがスコットランドでは人の食料となる穀物」A grain which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people.と定義したのも、この時代だ。 産業革命によって都市の人口が増えるにしたがって食糧需要も増えた。都会の住民の間でミルクを飲む習慣が一般化すると、毎朝彼らに新鮮なミルクを届けるため、カントリーサイドから大都市へ、発明されたばかりの蒸気機関車に引かれたミルク列車が夜を徹して疾走した。いまは羊の姿しか見られないフィールド、圃場には、かつては土を耕し、作物の手入れをする大勢の労働者たちの姿が見られたことだろう。 前回の復習になるが、19世紀後半、安価な海外の農産物が大量に輸入されるようになると、ジェントルマンは経済的価値を見出せなくなった土地を手放しはじめた。かつてジェントルマンから農場管理を請け負っていたファーマーは、20世紀にフィールドの新しい所有者になったが、そこで挑戦できる農作物はまことに限られた。新たな投資を最小限にし、人手をかけず、あまり農業のノウハウも必要がない … それが羊の放牧だったというわけだ。その羊さえ、いまや厳しい頭数制限にさらされている。田園風景こそ、何とか保たれているが、総合的な「農業力」という点では、絶滅に瀕しているといっても過言ではあるまい。 20世紀の農業は、農産物の消費地である都市との関係だけではなく、国際関係という複雑な要素に直面しなければならなくなった。洋の東西を問わず、農業経営はむずかしい。 4 競技場、戦場、そして…サッカー競技場にしても、ラグビーの競技場にしても、英語ではフィールドだ。すでに、よく知られているように、これらのスポーツはイギリスのカントリーサイドで誕生した。ヴィレッジの住人であるコテージャーたちが、農作物を収穫した後のフィールドで展開した遊びがこれらの競技のはじまりだった。圃場であるからには丘あり、くぼみあり、今日の長方形かつ真っ平らに整地された幾何学的な競技場の形態からは想像もつかない。野を横切り、丘を越え、気の遠くなるような広いフィールドが舞台だった。近隣のヴィレッジどうしが対抗するゲームに人々が興奮し、強力チームは、しだいに全国にその名を知られるようになっていった。 今日、イングランド、ウェールズ、スコットランドそれぞれにプロサッカーリーグがあり、前2者に90あまりのチームが、後者に40近いチームが所属しているといわれる。すそ野が広いスポーツ発祥の地と、テレビ放送があるときだけ興奮する国とでは、文化のありようが違う。 アメリカ合衆国で発明された野球も、もとはイギリスのクリケットがルーツ、だから野球場もフィールドだ。 戦場もフィールド、そして学問分野もフィールド … 、私の研究フィールドは、かつては日本の田園風景だったが、いまはこうしてイギリスの田園風景についてレポートしている。 |