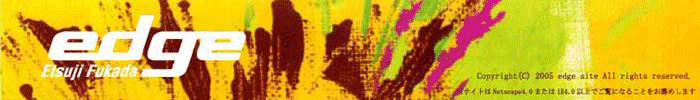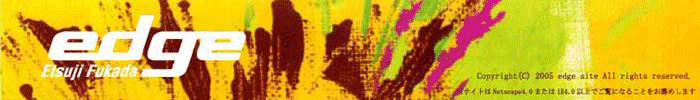同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #9 |
Part 1/ 38 St. Lowrence Terrace |

午前8時 15 分、急ぎ足で階段を降りて、
玄関のドアに手を掛る。「鍵は持った、財布も持った、受験標は持ったし、筆記用具も入れた ・・・・
あっ!セブン・デイズ・トラベルカードを忘れた … 。」
セブン・デイズ・トラベルカード、一週間有効の地下鉄・バスの両方使える定期券である。また急ぎ足で階段を駆け昇る。
その朝、目を覚まし、枕もとの目覚まし時計を見ると、午前7時になろうとしていた。
妙に静かな朝だった。カーテンを開け、電気ポットに水を入れ、コンセントをつなぐ。早起きはいいもんだ、
と鏡の中の寝ぼけた顔に話しかける。ラジオのスイッチを入れる。DJの努めてさわやかな声が流れてくる。
えっ!?、ちょっと待てよ、今、なんて言った、スリー・ミニッツ・トゥー・エイト・オクロック … 。テーブルの上の
腕時計を見て、今が8時だということを知った。枕元の目覚まし時計をつかみあげる。7時にベルが鳴るように
あわせておいた手巻きの目覚まし時計は、もうほとんど7時になったところで針が止っている。ベルを鳴らす
寸前にネジが切れてしまったのだ。アンティークなデザインに惹かれて買ったスコットランド製のベイビー・
ベンという目覚まし時計、カチカチとうるさいばかりで大事な時に役に立たない。なるほど、それで起きた時、
静かだったのか。昨夜ネジをまわしておかなかった僕が悪かったのだが、やつあたりでベッドの上に
ベイビー・ベンを投げ捨てると、思い出したようにジリジリとベルが鳴りだした。
“ ジリジリジリジ・リ、ジ … リ、ジ …… リ、ジ ………”
それは最後のあえぎだったようですぐに力尽きた。
今日は英語学校の入学試験があるのだ。入学試験といっても現在の英語力のレベルを計るだけのものだ
ろう。でも学校から送られてきた説明書には、試験を受けたからといって必ずしも入学できるわけではありま
せんとも書いてあったし、やっぱり緊張する。言葉が思うように通じず、習慣も違う国で独りで何か事を起こ
そうという時には、たとえささいな事でもたえずライブハウスのステージに上がるくらいの緊張がつきまとう。
いちいち気合いを入れないと前に進めない。ましてや学校の試験なんて、大学3年の期末試験以来 10 年
は経験してないことになる。前日も妙に胸が高鳴っていた。ゆっくり朝食を取り、リラックスして出かけようと
思っていたらこの始末だ。
忘れ物のないことをもう一度確認して、ブルーのドアを閉めた。家を起点に垂直に伸びる通りは、
50 メートルも行くと、バスの通るラド・ブローク・グローブ通りに交差する。その角に立った教会の
キリストの像に小さく挨拶をして角を左に折れる。空は気持ち良く晴れ渡り、でも 11 月も後半となれば
通りを吹き抜けてくる風は突き刺すように冷たい。ここ数日、夜遅くまで本を読んでいたりしていたので、
起きるのがいつも昼近くだった。こんなに早く起きたのは何日ぶりか。これから職場へ学校へ出かけて行く
人種入り乱れた大人や子供が集まっているバス停の前を通り過ぎてラド・ブローク・グローブ駅へ急ぐ。
駅前のニュース・スタンドで新聞を買う。何日もブラシをかけてないようなくしゃくしゃの髪をした白人の
ニイチャンにきっちり新聞代 30 ペンスを渡す。
「 OH! LOVELY 」
イギリスではおつりの手間がはぶけたり、何かいいアイデアが提案されたり、事がうまく運ばれたりしたら、
誰でも彼でも “LOVELY” だ。
改札を通り抜けるとき電車がホームに入ってくる音が聞こえ、階段を駆け昇る。すべりこみセーフ。ドアの
脇で乱れた息を整えていると、一緒に駆け込んだ黒人のオバチャンと目が合ったので軽く微笑みを返す。
電車を埋める人達はみんな生活の臭いを身にまとい、いつもと変わらぬ日常にまぎれていこうとしている。
この人達の目に僕はどんな風に映っているのだろうか。
電車が動きだし、高架の上から見下ろす風景がゆっくりと流れ出す。すべての物が動きだしたばかりの
キラキラした月曜の朝だ。こういう朝の街並みを見る度に、5年前、初めてロンドンに来たときの事を思いだす。
当時 26 歳だった僕が、生まれて初めて日本以外の国に足を降ろしたのが、このイギリスだった。
僕はその頃、友人でもある俳優・時任三郎のマネージャーを始めたばかりで、仕事について3ケ月目に
ユーゴスラヴィアでテレビ番組のロケが行なわれることになった。ロンドンはその乗り継ぎ地だったのだが、
スケジュールに余裕があったので3日早く日本を発ち、ロンドンの街に立ち寄ることになった。
その仕事につくまでは売れないロック・バンドをやっていて海外旅行をする余裕など逆立ちしたってあるわけ
なかった。それに特別したいという気もなかった。でも、ロックをやっていたので、イギリスという国には絶えず
意識を置いていたし、好きなミュージシャンの多くはイギリス人だった。そしてほんの偶然の、記念すべき
海外初体験がイギリスだったというのも何かの因縁か。
僕らを乗せた飛行機が早朝の空港に着き、うわついた気分のまま入国審査が終わり、まだ自分が何処に
いるのかうまく認識できぬうちにいつの間にかタクシー乗り場に立っていた。初めての場所で、通訳も付き
添いの人もないというのに、二人とも英語は全然ダメだった。それでもホテルの名前くらいはなんとか
タクシーの運転手に伝わった。
空港を出ると、自動車専用道路の周りには田園風景が広がっていた。その中にレンガ作りの建物が立ち
並ぶ様に、なんとなく自分が外国にいるのだということがわかってきた。でも、まだ狐につままれたような気が
していた。
車の数が増し、次第に街に入って来たことを知らせる。高台になった所から見下ろした街並みが朝靄に
かすんでいる。通りの両脇を高さの揃ったレンガ作りの建物が整然と並ぶ様はとても美しい。なんの脈略も
なく、美意識を何処かに忘れてきてしまったような日本の街並みに囲まれて生活している僕たちの目には
余計にそう映る。
ふと、思春期の頃、心ときめかせたイギリス映画 ” 小さな恋のメロディ ” のファースト・シーン、空撮された
ロンドンの街の映像が脳裏をかすめる。窓の外の風景が記憶の中にある映画のシーンとじわじわっと重なり
合う。その映画に感動したということさえ忘れかけていたというのに、その映像のバックで流れていた
ビージーズが歌う “ イン・ザ・モーニング ” を知らぬ間にくちずさんでいた。それで初めて自分がロンドンにいると
いうことに実感がわいてきたというのが、なんとも我ながら微笑ましい。
タクシーが市街地に入り、警官を乗せた馬が闊歩する、深い緑に包まれたハイド・パークの中を抜ける
頃には、もはや異国の地にいる自分に疑いはなかった。
その3日間の滞在中、昼間はお互い別行動をすることにして、僕はガイド・ブック片手にホテルのまわりを
猫が縄張りを広げるように歩き回った。腹ぺこで入ったカフェでサンドウィッチすら注文できずコーヒーを
すすったり、ホテルのルームサービスで朝食を頼もうと電話し、相手が部屋番号を聞いているのに “
English breakfast please” と言い続けて失笑を買ったりさんざんだったけれど、地図なしでも通りから通りへと
歩きまわれるようになったときには、ほのかな感動をおぼえたりもした。自分のペースで歩いた街は、しっかり
心に焼き付いていたのであろう。その後、パスポートがスタンプで大賑わいするくらいいろんな所へ行く
チャンスを得て、いろんな文化を垣間見て、いろんな偶然がいくつも絡まりあい、いろんな人達との出会いが
あって僕の人生は今いる方向へ導かれてきた。そして、 31 歳の僕がこのロンドンの街に戻ってきたのは、
あのたった3日間の体験の記憶が頭の何処かにしみついていたからではなかろうか。
5年前はバスどころか地下鉄に乗るのさえも怖かった。ポートベローなんてところがあることさえ知ら
なかった。ましてや、まさかこの街に住もうなんてことは思いもしなかった。あの時のロンドンが、
今こうして暮らしているロンドンとはまったく違う場所に思えてしかたない。
カラフルな落書きが線路脇の建物の壁を賑わせてくると、僕の乗った地上を走る地下鉄メトロポリタン・
ラインは終点のハマースミス駅に入る。そこで地下を走る地下鉄のピカデリー・ラインに乗り換え、
ひとつ目のバロンズ・コート駅で降りる。そこから歩いてすぐのところに僕の目指すハマースミス・アンド・
ウエストロンドン・カレッジがある。僕は内心すごくおどおどしていたのだけれど、それをわかられまいと、
何度も通ったことのある道を行くような顔をして学校の構内に入って行った。
教室に着いたのは僕が一番で、少し早すぎたのか、指定された教室のドアにはまだ鍵がかかっていた。
薄暗い廊下にボーッと立っていると、限りなく白に近い金髪を腰あたりまで伸ばした白人の女の子が現われ、
教室の番号を確かめドアに手をかけようとした。
「まだ誰も来てないよ」
そう僕が言うと、その子はほとんど表情を変えないで僕に微笑みかけ、僕の横に少し離れて並んだ。
それ以上の会話はなく、黙ったまま、2分位は二人きりで立っていただろうか、彼女の透き通るような青い瞳は
じっと、ただ壁を見つめていた。
試験は筆記問題が出来た順にその場で採点され、教官からの口頭による簡単な質問があって終わる。
僕の次に教室に来たあの白人の女の子はあっという間に筆記試験を終え、教官の口頭の質問にもすらすら
答え、その会話でドイツ人だとわかったその娘は、視線をゆらすことなく金髪の長い髪をゆらしながらさっさと
教室を後にした。僕はまだ 10 問ある問題の3問目あたりに頭を悩ませていた頃だ。あんなにしゃべれるん
だったら僕は絶対に学校など行こうなんて思わないだろうと思いながら、その後ろ姿をぼんやりと見つめた。
教室に来たのは僕が一番早かった。だというのに教室を出たのは 20 人近くいた受験生の中で僕が
一番遅かった。それでも晴れて1月からの入学が認められた。下から2番目のレベルのクラスのようだ。
授業は1日3時間2レッスンで、月曜から木曜までの4日間。
英語力をつけるというのも渡英の大きな目的だったにもかかわらず、それまで4か月、英語学校には
通っていなかった。もし僕が 20 歳そこそこで、まだ将来の展望が何も見えていないのだとしたら、
すぐさま英語学校の門を叩いたのだろう。しかし、僕はもう 31 歳。これまで歩んできたポピュラー音楽の道を、
もうひとつステップ・アップするために仕事までやめてやってきたのだから、逆にすべきことはいっぱいある。
ひとつでも多くコンサートや演劇なんかを見たかったし、旅もしてみたかった。そして僕に大きな影響を与えて
くれたイギリスのロック・ミュージックがどんな所から沸き起こってくるのかを知るために、出来るかぎりこの
街に住んでいる人達の感覚に近い生活がしてみたかった。お金がありあまっているのなら話は別だが、
そんな余裕はなく、なにかとその時その時で不必要な物を切り捨てる必要があった。話すということは、
人間に気持ちを伝えるということだ。学校だけが勉強する場所じゃない。そう思ったから学校には近付か
なかった。
しかし、自分ではしっかりした考え方を持っていたとしても、世間というものは肩書きを求めてくる。
イギリスに入国する際の書類にも、ちゃんと職業を書く欄がある。仕事も辞めた、学生でもない、
こういう人は入国の際とてもやっかいなことになる。学生でもなく仕事もないとなれば入国審査官は
すぐさま職を求めてイギリスに来たとみなす。かつての植民地、 1997 年に中国に返還される香港からの
移住者さえも拒否する姿勢を打ち出しているイギリスは、特に入国のチェックの厳しい国のひとつである。
イギリスの経済の状態は良いとは言えず、失業率も高い。そこへきて外国人に仕事を奪われてしまった
のでは困ってしまうというわけだ。僕は見事にそうみなされてしまう人の代表選手であった。
もちろん僕はイギリスで仕事をする気などまったくなかった。しかしそんなことを素直に信じる入国審査官など
いるわけはない。7月にヒースロー空港で入国する際は、まだ状況もわかってなかったし、職業欄には学生と
書き、学校はこれから探すと言ったら、完全に疑いのまなざしで見られ、ぐちゃぐちゃつっこまれ、といわれても
何を言っているのかよくわからず、めんどくさいので生活費として持っていた現金を見せたら何なく6ケ月滞在
可能の観光ビザがもらえた。世の中すべて金、か … 。
こんなものかと思って気を抜いたのがいけなかった。8月の終わり頃、僕は日本から来ていた彼女と
ドーバー海峡をフェリーで渡り、北フランスに3泊4日の旅に出た。イギリス側のドーバーからフランス側の
カレイまで高速フェリーでたったの 40 分。新潟から佐渡島に渡るような物である。天気の良い日は白く切り
たったお互いの対岸がしっかりが見渡せる。フランスへの入国はパスポートをチェックしているのかしてない
のかわからないくらい簡単に終わってしまい、ほとんど国内旅行の感覚だった。その2週間前に行った
アイルランドにいたってはイギリスからの入国者はパスポート・チェックなしだったから、ヨーロッパ圏内の
出入国はこんなものかと思い込んでしまった。それにしても、たった 40 分間、船にゆられただけでまったく
言葉が変わってしまうのがなんとも不思議だった。カレイから海岸沿いを南西に 50 キロほど下った小さな
避暑地で3日間過ごし、4日目の早朝、カレイに戻り、そこからフェリーに乗りドーバーに着いた。
僕達以外の人はほとんど素通りに近い状態で入国のゲートを抜けて行く。そこは EC (ヨーロッパ共同体)
加盟国のパスポートを持っている人用のゲートであった。当然僕達2人はそうではないからもうひとつの
入国審査カウンターに並んだ。そこには僕と彼女しかいなかった。僕はヒースロー空港でしたのと同じ
腹づもりで入国審査に臨んだ。しかしあの時と状況はずいぶん違っていた。すでにイギリスに入国して
すでに2ケ月近く過ぎていて、入国カードの職業欄に ” 学生 ” と書いたのなら、当然もう学校に入って
いなければならない時期だった。そしてたった4日の短い旅で必要以上のお金を持っていなかったし、
日本へ帰るための航空券もホテルに置いたままだった。そういう事実に気づいたのは ” 訊問 ” が始まって
からだった。
いかにもいじわるそうな白人の審査官が機嫌悪そうに現われ、僕のパスポートと入国カードを見て
露骨なまでに嫌悪の表情を浮かべ、そこからは悪夢のようだった。僕の言うこと全部に疑いのまなざしを
投げ付け、ケチをつけてくる。
「英語の勉強など日本でもできるだろう。なんで日本でしなかったんだ。」
「日本にいた時は忙しくて時間がなかった。」
「なに!?忙しかった?けっ … 。」
ツバでも吐き出すように、そう言葉を吐き捨てて顔をそむける。髪の生え際が頭のてっぺんあたりまで
後退し、その分の髪が移ってきたようにふさふさした髭を生やした、一日中こんな苦虫を潰したような顔を
しているんじゃないかと思うくらいかわいげのない顔をしたオヤジは、ひとつ会話が終わる度に黙り込み、
いちいち溜息をつき、いらだたしげにボールペンの背でデスクをトントンついたりパスポートをパラパラ
めくったり閉じたり。そういう態度を取られたんじゃこちらだって何も悪いことはしてないんだしオメエの国に
金を落としてやってんだぞなんだその偉そうな態度は、といった傲慢な成金のオッサンみたいな口の
ひとつもきいてみたくもなるが、僕のパスポートの行方は、ガサガサにかさついた手をした審査官に握られて
いて、履いてる靴を脱いで頭のてっぺんをひっぱたいてやりたくなるようなこのオヤジの気分ひとつで僕は
イギリスに入れなくなってしまう。ひたすら我慢して誠実さをアピールし続ける。
ガランとした入国審査場に 20 分近く立っていただろうか。結局このドーバー海峡の入国審査官は、
あと2ケ月以内に学生ビザを取るかイギリスを離れるかしろと言葉荒げに言い、憎しみをぶつけるように
パスポートにスタンプを ” バコーン ” と押した。結果的には2ケ月間延長されるはずだった観光ビザは、
7月にヒースロー空港で得た来年1月まで滞在可能の期限を半分削られてしまった。
僕のようなイギリス滞在者にとってドーバーは鬼門だ。ここから船でフランスに渡るのが何処へ行くよりも早くて
安い国境を越える方法で、観光ビザの延長をする目的の外国人がたくさんやってくるのだから、審査官も
目尻を吊り上げるわけだ。後に数少ない日本人の知り合いから聞いただけでも、ここで痛い目にあった
日本人の話は驚くほど多い。ドーバーで入国を拒否され、そのまま日本に強制送還されてしまった人も
いるという。昔ほどではないにせよ、労働許可を得ないで仕事をしている人はまだまだたくさんいるのだろう。
かくして、入国拒否という最悪の事態は免れ、ロンドンに戻ってくることはできたものの、
あまりの悔しさからか高熱が出て2日間寝込んでしまった。
ビザを削られたからといってすごすご日本に帰るわけにはいかなかった。削られた分はその2週間後、
スペイン旅行に行った帰りのロンドンのもうひとつの空の玄関、ガトウィック空港で取り戻した。
入国カードの職業欄にははっきりと音楽家と書き、パスポートと共に日本に帰るための航空券と銀行の
残高証明書を提示し、今は休みを取って次の仕事のための研究をしていると審査官に述べた。
日本ではどんな仕事をしていたのかとか、事細かな追及はあったが、今回は何も屈するところはなく、
結局そこから6ケ月間の滞在が許可された。
ドーバーから戻り、このスペインに渡るまでの間、ずっと自分が何者なのかを考え続けた。
この先イギリスにいる間に何をしなければいけないのかを考えた。ドーバーではあせったのもあって、
ただでさえひどい英語がさらにしどろもどろになってしまい、余計に疑われてしまった感があった。
だから、スペインいた間、入国審査場で言うべきことを英語でノートに書きだし、必死で暗記した。
これこそ生きた英語の勉強である。そういう事を考えることが出来ただけでも、この事件は価値が
あったと思う。
学生ビザを持っていたらこんな思いをすることもなかっただろう。
学生ビザを取得するには、週に 15 時間以上の授業数を持つ英語学校で受講していなければならない。
そういう私立の学校はロンドン市内には数多くあり、レベルもピンからキリまであるが、ある程度の
グレードを保った学校であったら月に7万円位の授業料が必要であろう。
今、お金持ちの日本は海外脱出ブームで、ロンドンにもたくさんの日本人語学生がいる。
どこの私立の英語学校にも日本人だらけという話を聞く。そうするとどうしても、ただなんとなくロンドンに
来ている日本人同士つるんでしまうことになるという。限られた時間の中で、せっかくロンドンまできて、
高いお金を払ってまでして、僕はそういう環境の中に入りたくはなかった。
そんな僕も1月から英語学校に通うことになったのだが、授業料は1月から7月までの2学期分で約5万円。
公立だけあって馬鹿みたいに安い。でもこの学校の授業数では学生ビザは取得できない。ビザが取れない
から日本人の生徒の数もぐっと少ないという。授業数が少ないのは他にやりたいことが色々とある僕には
ちょうどいい。そんな所だったら通ってみてもいいなと思ったのだ。
学校からの帰り道、友人の家に立ち寄り、夕方頃、ラドブローク・グローブ駅のホームの階段をボケっと
降りていた時だった。
「 HAVE A GOOD TIME? 」
10 歳位の男の子がすれちがい様、僕にそう言った。
“ ハブ・ア・グッド・タイム!?、なんだそれ、そりゃあいろいろ大変だけど、毎日楽しくやってるし、
英語学校にも入れることになったし、でも、なんでこんなガキにそんなこと答えなきゃいけないんだ …”
相手は別に怪しげな勧誘するわけでも募金箱を下げているわけでもなく、きちんと小学校の制服を着ている
普通の子供で、僕をからかっているようにも思えない。どう答えてよいものやら首をかしげていると、
その子は自分の手首を指差しながら、さっきと同じことを言った。
「 HAVE YOU GOT A TIME? 」
よく聞けば、なんの事はない、 “ ハブ・ユー・ゴット・ア・タイム? ” 、今何時ですか、と彼は時間を聞いて
いただけの話だった。あっ、なあんだ、そんなことか、そんならそうと早く言えよ。
最初からそんなことはわかっていましたよとばかりに腕時計を見て時間を伝えると、
子供は困ったような顔で “ サンキュー ” と言って階段を昇って行った。こんな簡単な文章を聞き違えるような奴に、
英語学校がどうこう言う資格はないな、とニガ笑いをしながら改札を通り抜けた。
駅を出ると夕闇にどっぷりつかったゴミゴミした街があった。
“Have a good time ? ”
Yes, I have! 、ここでの生活もまんざら悪くはないよ。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|