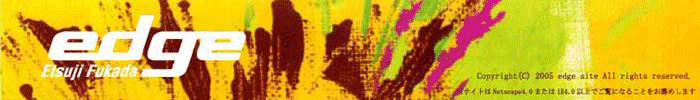同じなのに違う空の下 edge in London '89-'90 #8 |
Part 3/ GHETTO ゲットー |

ポツンと独り、なんともいえない孤独感を味わっていた。
あたりはピーンと張り詰めた緊張で静まり返っている。
そこらじゅうに散らばる白くて柔らかそうなジャーマン・ブレッドの切れ端。
パンとジャムの入った桶をのせた荷車のまわりに重なるように倒れているヴィルナ・ゲットー・シア
ターの劇団員達。その中から腹話術の人形、ダミーだけがもだえながら立ち上がり、立ち去ろうとして
いたナチスの将校キッテルに何か訴えかけるが声にはならない。
それに気づいたキッテルは、冷たい表情のまま静かにピストルをダミーに向け、そして引き金を引く。
銃声が響き渡る。
ダミーが糸が切れた操り人形のように崩れ落ちる。もう一度あたりを見渡したキッテルが踵を返し、ゆっくりと去って行く。
銃声の余韻が消えると、再び訪れる深い沈黙。
ナチス・ドイツの兵隊が乱射したライフルが残した、火薬のきな臭い匂いがじわじわとやって来て、
鼻を突く。
すると荷車の後ろに倒れていた腹話術師のスリックだけが命絶えだえ這いずって来る。そしてさっきまでキッテルが座っていた椅子に腰掛け震えた声で言う。
” Our last performance? Our last performace…”
低い歌声がどこからともなく起こり、次第に強さを増しながら、それとともに撃ち殺された人々が暗が
りの中で亡霊のようにゆっくりと立ち上がる。歌はますます強さをおびて、椅子に座ったスリックは
おびえるように耳をふさぐ…
”… We'll live forever. We will survive…”
ゲットー”という芝居を初めて見たのは8月だった。友達のサトミちゃんに誘われて、どんな内容の
芝居なのかも知らずに出かけた。その日、サトミちゃんと彼女の友人達はすでに前売りのチケットを持
っていて、突然行くことになった僕には当日売りの立ち見チケットしか残っていなかった。それで僕は
独り、2階席の一番後ろの通路に腰掛けてその舞台を見ていた。
幕が降り、場内に灯がともる前に重い足取りでロビーに出た。テムズ川沿いにあるナショナル・シア
ターのロビーには、その川沿いの夜景が広がり、無数に浮かぶ街の灯が、悲しい世界から抜け出して
きたばかりの心にしみわたる。ロビーがにわかに騒がしくなり、1階席で見ていたサトミちゃん達とも
おちあったけれど、なんとも言葉がでなくって溜息ばかりついていた。
ロンドンのほぼ中心、たくさんの劇場がひしめくコヴェント・ガーデンあたりから南へ少し下ると
テムズ川が姿を現わす。そこに架かっている橋が映画「旅情」の舞台としても有名な
ウォーター・ルー橋。その橋を渡るとサウス・バンクと呼ばれる国立・王立の劇場、
ギャラリー、コンサート・ホールが集まるエリアになる。ウォーター・ルー橋をはさんで
東側の川沿いにある近代的な建物がナショナル・シアターである。ナショナル・シアターの中には
大、中、小の3つの劇場があり、それぞれオリビエ、リトルトン、コッテスローと名前がついている。
いずれもイギリスの近代舞台演劇に大きな功績を残した人物の名前だそうだ。
”ゲットー”は、そのナショナル・シアター内の大劇場オリビエで、4月後半から公演されていた。
第二次世界大戦中、ドイツに占領されたリトアニアの首都ヴィルナ(現在のソ連邦、リトアニア共和国
の首都ヴィリニュス)に配属されてきたナチスの将校キッテル。若くてハンサム、軍人でありながら
アーティストでシンガーのキッテルは、ユダヤ人の大量虐殺を行ないつつも、ユダヤ人居住区ゲットー
にユダヤ人アーティストによる劇場を作ることを命じる。
ソ連軍によるリトアニア陥落間近に劇団員全員が射殺される悲惨な結末までの流れの中で、
迫害を受けながらも必死に生き延びるユダヤ人の様々な人間模様を劇中劇、劇中歌をからめて描く
音楽劇である。
劇場を出た僕達はウォーター・ルー橋を渡ってコベント・ガーデンに向かって歩いていた。
川辺をすりぬける風がほてった頬に心地良い。橋の上からの夜景は、西は有名な時計台ビック・ベン
あたりから東はセント・ポール寺院あたりまでがパノラマとなって広がり、感動の余韻を静かに噛みし
めるにはこの上ないロケーションだった。あいかわらず黙りこくって歩いていると、僕の少し後ろを
歩いていたサトミちゃんが、実にさりげなく僕の肩を“ポンポン”と叩いていてくれた。彼女には
言葉の出ない僕の胸の中が見えているみたいだった。
2度目に”ゲットー”を見たのはその数週間後、木曜のマチネだった。前と同じ当日券だというのに、
昼の部だということもあってか最前列の中央の席が取れた。最後列の通路だった前回とは極端なまでの
違いである。今度はひとりだった。サトミちゃんはもう東京に帰ってしまっていたし。
その日、2階席には人もまばらで、1階席の僕のまわりには、やたら老人が多かった。そしてその中に
は大勢のユダヤ人がいた。彼らは、独特の小さなお皿のような帽子を頭のてっぺんに乗せているので
すぐにわかる。実際、その戦争の時代を通り越してきたユダヤ人と共にこの芝居を見るのはなんとも
切ないことであった。
ちょうどその頃、テレビでは第二次世界大戦中の記録フィルムをによる特集番組が毎晩のように放送
されていた。ヨーロッパの人々にとって、あの戦争でのナチス・ドイツの暴走は余ほどの驚異だったの
だろう。目を覆いたくなるような悲惨な映像を次々と映しだし、2度とあんなことは繰り返さないと
いう強い意志にあふれていた。その最大の被害者がアウシュビッツの大量虐殺で知られるユダヤ人でる。
”ゲットー”の舞台となっているヴィルナは”リトアニアのエルサレム”と呼ばれたほどのユダヤ文化
の中心だった。ナチス・ドイツに占領されたとなれば、執拗なまでのユダヤ人狩りが行なわれたのは
言うまでもない。 1940 年に8万人いたヴィルナのユダヤ人が 42 年には1万2千人にまで減っている。
逃亡した人もいるが、ほとんどが虐殺されたという。その優れた頭脳がゆえ、迫害を受け続けた悲しい
歴史を持つ流浪の民、ユダヤ人。たまたま見た芝居で僕は、それまであまり気にも止めてなかった
ヨーロッパの悲しい歴史を知った。
舞台の間口全体をおおう薄いブルーのスクリーン・カーテン。その真ん中には、子供がクレヨンで書い
たような赤い太陽が浮かんでいる。つりさげられたブルーのカーテンは舞台の半円形にせりだした部分
もおおい、その中央前方には古ぼけた木の椅子がひとつ、客席に向けて置いてある。場内の灯がおちて、
低い風の音のような音楽が流れると、一人の老人が舞台に現われ、椅子に腰掛け、見えない誰かの質問
に耳を傾ける。そして震えた声で話し始める。
「わし達の最後の公演?なにひとつ思い出せんよ…。最後の公演…、そう、あれはキッテルがゲンズを
殺した前の晩だった。 10 日後、ゲットーはぶちこわされてしまった。あれがラスト・パフォーマンスだ
った…。」
”ゲットー”は実話と残された記録をもとにイスラエル在住のユダヤ人劇作家ヨーシュア・ソボル氏の
作、演出によって 1984 年にイスラエルで初演された作品である。登場人物の中、劇団員でひとりだけ
生き残る腹話術師スリック=ファースト・シーンでインタヴューに答える老人のモデルになっている人
物は、作品が書かれた当時イスラエルに在住していた人物で、彼の証言がこの作品を産み出した。ナチ
スの将校キッテルや図書館長のクラーク、ユダヤ警察の暑長ゲンズも実在した人物である。 1985 年にベ
ルリン・フェスティバルでも好評を博したこの作品が今年英訳され、イギリスでの初公演が実現した。
…なんてことを最初に見た時は何ひとつ知らなかったが、この2度目を見る前には、プログラムや原作
本で内容をしっかり把握していた。しかも役者の唾がかかりそうな距離でユダヤ人の老人に囲まれてと
いう現実味に満ち溢れた状況だったので、ラスト間際にナチスの兵隊が機関銃をぶっぱなした時には自
分も撃ち殺されたような気分だった。
カーテン・コール。出演者全員が観客の拍手に答えて深々と御辞儀をする。たいていどんな内容の芝居
でもカーテン・コールには出演者の笑顔のひとつもあるものだが、この作品ばかりはそうはいかないら
しい。冷酷なナチスの将校キッテルを演じた俳優さんなどは、一番重要な役回りだったのだから舞台中
央で絶賛の拍手を浴びてもおかしくないのだが、3回のカーテン・コール、いずれも舞台上に広がった
出演者の後方の隅で”ゴメンナサイ”とあやまるように頭を下げていた。
終演後、目頭を熱くした僕とは対象的に、客席を立つ御老人達の表情は意外に静かで、何かを思いだす
かのような遠い瞳をしていた。
劇場を出ても空はまだしっかり明るかった。ウォーター・ルー橋を渡りながら、シリアスな内容以上に
音楽のことが頭の中を駆け巡っていた。”ユダヤ人迫害の歴史”だけじゃ、この作品はこんなにも
魅力的なものにはならなかっただろう。舞台演劇ならではの演出の遊び、そして音楽が舞台に見る者を
引き込む。こういう重く悲しい世界の中だからこそ音楽は美しく力強い。それは現実の世界と同じだ。
この劇中で歌われている曲は、ガーシュインの”スワニー”以外、初めて耳にするものばかりだった。
ところが、どのメロディにも、いつかどこかで聴いたことのあるような懐かしさがあった。それは僕達
が子供の頃に聴いたアメリカのフォーク・ソングの匂いだった。あの頃、僕はアメリカを通した世界し
か知らなかったから、そう感じるのだろうか。あの頃の僕にとってユダヤ系もイタリア系もなく、
アメリカ人はアメリカ人だった。
劇中の伴奏はすべて舞台上の出演者が奏でる生の楽器、もしくは生声のコーラスで、スピーカーを通さ
ない声や楽器の音が会場に響き渡るのが心地良かった。ずっとロック・ミュージック、ポピュラー・
ミュージックに携わってきた僕は、こんなに当たり前な生の音の良さ、強さを忘れてしまっていた。
音はスピーカーを通して聴くもの、エコーは機械がつくるもの、そんな固定概念に支配されていた
自分にとって、当たり前なその響きは、ある種のショックと言ってよかった。
コヴェント・ガーデンに出ると、現在はショッピング・モールに姿を変えた旧中央卸売り市場の建物を
中心に、短い夏の長い夕暮れを楽しむ人々で賑わいを見せていた。ロック・ガーデンというレストラン
のテラス前で、スリムで背の高い黒人が、ゴミ箱に腰掛けて唄っている。手にしたギターは、その大き
な身体には似合わない小さな傷だらけのガット・ギターで、しかも弦が1本切れている。そんなことに
おかまいなしで彼は唄い続ける。弦楽器のはずのギターはしばしば打楽器になり、はじけるような彼の
声は、通り行く人のざわめきにも負けず、石畳の広場に響く。そうだ、これが音楽だ。
異国の地でささいな発見に心を動かしながら夏は過ぎていった。
夕暮れが河面に迫っていた。真横をチャリング・クロス駅に入って行く列車がガタガタと走って行く。
あの夏の日は遠く、 11 月のテムズを吹き抜ける風が冬の入り口を風が伝える。僕はウォーター・ルー橋
より1本西にある、鉄道の鉄橋脇の橋の上をサウス・バンクに向かって歩いている。
これから通算4度目の”ゲットー”を見るのだ。
もしこの芝居に出会わなかったら、僕のヨーロッパに対する認識はもっと浅いものだっただろう。
ロンドンを知るにはイギリスを知らなければならない。イギリスを知るにはヨーロッパを知らなければ
いけない。その興味のきっかけのひとつを与えてくれたのがこの芝居だ。約半年間続いたこの公演も
あと数日でいよいよ” Last performace ”を迎える。今日は最後のご挨拶のつもりでやってきた。
橋の下を観光船が通り抜けて行く。遠くからみれば街の灯を優しく揺らすテムズの水も、
こうして真上からのぞき込んでみると黒く濁って渦巻いている。
都市の美、それは厚化粧と華やかなドレスで着飾る、赤い街灯の下のロクサーヌ達だ。
橋のあちこちで” NO HOME, NO MONEY ”と書いたダンボール紙を掲げた白人の若者が道端に座り
込んでいる。サウス・バンクの方から歩いてきたスーツ姿の中年男性が、歩調をゆるめるでもなく、
ポケットの小銭を若者の前の帽子の中に落とした。若者は”サンキュー”でもなく、
ただうつろな瞳で帽子の中を見ていた。こんなところにずっと座っているのも大変だろうな、
同じ大変なのだったら仕事をすればいいのに、と思ったが、そんな単純な話で済むようなことではないらしい。
何枚かのペニーで買ったパンでとりあえず明日が迎えられればそれでいいのかも知れない。
それでいいのか、も、知れない…。
橋を渡り終えて階段を降りると、コンサート・ホールの前の広場で、背の高い白人の若者が
3つのボールを使った曲芸を披露している。およそ芸というにはほど遠いパフォーマンスだったが、
少なくとも彼は自分の身体を使って金を稼ごうとしていた。僕はたまたまポケットの中にあった
10 ペンス硬貨を2枚、彼の足元の帽子に入れた。チャリンという音に気を取られたのか、
若者はリズムをくずしてボールを落とした。ニガ笑いしながらボールを拾い上げた若者は、
また懲りずにボールを宙に投げ続ける。そう、それでいいんだ。
ナショナル・シアターに入ると、バーの前のロビーではジャズのカルテットが演奏していた。
そのまわりを開演時間を待つ人達が囲み、ある者はオシャベリをしながら、ある者は静かに目を閉じ、
一日の疲れをビールやワインで癒している。これからみんな劇場に入り、
3時間ばかり現実の世界から心を解き放つのだ。
” No theatre in a graveyard”
墓場に劇場なんかいらない。ヴィルナ・ゲットー・シアターの結成を命じたナチス・ドイツ対する、
ユダヤ知識人の反発のスローガンである。とはいうものの、たとえナチスの命令であれ何であれ、
明日には強制収容所に送られるかもしれない恐怖を抱えながら生活するユダヤ人達にとって、
劇場はかけがえのない娯楽の場所になった。強制収容所行き、それは死への旅発ちを意味する。
最後になるかもしれないその夜を楽しむために、彼らは思いっきり着飾って劇場に向かう。
墓場に行く前にせめて劇場へ。舞台に立つ者もユダヤ人である以上その状況に変わりはない。
彼らはユダヤ人としての尊厳を失うことなく作品を選び、舞台を務めた。
ヴィルナ・ゲットー・シアターは公演があればいつも、立ち見席もないくらいの大盛況だった。
劇場内は異様なまでの民族意識と生命の息吹に満ちあふれていただろう。
ジャズの演奏が終わり、少ししてから開演が近づいたことを知らせるチャイムが鳴る。
僕はシェリーのグラスをバーのカウンターに返し、ずいぶん擦り切れた”ゲットー”の原作本を片手に
劇場に入る。
席に収まると、もう何度も見た作品なのに胸が高鳴るのがわかった。
今日もまた、新たな感動に出会えるのであろうか。しかし、いくら気持ちが高まったとしても、
45 年前のヴィルナ・ゲットー・シアターに渦巻いた、そんな感動を得ることはできないだろう。
そんな感動を得ることのできない、得なくてもよい平和な時代に僕らは生きている。
たとえ悲惨な最後をとげたにしろ、せめて一夜でも生命の尊さを謳歌したヴィルナ.ゲットーの人々。
そんな人々と、現代のイギリス、テムズ川に架かる橋のたもとで、濁った瞳で座り込んでいる若者と
どちらが幸せなのだろうか。
ゆっくりと劇場の灯がおちる。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|