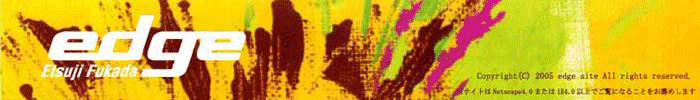
同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #14 |
Part 9/Typhoon /台風 |
季節はずれで場違いな台風がロンドンを襲っていた。 「わかったわ。あなたがそんな風に言うのなら、私はこれ以上このクラスの 授業は受けられないわ!」クリスティーンさんは、すこしソバカスの浮かぶ頬を紅潮させ、 鞄に荷物をねじ込みながら教室から出て行った。教卓に両手をついた担任教師のクリフは、 やはり紅潮した顔をこわばらせ、やれやれとうなだれた。教室のあちこちからため息が漏れた。 窓ガラスを強い風が叩き、中庭をコーラかなんかの空き缶がカラカラと音を立てて転がっている。 ハマースミス・アンド・ウエスト・ロンドン・カレッジの外国人のための 英語クラスが始まって3週間が過ぎようとしていた。正確に言うとクリスマス休暇明けの2学期が始まって 3週間である。授業は月曜から木曜の、それぞれ午後1時15分から4時までで、途中に15分の休憩がある。 その騒ぎはその休憩後に起こった。 昨年の11月に続いて2度目の台風にロンドン市内は大混乱。まさかイギリスのような北の国に 台風がくるとは思わなかった。この現象もここ数年の事らしく、地球の温暖化と深い関係があると新聞に書いてあった。 まったく困った時代になったものだ。 いつも通り時間に余裕をもって部屋を出た僕はラドブローク・グローブ駅のホームで30分近く電車を待ったが、 来るのは吹き抜ける強い風ばかり。それで電車をあきらめバスに乗ったら道路が大渋滞。 30分近い遅刻でやっと学校にたどりつけた。145番教室のドアをそっと開けると、 ちょうどクリフが”HAVE TO”の用法についてレクチャーしているところだった。 ちょっと赤ら顔のアングロサクソン系、いかにもイギリス人って感じのクリフ。 カシャッというドアの開く音で話しの腰を折られた英語教師は、僕に型通りの笑顔でハッロォウと挨拶し、 またすぐにレクチャーに戻る。 スペイン人、フランス人、ブラジル人、パキスタン人、アラブ人、トルコ人等、 人種入り乱れた約20人が教卓を囲むようにコの字型に並んで、ノートを取ったりしている。 その内の何人かが、視線でハローと挨拶をくれる。その中にはもうひとりの日本人ヨーコちゃんもいる。 ドアに一番近い席に腰を降ろし、テキストとノートを出しながら黒板を見る。 I don't have to go to work every day…「それでは、この練習問題の続きは休憩の後にしましょう。3時には教室に戻るように。」 前半の授業が終わり休憩に入ると、先生も大半の生徒も教室から出ていった。 みんな、入り口脇のコーヒー・バーあたりで一服するのだ。 「コンニチワ、グェンキデスカ?」 僕の隣に座っていたフローリアンが、リンゴを自分のセーターにこすりつけながら言った。 僕はこの優しい目をしたスイス人に簡単な日本語を教えていた。彼は21歳、スイスではケーキ職人だったそうで、 道ばたなんかに落ちている、いろんな種類のジュースの缶を集めるのが趣味という変わった奴だ。 「うまくなったね。でもグェンキ”じゃなくてゲンキだぜ。」 彼の斜め前に座っているフランス人のクリスティーンさんが笑顔で僕らの会話を聞いている。 彼女は35歳で2児の母、旦那さんの仕事の関係でイギリスに住んでいる。真面目で明るくて、 さりげないオシャレがいかにもフランス人らしい。 「それにしてもひどい風だね。お陰で電車が来なくて遅刻しちゃったよ。 ところで、僕が来るまで、どんなことをやってたの?」 リンゴをひとかじりしたフローリアンが顔をしかめて肩をつぼめた。 「別になにもたいしたことやってないよ。クリフだって15分遅れて来たし。 昨日僕達が提出した宿題のチェックがまだ済んでなくて、なんだかんだ言い訳して…。」 フランス語が日常語のフローリアンはフランス語訛りの英語で、 口をとがらせてボジョボジョと答えた。 「そうよ、クリフは時間に遅れるななんて偉そうに言うわりには自分が遅刻して来るし、 あんな簡単な宿題のチェックが済んでいないなんて話にならないわよ。これじゃ授業が前に進まないじゃないの。」 やっぱりフランス語訛りのクリスティーンさんが、それまでの穏やかな表情を急変させて僕らの会話に割り込んで来た。 やはり僕の隣にいたトルコ人のオズラム、スペイン人のマリアホセという2人の女の子もその会話の中に加わって、 クリフ先生の怠慢な授業態度に対する井戸端会議が始まった。僕を含めたこの5人はいずれもこの1月からこの授業に参加していて、 だいたい授業の様子がつかめた先週あたりから、このクリフという教師に対する不満が出始めていた。 ヨーロッパの人々は、どの国の言葉も語源がラテン語で、文法が似通っているせいか、 僕と同じクラスにいるのがおかしいくらい早口の英語でベラベラ喋る。 フローリアン、マリアホセ、オズラムの3人はまだ20代前半で、さし迫った近い将来の仕事のこともあり、 もっと勉強したいというあせりにも似た意欲に満ちていた。 オズラムとマリアホセはそれぞれ「オペア」と呼ばれる住み込みの家政婦をしながら通っていたし、 フローリアンは週に何回かレストランの皿洗いをしていた。彼らには日本人の若者のように授業数も多い私立の英語学校に通うような余裕が、 経済的にも時間的にもないのである。授業は週に4日間、しかも1日3時間弱、彼らにとっては貴重な時間であった。 それだけにクリフという先生のノンビリした態度にいらついていた。 僕とクリスティーンさんは30歳も過ぎていて、それなりに余裕もあったから、 行こうと思えばしっかりした学校に行くこともできるだろう。だけど問題はそういう事ではなくて、 クリフがほんの少しでもその気になれば授業は内容の濃いものになるのにという、もどかしいようないらだちだった。 僕が思うに、この50歳過ぎのクリフという太っちょのイギリス人、 教え方は下手ではないし、これといって悪質な人間という訳でもない。 ただ残念なことに彼の辞書からは情熱という2文字が消えてしまっているようだった。 なんでイギリスという国には、こんなにやる気のないやつが多いのか。 いくら汗を流しても支配者階級ばかりにお金が集まる階級制という社会構造がイギリス人の労働意欲を低下させ、 豊かな国力で整備された福祉制度は、皮肉な事に失業保険で生活する働かない人を急増させた。 現在のイギリス人の多くに漂うやる気のなさは、こういう根本的な社会構造に問題があるといわれている。 それとクリフの情熱のなさが関係あるとは言いきれないが、 失業保険でブラブラする人があふれた1960年代に働き盛りの青年期を過ごした彼に、 少なからずともそんな社会風潮が影響しているのは間違いない。結局、ちゃんといわなきゃこの授業は、 いつまでもこの調子でズルズルいっちゃうぜ、なんて話しで盛り上がったいたら、休憩時間を終えた話題の人、 クリフが教室に戻って来た。彼自身が決めた授業再開の時間を5分過ぎていた。 クリフが教科書を開き、我々生徒に向かって顔を上げると、 いきなりクリスティーンさんが立ち上がって先陣を切った。 「クリフ先生、ちょっとお話ししたいことがあるんですけれども。 あなたの授業に対する態度についてです。あなたの授業に対する姿勢は少し怠慢だと思いませんか。 時間にもルーズだし、授業内容も簡単すぎると思います。宿題のチェックもしてこないことがたびたびあるし、 もっと真剣に授業に取り組んで欲しい。」 さすがに大人の女、2児の母、びっくりするほどズバッときた。 彼女の英語はたどたどしかったが、逆にその分強く響いた。すぐにフローリアンがクリスティーンさんの援護射撃に入った。 「僕達は時間いっぱいみっちり授業を受けたい。 宿題だってもっとたくさん出してどんどん先へ進むべきだと思う。」 クリフにはまったく予期せぬ宣戦布告だった。 後退した髪の生え際までみるみる赤くなったが、すぐに体勢を建て直すかのように、 うす笑いをうかべながら反撃に出た。 「ちょっと待って下さい、皆さん。何がそんなに気にいらないのか、 私には理解できないのですが。私は決してなまけているつもりはありませんし、 授業内容もこのクラスのレベルにあった物です。あなたたちの力ではこれより難しいことはまだ無理です。 これ以上のことを私に要求されても困るのですよ。」 それに対してトルコ人のオズラムも発言しようとしたが、感情が先走ってしまって言葉につまってしまう。 アラブ人のホセインが仲裁を買って出ようと何やら言いだしたが、言ってることが話の本題から完全にずれていて、 解決の糸口を見いだせそうもない。フローリアンの向かい側に座っていたフランス人の女の子エステラが、 その騒動が気にいらないのか強い口調のフランス語でフローリアンになにやら言う。どうやらこの子は保守穏健派のようだ。 フローリアンも負じとフランス語でやり返す。まさかこんなに緊迫した状況になるとは予想していなかった。 僕も意見しようとするのだが、興奮しているためか言いたいことが英語にならなくて、 拳ばかりに力が入る。 険悪なムードが流れる中、ブラジル人の数人が教室に戻って来た。陽気で楽天家の彼らは、 なかなか時間通りにことを運ぶことが出来ないらしく、決められた授業再開の時間に席についていることはめったにない。 彼らにはこの騒ぎがなんだかわかるはずもなかった。 ますます熱をおびた口論はクリスティーンさんとクリフの一騎打ちの様相となった。 「じゃあ、私たちはどうすればいいのですか。」 「どうすれば、と言われてもね。私は私のやり方でやるしかないですからね。」 「あなたはこのまま、こうやって授業を続けて行くというのですね。」 「当然です。これが私のやりかたなのですから。」 「もう私はがまんできません。帰らせていただきます!」 イギリス軍がガンとして態度を変えないので、遂に血の気の荒いラテン系フランス軍は決裂を宣言してしまった。 クリスティーンさんがバタバタと荷物をまとめていると、彼女の隣に座っていた教会に従事するかわいいスペイン人のオバチャン、 シスター・モデスタが淋しそうな顔で十字を切り、小さい身体を小さく丸めて手を組んだ。Oh, my God… 窓の外で吹き荒れる風のようにクリスティーンさんが教室を出ていってしまい、どうにも暗いムードだけが残った。 残された僕達はどう対処したらよいのかとまどっているうちに、驚くほどあっさりと気を取り直したクリフは、 呼吸を整えながら授業を再開した。こういう騒動には慣れているのだろうか。そこまで情熱を失ってしまっているのか。 さすがにひきつった目尻は隠せなかったが。 ここが公立の、受講料も安いボランティア的要素が強い学校で、 僕達くらいの基礎レベルの生徒では勉強する目的意識はまちまちで、人種も違えば宗教も違う、 年齢層もバラバラとなれば、先生も教え方が安易ではないことは理解できる。 イギリスで英語の勉強をする外国人の多くは、ケンブリッジ大学が主催する英語検定試験中級の取得を目指しているという。 その目標が目の前にあるようなクラスなら、教師も生徒も気合いの入り方が違うのだろうが、 そんな試験とは程遠いレベルのクラスには差し迫った具体的な目標というものがない。 期末試験があるでなく、ただなんとなく来ている生徒も多い。 そういう環境でそういうクラスを長年受け持ってきている人間に情熱を求めるのは無理な注文かも知れない。 だとしたら、それはとても悲しい。 授業が終わり、僕はフローリアンと一緒に駅に向かって歩いていた。あいかわらず強い風が吹き荒れていて、 帽子を飛ばされないうようにするのが大変だった。 あの騒動の中で何ひとつ発言もできなかったことで気が重かった。もしちゃんと英語が話せたら、 こんな騒動もうまくまとめることができる自信があっただけに悔いも大きい。 「それにしてもクリスティーンのことは残念だなあ。彼女、もうこのクラスに戻って来ないのかなあ。」 横断歩道を渡りながら僕がポツンとつぶやくと、フローリアンがこう答えた。 「どうだろうね、クラスを替えようにも他のクラスもいっぱいみたいだし。 いずれにしてもクリフはクリスティーンのことをあまり心良く思ってないんだよ、きっと。というのも、 彼女の旦那は、ドーバー海峡の下を通すトンネル工事のフランス側の人間らしくて、 クリフはあのトンネルを通すのに反対しているらしいんだな。」 思わぬところでイギリスとフランスの敵対感情の一端が顔を出した。 この両国には何度も刃を交わした歴史もあるから、僕達には理解しえれない複雑な感情がお互いにあるのだろう。 イギリス人というのは、イギリスはイギリスであってヨーロッパではないと頑固に思っている国民性をもっている。 それが証拠に、EC(ヨーロッパ共同体)に加盟することを最後まで拒んでいたのがこのイギリスである。 日本とはちょっと毛色の違った島国根性とでもいうのか。 だから、現在進行中であるイギリスとフランスをトンネルでつなげるユーロ・トンネルについても、 もう工事は始まっているのに未だ乗り気でないのがイギリスなのである。フランス側の工事は着実に進んでいるのに、 イギリス側は一向に進まない。そんなトンネルを作って、またドイツが攻めて来たらどうするつもりだなどと気炎をあげる人も多いらしい。 そのトンネルを使ったロンドン、パリ間の超特急列車計画も、イギリスが途中から金を出さないなんて言いだしたものだから暗礁に乗り上げてしまった。そんな国民性の違いが、今回の騒動の要因になっていたとすれば、それも悲しい。 僕自身も、クリフと接して3週間、彼が僕達日本人のことをあまり心良く思っていないということを感じていた。 あからさまな嫌がらせをするとかそういうことではないが、ちょっとした僕に対する態度にそれが現われる。彼だけに限らず多くのイギリス人、あの、ドーバーの入国審査官もそうだったが、世界という土俵で、経済大国の名の下で日本が幅を効かせているのがどうにも気に食わないようである。それは一時でも世界の頂点を極めた彼らのプライドでもあり、現在の衰退からくる嫉みでもあるのか。だとすれば、それはすごく悲しい。 クリフさん、僕はあなたがたイギリス人と、ヨーロッパの人々と戦うためにロンドンに来たのではありませんよ。 あなたがたに僕たち日本の良さを知ってもらいたくて僕は英語を学んでいるのですよ。 「想像してごらんよ、国なんてものはないんだぜ」 20年前、ジョン・レノンはそう唄った。確かにそうである。 フローリアンの母国スイスでは、同じ街にドイツ語を喋る人とフランス語を喋る人が一緒に生活していて、 南に行けばそれにイタリア語を喋る人が加わると言う。どの言葉を喋ってもスイス人なのである。 国境線なんてものは人為的に作られたものだ。とは言っても、たった20人のこのクラスの中でも、 高速フェリーを使えばたった40分で渡れるドーバー海峡はまだまだ広く、 直行便のジェット機に乗ればたった時間で着いてしまう日本はあまりに遠い。 僕は年令も職業も国籍もバラバラの人たちが集まったこのクラスを結構気に入っていた。 クリフともいつか打ち解けられそうな気もしていた。目の色も髪の色も肌の色も言葉も習慣も食べ物も違う人同士が、 お互いの良さをわかり合うにはまだ時間がかかりそうだが、美しいとか素晴らしいとか感じる心は人種も国境も越え同じはずだ。 なんとかうまく事が進んでくれたらなあ、と願うばかりであった。 アルバイトに出かけるフローリアンとバロンズ・コートの駅で別れた僕は、 地下鉄でロンドンの中心部にあるボンド・ストリートに向かった。 大晦日の夜に知り合ったクラシック・ピアニスト、レイコさんのギャラリー・コンサートを聴きに行くためにだ。 ドイツ軍の空襲にもびくともしなかった地下鉄だけが台風にも負けず正常に運行していた。 ピカデリー・サーカス駅から地上に上がると、道行く人はみな、前のめりになって歩いている。風雨入り乱れるといった 日本の台風みたいな激しさはなく、やたら風ばかりが強い。2回、帽子をふっ飛ばされながらもそのギャラリーに着くと、 台風のためにコンサートは中止との張り紙。ギャラリーには誰もいなかった。 しかたなしに家に戻ろうとオックスフォード・ストリートに出てみると、 夕方の帰宅ラッシュの時間だというのに2階建ての赤いバスの姿が通りにはなく、 どのバス停のまわりもバスを待つ人たちでごった返している。ロンドンはどこもかしこも大荒れだ。 ふと英語クラスでの騒動を思い出しながら、ジョン・レノンの「イマジン」を口ずさむ。 想像してごらんよ 天国なんてものはないんだぜ やってみれば簡単なことさ 僕たちの足元に地獄なんてものもなく 上には空があるだけさ 僕もそう願いたいよ、ねえ、ジョン、と空を見上げたら、また帽子をふっ飛ばされた。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
