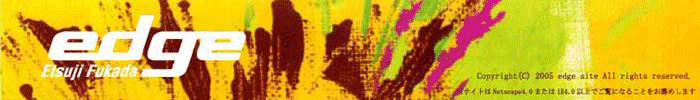同じなのに違う空の下 edge in London '89'-90 #4 |
Part 1/ 38 St. Lowrence Terrace<4> |

途方に暮れていると、大家のおばあちゃん、フィリスさんが、息をきらして上がってきた。
60代後半か、小柄でしゃきしゃきしたフィリスさんは、とにかく早口で、なにしろ自分のペースで話しまくる。
「よく来たわね。オー、ごめんなさいね、まだ掃除は終わってないわ。というのも、夫のジムが病気でね、
そう血液の病気なのよ。この間会ったからわかるでしょうけどほとんど寝たきりなのよ。調子いいときは部屋の中くらいは歩けるんだけど。それがこの2、3日調子が悪くて病院に連れていったり、それは大変だった
のよ。あら、このランプ・シェード汚れてるわね。取り替えなくちゃ。そう新しいのが用意してあるのよ。
ジムが元気だった頃は彼が全部やってくれてたんだけどね。今日はとても冷えるわね。そうそう、シーツと
毛布は後で持ってくるわ。オー、ごめんなさい、そろそろいかなくちゃ。ジムは私がそばにいないと怒るの
よ。また、後で来るわ…。」
フィリスさんは話しながら掃除をしようとする素振りは見せたが、結局は言うことだけ言ってそそくさと階段を降りていった。
実際にはもっとたくさん話していったのだが、なにしろ早口で、僕の語学力ではすべて聞き取れる代物では
なかった。
ア然としてる僕のことなどおかまいなしで、とにかく忙しそうで、次から次へと思考が巡っていってしまっ
て自分ではどうにもならない、そんな風だった。
最初は“約束とちがうじゃないか!”と日本語でどなってやろうかとも思ったが、話を聞いているうちになん
だかあわれになってきて、まあいいやって気分になってしまった。
こんな老人をいじめてなんになると。
この部屋の広さで、管理がきちんと行き届いていたら、家賃が週40ポンドなんてことはありえないのは、
幾度かの部屋探しの経験でわかっていた。
病気の夫を抱えた老いた女性ひとりでアパート経営どころじゃないのだろう。
これも試練だと思うしかなかった。
まだ、住むところがあるだけでも幸せなのかもしれないと、なんとか重い腰を上げた。
すさんだこの部屋でまず最初にやったことは、黄色い水仙の花を飾ることだった。そして、
3束あったうちの1束を持って一階に下りて、大家宅のドアをノックした。
ドアの隙間から顔を出したフィリスさんに、ジムさんへ、と花束を渡した。
フィリスさんの顔に、偽りのない夏空のような笑顔が広がった。
それでいくらか僕の心にも暖かさが戻ったような気がした。
部屋に戻り、まず薄汚れたキッチンから掃除を始めた。
ラジオから流れるポップ・ミュージックにはげまされ、なんとか寝られる程度に部屋が片付いたのは夕暮れ
迫るころだった。
ふうと、大きく溜息をついて部屋を見渡していたら、朝から何も食べていないのに気がついた。
こんな日にひとりで食事するのはとてもわびしいものだが、どういうわけか誰にも会いたくなかった。
こんなに沈んだ自分を人に見られたくなかった。
これじゃまるで5月病にかかった大学生ではないか。
かといってこの部屋で何かを作って食べようという気も起こらない。
外に出たかった。
朝、載ってきたのと逆ルートのバスに乗って約10分、クィーンズ・ウエイ まで出る。
乗降用のドアのない二階建ロンドン・バスが信号で停車しているうちにバスから飛び降りてレストランが並ぶ通りへと入っていく。
ポケットに手を突っ込み、伏せ目がちに人ごみをすり抜けて行く。
ワンタン入りのヌードルスープ、いわゆるワンタン麺かなんかで軽く食事はすまそうと、夏の間、彼女とよく行ったチャイニーズ・レストランへ向かう。
だけどおりしもディナー・タイムで、小さなその店の前には順番を待つ人達が溢れていた。
待とうかどうか考える以前に気分が萎えた。
一度目標を失ってしまったら、もうどうでもよくなってしまった。
それでファースト・フードのハンバーガー・ショップに入った。
フィッシュ・アンド・チップスとチキン・バーガーを食べ、インスタントみたいなコーヒーを飲んだ。
うまいともまずいとも思わなかった。
不用意に明るい蛍光燈の灯の下で黄色と白で彩られたプラスティックの椅子やテーブルが、安っぽいBGMと見事にマッチして、こういう場所を考え出したアメリカという国はなんてセンスのない国だろうと思った。
そんな場所ばかりになってしまった日本はどうなってしまうのだろうと憂鬱になった。
なんで自分はこんなところにいるのだろうと思った。
でも、今の僕にはそんなハンバーガー・ショップが見事なまでに似合っているに違いない、そう思った。
また、ふうと大きな溜息をついて店を出ると、ヒデト君のことを思い出した。
前日の昼間、引っ越しの荷造り、といってもスーツ・ケース物を詰め直すだけだったが、
それも大方終わった頃、ヒデト君から電話があった。
「もしもし、ヒデトです。どうですか、引っ越しの準備は。何か手伝う事はありませんか?」
「いや、ほんとスーツケース一個だから大丈夫だよ。」
ヒデト君はロンドンに来て6ケ月。日本でポピュラーミュージックの作曲家を目指していて、毎日、日本から持ち込んだ録音機材で曲作りに励んでいた。
僕より3歳年下で、1週間後に日本に帰ることになっていた。
彼とはロンドンに来てから友達を介して知り合った。
ちょうどその頃の僕はアパート探しに奔走し、なかなか条件にあった物件が見つからずあせっていた。
ヒデト君は、このクイーンズ・ウエイの近くのベッド・シッターに住んでいた。
おせじにも広い部屋とは言えず、ベッドが部屋をほとんど占領していた。
建物の3階にある北向きの部屋で、一つひとつの部屋の天井が高いのか、通りに面した窓から下を見下ろすとそうとうな高さがあった。
なかなか思い通りの部屋が見つからず、不動産屋さん回りに疲れていた僕に、ヒデト君は自分の部屋を引き続き借りてはどうかと提案してくれた。
僕にとってその部屋は広さからいえば満足のゆくものではなかったが、最大の魅力は、決めてしまえば幼稚園児並みの英語を引っ提げて不動産屋をまわらなくて済むことと、ヒデト君が引いた電話がそのまま引き継げるということだった。
まあいいっかって感じで、僕は半ばヒデト君の部屋を引き継ごうと決めていた。
その部屋の大家の都合で借りるかどうか返事をしなければいけない日の前日、今度は違う知り合いから、友達夫婦が間借り人を探しているらしいという話が舞い込んだ。素性の知れたきちんとしたイギリス人と一緒に生活が出来て、しかもその人はものすごく音楽にくわしいという。
僕にはこの上なく条件の良い話だった。
ただその話は2、3日後、彼らが旅行から帰ってこないと確かな事がわからないということだった。
あまりに急な判断を迫られ、悩んだあげくヒデト君の方をことわることにした。
ことわった翌日、イギリス人夫婦の話が先方の都合でダメになった。
あわててヒデト君に電話し直すと、もうすでに次に借りる人が決まっていた。
楽をしようとしてバチが当たったというところか。
そんなドタバタのあげく、すべては振り出しに戻り、また不動産屋をまわりを始めた。
そして土壇場で探し当てたのがセント・ローレンス・テラスの部屋だった。
急展開でダメになった“魅力的な話”がなかったら僕はヒデト君の部屋を引き継いでいた。
受話器の向こうのヒデト君の声には妙に張りがなかった。
「イヤ、実を言うと、昨日の夜の話なんですけどね…、僕の部屋の窓から隣の部屋のブラジル人が落ちて死んでしまったんですよ。」
「エッ!?死んだって…、なにそれ。」
「イヤ、その、夜ね、結構遅かったんですけどね、曲を書いてたら誰かがノックするんですよ。誰かと思ったら隣の部屋に住んでるブラジル人で、部屋の中に鍵を忘れてドアが閉まってしまったっていうんですよ。
うちはどの部屋も全部オート・ロックになってるもんで。それで窓が開けたままになっているから、僕の部屋の窓から出て壁づたいに自分の部屋に戻りたいっていうんで、まあ、どうぞ、どうぞって通してやったわ
けなんですよ。僕はそのままキーボードを弾いていたんだけど、そしたら悲鳴が聞こえて、なんだと思って立ち上がったら、そのブラジル人が…。手をかけた雨トイが完全に腐っていたらしいんですよ、そのまま、
前に止めてあった車の上に…。目があっちゃったんです、彼が落ちる瞬間。それから警察に電話して、事情聴取受けたりしてなんやかんや、そんなんで一睡も出来ずで…。別にそんな仲が良かったわけでもなかったんですけどね、やっぱりね、嫌ですよね。それで、なんかひとりで部屋にいたくなくってこれからどこか出かけようと思って、で、手伝うことがあればなあと思って電話したんです。」
そんな信じられないような話を聞いて、その亡くなったブラジル人には悪いが、あの部屋を借りれなくてよかったと思った。
誰だってそんな事件が起こった部屋には住みたいとは思わないだろう。
そんなショッキングな事件に遭遇してしまったヒデト君を食事にでも誘ってあげるべきだったんだろうがが、
ちょうどその日は僕と彼女にとってロンドン最後の日で、夜はコンサートのチケットが取ってあったし、
その前に友達と会う約束もあり、ちょうど出かけるところだった。
どうしたらよいものか戸惑って言葉がとぎれた。
「じゃあ、明日、新しい部屋に移ってから手伝うことがあれば電話ください。」
こちらの都合も察してくれたのか、ヒデト君はそう言って電話を切った。
だから、明日にでも電話でもして、もしいたら食事に誘ってあげようと思っていたのだが、その日の僕はそんな人でさえ慰めてあげられないほど心がしぼんでいた。
とぼとぼと部屋に戻り、なんとなく映画”パリ・テキサス”のサントラ盤を聴きながら、普段はあまり吸わないタバコを吸った。
ライ・クーダーの切なげなスライド・ギターは夜の街の囁きとタバコの煙の間で揺れる。
窓の外には昨日まで知らなかったロンドンの夜が広がっていた。
街灯の灯は牛乳の中にピーチとオレンジが混ざったような乳白色で、街を優しく包んでいた。
その灯で両脇をふちどられた西向きのまっすぐな通りは、まるで夜空に向かう滑走路のようだった。
灯を消すと、街灯の灯が静かに部屋を包む。
カーテンを閉じ、スプリングの弱ったシングル・ベッドに沈んだ僕は、3階から落ちて行くブラジル人と目が合ってしまったヒデト君の事を考えた。
明日は電話してあげよう。
何がしてあげられるわけじゃないけど。
その夜、空を飛ぶ夢を見た。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|