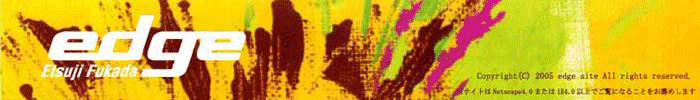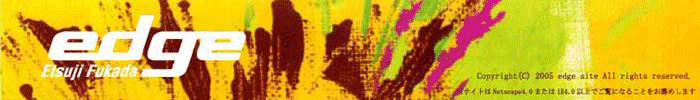同じなのに違う空の下 edge in London '89-'90 #7 |
Part 2/ ポートベロー・ロードの魔術師 <2> |

僕の部屋から直接ポートベロー・ロードは見えないが、その日になると、なんとなく町中がうきうきした
雰囲気になり、これといった用がなくても散歩がてら通りに出るのが習慣になりつつあった。
古着の店が集まっているテントのあたりで、古いジャズのレコードを見ていると、人波の間からマリコさんが
やってくるのが見えた。手を振る僕に気づいたマリコさんは、いつもの笑顔を顔いっぱいにひろげた。
「 OH! Hallo, なあっにしてんの?」
「別に用はないんだけど、土曜っていえば市場に出てこないと悪いような気がしちゃって。マリコさんは人形
の材料の買い出し?」
「ううん、おにんぎょさんの材料は土曜に来てもだめよ。よさそうなのは金曜の午前中にみんな
なくなっちゃう。今日は、朝からマジメにおにんぎょさん作ってたんだけど、きのうここで見つけたスカートが
気になっちゃて、ああ、今もまだ迷ってるんよ。かっちゃおうかなあ、どうしようかなあ。もう、売れてたりすれ
ばあきらめもつくんだけどね。」
彼女は人形を作る時の作業着であるエプロンをつけたまま歩いていた。そういうのが絵になる街である。
マリコさんは日本からアメリカ経由でロンドンに渡って 12 年あまり、人形作りのアーティストだ。
ポートベロー沿い、アンティークの店が集まるノッティング・ヒル・ゲート寄りにあるフラットに
ネコ2匹と一緒に住んでいる。
「ネエ、ちょっと一緒に、そのスカート見てくんない?」
長い髪を後ろに束ねて、漫画のポパイに出てくるオリーブ・オイルそっくりのマリコさんは、慣れた足取りで
お目当ての店に向かって行く。ハンガーにかかった古着がどっさりぶらさがっている中から、
彼女は赤いキュロット・スカートを取り出した。
「ネエ、これどう思う?かわいいでしょ?でも 12 ポンドか … 、どうしようかなあ。」
こういう場合、一応男から意見を聞きたくなるのが女心というものらしい。
しかし、たとえ意見を述べたとしても、その意志が変わることがないのも女心である。
古着なのだから、値段なんてあってないようなもので、叩けばなんとかなりそうなものだが、
以前このポートベローに自分で作った人形を売る店を出していいたことのあるマリコさんは、ここでの商売の
厳しさを知っている。それだけにズケズケと値切ったりができない。彼女は何度も鏡の前でスカートを当てな
がら悩んでいたが、店のおばちゃんが “ それ、 10 ポンドでいいよ ” と言ったのにあっさりと決断はくだされた。
消費欲が満たされた時の女性は本当に幸せそうである。
マリコさんのワードローブはほとんどといっていいほど、このポートベロー・マーケットの古着で構成されて
いる。ファッション雑誌のいうがままにしか服を選べず、誰が誰だかわからないような日本の女の子達に見
せてあげたいほど、彼女のファッションは個性的で素敵である。
「スカート、買ったらすっきりしたわ。ついでにおなかもすいてしもたわ。お昼食べに行こうよ。」
僕達は ” マイクス・カフェ ” というスナック・バーに入った。
キッチンから聞こえてくる言葉の強いアクセントから、この店はスペイン人がやっているのがわかる。
僕達はビーフの煮込みとチキン・ピラフをシェアすることにした。
「このところ通訳のアルバイトが忙しかったから、なかなか。人形作る時間がなかったのよ。だから、今日は
真面目にやるぞと思ってたのに … 。ゴハン食べたらまたいっしょうけんめいやろっと。」
彼女を紹介してくれたのは、最近日本で舞台演出家としてめきめき台頭を現わしてきたアモンで、
僕のロンドン行きに大いに賛同してくれた友人のひとりだ。彼も3年前、1年半に渡りこのロンドンで生活して
いた。マリコさんはその時の友達というわけだ。
マリコさんの作る人形はアンティークなドレスに身を包んだエキゾチックな女性達だ。
社交界で華開くような華麗さとは裏腹に、その材料は生活に密着したものばかりで、
たとえば帽子かけだとか、コンクリートを流し込んだ植木鉢が土台になった鉄の棒だとかが
人形の支柱になる。その素材はたいてい道端に捨ててあったとか、工事現場の瓦礫の中から見つけたとか
そういうものである。捨てられていた時の曲がり具合が人形のポーズを決める。
石膏で固められた胸頭部が、ポートベロー・ロードの市場なんかで集めたアンティークの生地で飾られてゆく。
物言いたげな瞳はドレスや帽子の色とコーディネートされ彩られる。虚ろに空を見る女、横顔で涙を流す女。
彼女の人形作りはひょんな事から始まった。
10 年ほど前、すでにロンドンに住んでいたマリコさんは、突然アフリカが見たくなり、独りヒッチハイクで
アフリカを目指した。まったく計画性のない旅は、思いがけない事件を巻き起こす。アフリカに渡る地中海の
船上で、空が黄色くなるほど何万匹の蝶の大軍と遭遇したり、アフリカに渡り、暗くなり野宿してたらどうも
まわりの様子がおかしい、よく見ると何かがわさわさしている、翌朝わかったのだが、そこは 1 メートルもあり
そうな巨大な蟻塚の横だった、とか、都会の生活じゃ考えられないような体験をしたという。
そんなアフリカからの帰り道、マリコさんは一文なしになっていた。
なんとなく地図を見ていたら、ちょうどその時がワインの葡萄の収穫時期だということを思い出した。
葡萄の収穫時期はどの村でも猫の手も借りたいほどの忙しさだという。彼女は、収穫の手伝いをすれば
一儲けしてロンドンに戻れると閃いたのである。行きゃあなんとかなるだろうと彼女はまたまたヒッチハイクを
して、ワインで有名なフランスの田舎町を目指した。
なんとか目指す地方にたどり着いた彼女は一軒のワイナリーの門をたたいた。ところが、その年は
天候不順で収穫が1ケ月遅れていてまだ仕事はないとのこと。途方に暮れた独りぼっちの東洋人の彼女を
不憫に思ったのか、そこの親切なご主人の提案で、どうせ収穫の時には人手がたりなくなるのだからと、
彼女は収穫まで家に置いてもらえることになった。
そんな訳で彼女はしばらく食事とベッドには困らなくなった。
毎日、たいしてやることもなくブラブラしていた彼女はむしょうにタバコが吸いたかったが、ゴハンをタダで
食べさせてもらって、まさかタバコ銭までくれとは言えない。吸えないと思うとよけいに吸いたくなるのが
人間である。
そんなある日、村では子供達のためにあやつり人形の芝居が開かれていて、その前を通りかかった彼女は
またまた閃いた。こんな人形を作って、ワイナリーに見学にくる観光客に売ったらタバコ銭くらいにはなるの
ではないかと。さっそく彼女は近所の家をまわり、材料になりそうなボロきれ、古新聞なんかを集め、製作を
開始した。思い付くまま作ったあやつり人形だったが、思いのほか出来栄えが良く、結局店を出す前に、
そんな彼女をおもしろがって見ていた村の人達に全部売れてしまった。予想以上の収入を得た彼女は、
収穫を待つことなくロンドンに戻ってきたという。
ロンドンに戻った彼女は再び操り人形を作り、ポートベローの市の時に店を出してみた。それから人形作り
が彼女の仕事となった。
しばらく何年かあやつり人形を作り売っていた彼女だったが、毎週毎週出来たと思ったらすぐ誰か知らない
人に買われてゆく、そんな繰り返しがどうにも淋しくなり、作品としての人形を作りたいと、店を出すのを
やめた。生活のために通訳の仕事を始め、じっくり腰をすえて人形作りを始め、数年前に自力で展覧会を
開いた。
今、彼女のフラットのリヴィング・ルームに並ぶ人形達はその後のものだ。前の展覧会に出品された作品は
写真しか残っていないが、あきらかに現在のものとは作風が違うし、どれも小降りである。現在の作品は
彼女より背の高い物も多い。彼女曰く、人形も成長しているのだそうだ。
彼女をアーティストとしての成功者と呼ぶにはまだ早いだろう。前のエキジビションの際には雑誌に取り上
げられたりもしたが、彼女の実力が認められたとは言いがたい。だからこそ彼女の将来が楽しみだ。
彼女のアトリエは1DKのフラットのベッド・ルームだ。彼女は言う。
「お金は生活できるだけあればいいわ。もっと広い家に住みたいとかそういうことも思うけど、もし本当にそう
するためには、それだけの時間をお金を稼ぐためだけに費やさなきゃいけないじゃない。そうしたら人形を作
る時間がなくなるもの。そんなのバカげていると思わない?もちろん今のままでいいとは思ってない。そう、
ちゃんと人形だけで稼げるようになったら、人形専用のアトリエのある家に住みたいわ。」
食事を終えた僕達は、再びポートベローに出た。ここはマリコさんには庭みたいなものだ。あちらこちらで
知り合いに会い、きさくな挨拶がかわされる。マリコさんはついでだからと野菜とかパンとかを買い、花屋の
前で足を止めた。そして、大ぶりな百合の花を買った。彼女はカーネーションとか菊みたいな花は好きでは
ないと言った。荷物が彼女の腕の中であふれそうになり、花を持ってあげようとしたら、彼女は優しく首を
横に振った。
「花だけは持っていたいの。」
生活のすべてがこのポートベローとつながり、そのさりげない生活の中から華麗な人形を作り出す
マリコさんは ” ポートベロー・ロードの魔術師 ” だ。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|