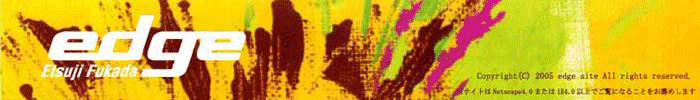
同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #13 |
Part 8/ Goodbye 80th And Wellcome 90th /80年代最後の日、90年代最初の日 |
ロンドンは暖かい。 12 月 28 日からの3日間をパリで過ごし、 31 日、日本流にいえば大晦日のお昼過ぎの便で帰ってきた僕は、ヒースロー空港の第4ターミナルのバス乗り場で市内行きのバスを待っていた。着ていた厚手のコートが不似合いな鈍い冷たさの風がそよいでいる。 パリは寒かった。 緯度から言えばパリの方が南にあるのに、ロンドンなど比べ物にならないくらいの底冷えであった。あれが大陸の寒気というやつなのか。寒さの質が根本的に違っていた。 思い立ったようにクリスマス明けに訪れたパリは、これで3度目。 去年の夏、独立 200 年祭を翌年に控えた凱旋門はお色直しの工事用のネットの中だった。祭りも終えた冬、もちろんネットはなく、寒さが結晶となったように霞む空気が凱旋門を包む。低く垂れ込めた霧のような雲はエッフェル塔の上半分を覆い隠し、塔に記された建国 200 年 の電飾サインがボンヤリと浮かぶ。夜ともなれば、シャンゼリゼ通りからなにから、白い電球の洪水が街中を埋め尽くす。その電球の数は半端ではない。クリス マスとニュー・イヤーのために輝く光に余分な色は存在することすら許されない。あたかも街にたちこめる霧をも計算にいれたような白く幻想的な世界。僕はた だただ見とれるばかりだった。 去年の夏のパリの印象は、仕事で滞在していたせいもあるのか、この冬の完璧な美しさと比べると少し違っていた。 僕は時任三郎のマネージャーとしてコマーシャルの撮影のために約 10 日 間、洗練された構図を求めて市内のあちこちを走り回った。撮影中、マネージャーにはこれといった仕事がない。日本のいる時のようにポケット・ベルに神経を 削られることもないので、仕事が打ち合わせ通りうまく運んでいるかを見守るだけでよかった。そうするとひとつの場所で動かないでじっとしていることが多く なる。撮影は路地裏とかでも行なわれる訳で、そんな所にしゃがみこんだりしていたりすると、観光なんかで歩いている時には気づかない細かい所を見てしまっ たりするのだ。 なんだか汚ねえ街だなと思った。遠目には荘厳な雰囲気を醸し出す古い建物の軒先がハトのフンだらけだったり、歴史的建造物 という塔の内部にむせかえりそうなアンモニアの匂いが詰まっていたり、フィルムのコマの中には決して現われない現実が転がっていたりする。犬を散歩させる 人にとって犬の排泄物はいつか消え去る物であり、吸い終えたタバコは通りに投げ捨てられる物と考えられているようだ。アスファルトに覆い尽くされた都市に は、そういう物が土に戻る隙間は残されてはいないというのに。凱旋門の上から見渡せば、みとれてしまうように美しい街並みの裏側にはそんな世界がある。 深い歴史の上に築かれた街に、今だ消え去る事のないデカタンスの匂い。一言ではとうてい言い表せない矛盾した美意識。 あの夏のパリは、前夜のパーティーの狂乱で目の下にくまができて、髪は逆立ち、パジャマの胸がはだけズボンはずり下がり、ベットから出るなりタバコに火をつけてしまう、でも愛さずにはいられない、そんな熟した女の魅力だった。 そう、あの後だ。あのパリから帰った後だ、僕がヨーロッパの風の中に身体を浸してみたいと思ったのは。 自分の中に流れる矛盾した感情の渦。夏の終わりのある夜、ひとり布団にくるまり、エアコンが虚しい呻きをあげる暗い部屋 で、ヨーロッパに住んでみようと決めたのだ。ヨーロッパの何処かの街にある安アパートの部屋でひとり眠る自分を想像した時は、にわかに心臓が高鳴り、かす かな震えが身体を襲った。 パリに刺激されてヨーロッパに行こうと決めたのに、結局考えた末、ロンドンに住んでしまった僕である。数ケ月前まではパリ もロンドンもよく似たヨーロッパの街だった。ところがロンドンの風景を目に焼き付けてしまってからこのふたつの街を見ると、歴然たる違いがあるのに気づ く。重厚な男らしさを主張するロンドンの街並みに対し、パリの街は柔らかく華麗で女性的だ。それが直感として捉えられたのも、僕の皮膚がヨーロッパになじ んできている証拠かも知れない。 「このバスはヴィクトリア・ステーションに行きますかね?」 バス・ストップでコートを脱いでいたら白人の老夫婦にそう尋ねられた。 「いや、ヴィクトリア・ステーション行きだったら、向こうのバス停です。」 住んでまだ5ケ月、今だ浮足立ったままのロンドンだというのに、まるですべてを知り尽くしたような顔で答えていた。英語も まだまだ話しているうちには入らないような物だが、フランス語に比べたら天と地の差がある。そんなパリから帰ってきた直後だということもあるのか、住み慣 れた我が街にいるようだ。たった5ケ月でこれである。この先何ケ月後になるのかわからないけれど、新東京国際空港のバス・ストップに立った時にはどんな感 触が生まれるのだろうか。 赤い2階建てバスが停留所に入ってきた。空港と市内を結ぶ “ エア・バス ” も ロンドン名物の2階建てバスだ。4ポンドを入り口で支払い、荷物は1階の荷物置き場に置いて2階にあがる。幸い一番前の席が開いていてそこに腰を降ろす。 僕はこの2階建てバスに乗るとき、空いていれば必ずこの席に座る。なんだか子供みたいだけど、一番前の席だったら視界も広いし、高いところからの視点はあ らたな発見をもたらしたする。 バスは走りだし、もうひとつ別のターミナルに寄ってモーター・ウエイに入った。晴れてはいないけれどボンヤリと明るい午後であった。 かなり見慣れた景色をちらちらと見ながら、友達が日本から持ってきてくれたエスクワイア日本版のロック特集の記事を読んでいた。 80 年代のロック・ミュージックの総括のような特集であった。 80 年代が終わろうとしている。 ちょうど 10 年前の今ごろ、 70 年代が幕を閉じ 80 年代が始まろうとしていた時期に、僕はミュージカルのオーディションに合格し、ポピュラー音楽の世界に足を踏み入れた。 21 歳の時の事だ。その舞台で知り合った時任三郎が僕の 80 年 代を語る上で、欠くことのできない存在となる。そのミュージカルの舞台を終えた後、僕はロック・バンドを作り、自分達の活動と共に、俳優としてレコード・ デビューすることになった三郎のステージをサポートした。僕達は確実に親友だった。その後、バンドの活動が息詰まってうだつのあがらない生活をしていた 25 歳 の僕を、自ら設立しようとしてた会社のパートナーとして迎えてくれたのも彼だった。時任三郎と僕、そして事務の女の子というたった3人の会社だった。僕は 彼から仕事の厳しさを学んだ。そのために僕達は友達などというなまやさしい関係ではなくなってしまったけれど。そして5年、結果的には僕はアイツが理想と して求めていた手足にはなれなかった。結果を出すには早すぎるのもわかっていたけれど、それ以上に僕は自分を取り戻す必要があった。今年の7月、会社を辞 め、彼のもとを離れた。彼と知り合って 10 年近い月日が過ぎ去った。僕は今でもアイツのことを親友だと思っている。これからもそうありたいと思っている。そしていつかこの 10 年の恩は返したいと思っている。だから今は距離が必要だ、そう思っている。 目は雑誌の活字に向かっていても、頭の中は自分の 80 年代を思い返していた。 20 歳の僕はその頃、 30 歳になろうと思った。これといった根拠はなかった。ただ惨めな 30 歳にはなるまいと思った。とんでもなく大人に見えた 30 代の人々。あの時頭に浮かんでいた 30 歳とは、こんな自分だったのだろうか。 10 年たって思うことは、まだ何も始まってはいないし、まだ何も終わってはいない、そういうことだった。 窓の外の風景が走り去るのと共に、刻々と 90 年代が近づいてくる。 ホーランド・パークでバスを降りて、ベエさんの家に立ち寄る。彼と彼のフィアンセはお正月を日本ですごすために、僕がパリに 行っている間にロンドンを離れていた。事前に預かっていた鍵でベエさんの車、オースチンのミニのエンジンをかける。この車は2月から僕の物になることに なっていた。仕事のために2年程イタリアに住むことになったベエさんからこの車を買わないかと持ちかけられたのが今月の始めだった。まさかロンドンで車を 持つなどということは考えていなかったのでかなり悩んだけれど、車があれば今までとは違ったロンドンを見つけることが出来る、そう思い譲ってもらう事にし た。とりあえず彼らの不在中、彼らのネコの世話をする代わりに車を使ってもいいということになっていたので、さっそくフラットの前に駐車してあったミニに 乗ってセント・ローレンス・テラスの部屋に戻った。 ひとりの部屋はいつもどおり静かで、毎年、日本で感じていた大晦日の午後という感じがまったくなかった。僕達は社会という 鎖の中にはまって生きていたのだなあとあらためて思う。街全体が似通った価値観をもってお正月という日に向かって行くからこそ、その日が特別な日になるの だ。ひとりでなにも考えず、社会にも触れずにいたら、盆も正月もクリスマスもなく、ただ1日が過ぎて行くそれだけのことである。 午後3時になろうとしていた。日本との時差が9時間あるから、日本はちょうど今ごろ新年を迎えるのだ。きっとテレビがいろんなお寺の除夜の鐘の中継をしている、あの夜だ。生まれて初めて、そうじゃない大晦日を過ごしている。 いくつか手紙が届いていた。どれもずいぶん前に日本を発った手紙だった。クリスマスの前はおびただしい数のクリスマス・ カードでポスト・オフィスがパニックになるため、郵便物が思い通り届くなんて事は不可能に近いという。日本の年賀状は元旦に届くように出すものだが、クリ スマス・カードはクリスマス前に届くようにするのが常識らしい。考えてみれば、クリスマスの日に働く人は誰もいないのだから、その日に配達されるはずもな いか。 こんな生活をしていると、日本の切手の貼られた手紙が届いているのを見ると思わず口許がゆるんでしまう。さっそく封を開け て、便箋の上の文字を追う。通信のメディアが年々増え続けているこのごろ、手紙の良さは不必要な手間がかかっているということだ。人の手によって飛行機に 乗ってやってきた手紙には通信という本来の意味以上のいじらしさがある。手書きならなおさらである。私的な手紙のワープロ文字ほど味気ない物もない。 全部読み終え、それぞれに返事を書き、封を閉じ、切手を貼る。手紙の交換というのは会話と一緒で答えが帰ってこないとそれ までのものになってしまう。また手紙を書いてきて欲しいのなら、返事はその日のうちに書き、ポストに入れることだ。いくつかの封筒を持って部屋を出た。 クリスマス以来、街はどことなくひっそりとしている。つい何時間か前までフランスにいた事が嘘のようだ。 封筒をポストに放り込み、そのまま電話ボックスに向かった。 “ もしよろしければ …” と、 今日の夜、こっちで知り合った日本人の友達から食事に誘われていた。歩きながら、まだ迷っていた。ロンドンに来て、日本人の知り合いばかり増えてもしょう がないじゃないか。でも行くか行かないかはちゃんと返事しなければ失礼だなあと思い、心定まらぬまま駅前の公衆電話のボックスに入った。 「クラシック音楽をやっている人を何人か交えて韓国料理屋に集まることになっているんですけれど、もしよろしければ … 。」 ソウイチロウ君はあいかわらず優しい口調で、無理強いすることなくやんわりと誘いを入れてくれた。クラシックの人って、どんな人達なんだろう。この街であまりに自然に存在するクラシック音楽に、このところ妙に興味をそそられていた所だったので、僕の心はぐぐっと動いた。 「もし、お邪魔じゃなければ、ご一緒させてもらおうかなあ。」 部屋に戻り、もろもろの用事を済せて、ミニのエンジンをかけた。途中の道が思いがけず渋滞していて、約束の時間より 15 分 以上遅れてレストランにつくと、もう僕以外の全員が揃っていた。それで僕は自然にレイコさんというピアニストの隣に座ることになった。彼女は僕より2歳年 上で、日本で大学院までを終え、5年前にロンドンに渡り、2年前にイギリス人と結婚したという。いわばエリートともいうべき経歴を感じさせない笑顔の素敵 な女性だった。彼女は恐ろしい程ポピュラー音楽に関して無知で、それがとっても正直でなんだかイイ友達になれそうな予感があった。 心の何処かにあった、クラシック関係というとカタブツばかりじゃないかという僕の心配はとりこし苦労に終わった。日本から レコーディングで来ていたヴァイオリニストのマリコさん、レイコさんの友人のピアニスト、ヨシコちゃん、ヨシコちゃんの友達でドイツで勉強しているタミコ ちゃんと日本からきた同級生ヤスコちゃん、そしてソウイチロウ君の大学の先輩シンジさん夫妻、みんな、東京では知り合うこともなかっただろう人達ばかり で、初めて会った人が多かったにもかかわらず、楽しい時間を過ごした。 食事が済んで、シンジさん宅で飲もうということになった。 シンジさんがお酒と一緒にギターを出してきたので、僕はクラシックの人達を前に、ポピュラー・ソングを歌うことになってしまった。 時計はいつのまにか 12 時を回り、イギリスも 1990 年を迎えた。 何曲かリズム・アンド・ブルースを歌った。そしてみんなが日本語の曲が聞きたいというので、クリスマス・イブの前の夜に完成したあの曲を歌うことにした。もちろん人前で歌うのは初めてである。
凍てついた 12 月の朝 僕はひとりで 夜明け前の空を見つめながら身動きもできず とらえようのない淋しさが音もなく襲いかかる むくわれそうにない祈りが この胸を縛りつける
きらびやかに光たたえた表通りは 数知れぬ苦しみをかき消すために時を忘れていた いくら歩き回ってみても僕の居場所は見つからず 遠くで響く鐘の音に君の救い求めていた
I EMBRACE YOU (君を抱きしめている) 聖なる夜を越えて I EMBRACE YOU 心つなぎ合わそう I EMBRACE YOU
たとえ人は何処にいても何をしてても 心の中に住みついている孤独から逃げられはしない それがわかりすぎているから今より強くなりたい それがわかりすぎているから君をもっと抱きしめたい
I EMBRACE YOU (君を抱きしめている) 聖なる夜を越えて I EMBRACE YOU 心つなぎ合わそう I EMBRACE YOU
凍てついた 12 月の朝 ひとりの僕は 夜明け前の空の中に世界中の悲しみを見たような気がした
歌いながら、この詞の中にこめたのと同じ孤独を感じていた。歌い終わって、暖かい拍手に大いに照れ、そしてギターを置いた。みんなはまたグラスを手にしてざわめきがもどってきた。僕は、そんなにひどくはなかったけれど、ある種の虚脱感を味わっていた。 「ねえ、いつも今の歌みたいなことを考えているの?」 たまたま隣にいたレイコさんが言った。 「うーん、どうなのかなあ。そうかも知れないし、そうじゃないかも知れない。」 答えになってるような、なってないような意味不明なことを僕は口走っていた。 「きっと、わたしのダンナと話が合うと思うわ。」 「そりゃあ、うれしいけど、俺、そんなに英語話せないよ。」 全然会話にはなってなかったが、お互い言いたいことはわかっていた。そのなんてことない会話で、彼女が敏感に僕の書いた詞の意味に反応しているのがわかった。 レイコさんは 20 代も後半になって、自分の意志でイギリスに出てきたという。きっと決断するのにずいぶん勇気がいっただろうし、こちらに来てからはひどい孤独を味わったに違いない。たぶん僕なんかよりずっと大きな孤独を。彼女の顔いっぱいの笑顔はそれを物語っている。 今日出会ったのは日本人ばかりだが、その何人かはここをベースに生活している人達だから、これもロンドンに踏み込んだことには違いない。 ウインブルドンに近いシンジさん宅を出たとき、もう午前3時を回っていて、何人かを車で家に送り、部屋に向かう頃には、もう夜明けの気配さえ漂っていた。さすがのパリも騒ぎ疲れて眠りこけているのだろうか。東京には車の少ない澄んだ空気に包まれた “ 昔の東京 ” が戻って来ているのだろうか。 街はずれのあちらこちらに、寝ぼけマナコのクリスマス・ライトが揺れていた。パリの官能的な光の世界にはない、ぼってりした安物のティー・カップの温かさにも似た情緒も悪くはなかった。 僕の 90 年代の最初のページはこうしてロンドンから書き綴られることになった。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
