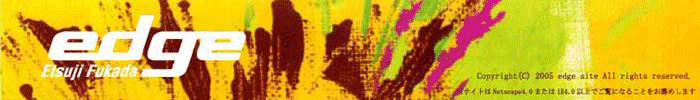同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #3
|
Part 1/ 38 St. Lowrence Terrace <3> |

7月 10 日、テニスのウインブルドン大会の決勝の翌日に僕はロンドンに到着した。
そして9月いっぱいまでは日本から仕事で来ていた妻と過ごした。
だから独り暮らしが始まったのは彼女が日本に帰った 10 月1日。
その日に僕はスーツケースとギターケースを抱え、バスに乗ってこの部屋にやってきた。
前日まで続いていた好天が嘘のような、今にも雨の振りそうな肌寒い曇り空の日曜日だった。
そのしばしの別れの朝、もうつきあって 10 年以上、結婚して5年になる彼女と、別に永遠の別れになるわけでもなく、たった1年間の、お互い納得の上での別居の始まりだというのに、あれほどの寂しさを味わうとは思わなかった。
彼女は仕事の同僚と共に空港へ行くことになっていたので、僕より一足先に、夏の間を一緒に過ごした部屋を出て行った。
オートロックのドアがガシャッと音をたて、その次に訪れた静寂の中で、これまで数珠つなぎなって編みこまれてきた日本での時間が “ ぷつん ” と音をたててちぎれたような気がした。
10 年近く仕事でもプライベートでも絶えず時間を共にしてきた仲間達の中から遂に僕だけ離れてしまったのだなという現実がひしひしと身体をしめつけた。
“ はあ ” でも “ ああ ” でもない意味不明の言葉のようなため息がひとりの部屋に響いた。
仲間達が開いてくれたお別れパーティーの時も、日本を発つ時も、 “ じゃあまた明日 ” って感じで、こんな寂しさを感じたりはしなかった。
東京での生活に取り立てて不自由はなかった。
人間関係には恵まれていたし、やり始めて5年の仕事だってそのまま続けていけば経済的には安定して行くだろうというところだった。
でもその反面、恵まれた人間関係にあぐらをかき、何もかもが中途半端で、これが僕だと胸が張れなくなっていく自分がいやだった。
時代はバブルの絶頂期。
そんなカラッポな僕が銀行から “ そろそろ家でもお買いになったらどうですか、融資しますよ ” などと言われるようになり、これってなんか違うだろうって思った。
現実っていうものをまったく理解してなかった。
理解しようともしていなかった。
とにかく何かを変えたかった。
自分の中の何かを。
それで新しい自分がひょっとしたら見つけられるかもしれないと旅に出た。
彼女と過ごした夏の間はどこかまだ観光気分で、場所が変わっただけで東京での生活の延長だったのだろう。
彼女の気配が消えた部屋で初めて、このロンドンでひとりで生活するのだという緊張感が生まれた。
その数日前、賃貸契約をした日、大家のおばあちゃんが、僕が来る日までにはきれいに掃除をすませておくと言い切ったのを信じた僕がバカだった。
油で汚れた電気コンロとオーブン。
うす汚れた流し台と冷蔵庫。
しみだらけのオレンジ色のカーテン。
前に住んでいた奴が汚したまま何ひとつ掃除された形跡のない部屋は、沈んだ心をよけいに落ち込ませ、荷物を開く元気などどこにもなく、コートを脱ぐのも忘れてベッドに座り込んだ。
部屋の中にあるものがすべてくすんでいるので、ここに来る前、バス停の前の露店で買った水仙の花の色だけがあまりにあざやかだった。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|