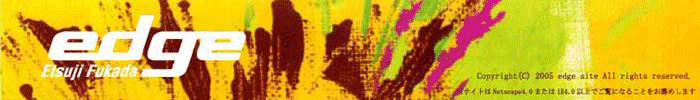
同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #15 |
Part 10/
Playing lawn tennis at the Queen's Park |
目覚まし時計のけたたましいベルで夢の世界から引き戻された。 まだ寝足りない頭はなかなかしゃっきとせず、雨漏りで出来た天井の染みが催眠術にかかったようにボケたりにじんだり。 昨夜、隣の家の、壁ひとつ隔てただけの隣の部屋でパーティーがあって、 壁が震えんばかりのダンス・ビートと嬌声で明け方近くまで寝付かれなかった。 事前にパーティーをする旨の佗び状が玄関にはさんであったので、なんと礼儀正しい隣人だろうと思ったのも束の間、 いやはややってくれるものです。年に一度の誕生日パーティーだったみたいで、それだから我慢も出来たような、 ものすごい騒ぎだった。 目覚まし時計のベルを止めて、またしばらくウトウトしていると、 今度は枕もとの電話が鳴った。かけてきたのはレイコさんだった。 「風が強いから、テニスはどうするってデイブが言ってるんだけど。」 「ちょっと待って、まだベッドの中なんだ。」 僕はベットから抜け出しカーテンを開いた。2月に入って最初の日曜の朝は、 時折強い風が吹き、窓のすぐ向こう側にある裸の街路樹がガサガサと音をたてている。今日はレイコさんの旦那、 デイブとテニスをすることになっていた。 「雨は降っていないみたいだし、これくらいの風なら僕はやりたいな。デイブはどうだって?」 電話の向こうでレイコさんが英語でデイブに話す声が聞こえる。彼らもまだベッドの中にいるみたいだ。 「デイブもやりたいって。」 「じゃあ、約束通り9時半にクィーンズ・パークに行きます。」 この部屋に電話が入ったのは2週間前のことだ。電話がひとつ増えただけで生活のリズムもずいぶん速くなり、 部屋の色が変わったような気さえする。電話がまだなかった時、 この部屋のなかにいる僕の世界に突然立ち入って来るのは大家のオバアチャン、フィリスさんくらいのものだった。 もうひとつの窓のカーテンも開け、ラジオをつけ、顔を洗い、電気ポットにスイッチを入れ、ハロッズで買ったパンを切る。 最近僕は世界的に有名な英国王室御用達のデパート、ハロッズの食料品売り場にあるこの“CHOLLALOAF”というパンに凝っている。 別にハロッズで売っているからどうこうではなく、本当にうまいのだ。しかもギッシリ身のつまった細長い1本が 1ポンド15ペンス(約300円)は決して高くない。これ1本あれば朝食4日分は十分にまかなえる。 観光客にとっても重要なショッピング・スポットである高級デパートに、このパンを買うためだけに出かける僕は馬鹿なのであろうか。 なにしろハロッズのあるナイツブリッジまでの往復の交通費の方がパンより高いのだから。 この部屋には不釣り合いな高級デパートのパンも、トースターがないために電気コンロの上の魚焼き網でトーストされて、 香取線香のような渦巻き模様にムラ焼けしてしまえば、ハロッズ・コーラ・ローフのセント・ローレンス・テラス風に仕上がる。 トーストと紅茶だけの朝食を大急ぎで流し込み、トレーニング・ウエアーに皮ジャンをはおり、 テニス・ラケットとバッグをたすきがけにしてドタドタと階段を降りる。 ちょうどゴミでも出しに行ったのだろう大家のフィリスさんが部屋に戻ろうとしていた。 「お早うございます、フィリスさん」 まだナイト.ガウンを着たままの彼女はオハヨウと照れながらドアのすきまから顔だけ出して言った。 あんなオバアチャンになってもまだまだ女の恥じらいを忘れてはいないようだ。 玄関のドアを閉めた時、ラドブローク・グローブをバスが走って行くのが見えた。大急ぎで駆けだしては見たものの、 僕がラドブローク・グローブに出たときには、バスは数十メートル先の停留所から発車したところだった。 「OH MY GOD!」 交差点の角に立っているイエスさんの像に愚痴のひとつも言ってみたくなる。 日曜日のロンドンはバスの本数がガックリ減ってしまい、1本逃すと30分待たされることも珍しくはなかった。 その1本だって、何時何分に来ますと言うタイム・テーブルに添ってくるわけでもない。たとえあったとしても それに忠実に運行されているとはとても思えない。同じ行き先のバスが2台連なってやってくることも珍しくない。 あてにならないバスを待っていたら約束の時間に遅れてしまうので、僕は半ばヤケクソで走りだした。 ホントだったら今ごろは僕はオーナー・ドライバーだった。僕の所有物になるはずだったベエさんの車ミニは、 僕の手に渡る前日にバイクがつっこんでオシャカになってしまった。すっかり頭の中で車のある生活を描いていただけに、 こうやってバスを追いかけたりしてると、その事故が恨めしい。 初めて過ごす冬だから、どんなのが一般的なロンドンの2月の気候なのかわからないのだけれど、 とても北海道なんかよりずっと北にある国とは思えない穏やかな寒さが続いていた。正面から吹いてくる風も身を切るような 冷たさではなかった。 途中でバスが来たら乗ろう思って走っていたのに、結局バスは姿を見せず、ちょうど身体がポッポしてきた頃に クィーンズ・パークに着いた。クィーンズ・パークはロンドンの北西の住宅街の真ん中にあるこじんまりとした公園で、広い芝生の プレイ・フィールドとピッチ・ゴルフ場、そして6面のテニス・コートを持っている。しっかりと根付いた大きな老木が、 この公園の深い歴史を物語る。 デイブがテニス・コートの脇のベンチに腰掛けて新聞を読んでいるのが公園の入り口から見えた。 まだこの肌寒い季節の、それも午前中にテニスなんかをやる人は相当な酔狂者だ。 ここで週末に彼とテニスを始めて3週目になるが、他のコートを陣取る顔ぶれは毎週同じである。 テニス・コートの脇にはスナック・バーがあるが、まだ鍵がかかったままだ。公園を見渡しても、 犬を散歩させている数人とテニス・コートの数人だけがいるだけで、これじゃ商売にはならない。この時期の店開きは週末だけ、 それもお昼過ぎからのようだ。スナック・バーの横の花壇では、植えられた数種類のハーブが花をつけ、 ここだけは早くも春の到来をつげている。 「ハーイ、デイブ、調子はどう?」 「うん、悪くはないよ」 グレーの巻き髪を短くカットし、丸いメガネをかけたデイブと、お決まりの挨拶を交わした。 彼は映画や舞台の脚本家を目指し、現在は企業で教育ビデオの製作をしている33歳である。 分厚い日曜版の新聞を無造作にたたんだ彼と僕は最近観た映画の話をしながら軽いストレッチを始めた。 昨夜、僕は日本人の知り合いに誘われて、デビッド・ロイド・クラブという会員制のテニス・クラブでテニスをした。 ロンドンの郊外に3箇所、各クラブに15面の屋内コートを持ち、トレーニング・ジムやスカッシュのコート、屋内プールも完備した、 どちらかといえばアメリカン・スタイルのスポーツ・クラブだ。格式ばったイギリスのクラブとは違い、 ここは入会金さえ払えば誰でも入会できるから、おのずと日本人を始めとした外国人が多い。 風もなく快適にエアー・コンディションされ、コート・サーフェースはカーペット。緑色のじゅうたんである。 コケても痛くないし、ウエアーも汚れない。そこに比べたら、このクィーンズ・パークでのテニスは苛酷な自然との戦いである。 イギリス特有の吹き荒れる風、出たり入ったりが忙しい太陽の光、突然襲いかかる雨、そして予期せぬイレギュラー・バウンド。 ここまでの状況は話に聞く憧れの芝生のコートでのテニスに酷似している。 大きな違いはウインブルドンのボリス・ベッカーのようにジャンピング・ボレーをしようものなら大ケガをすることである。 コートのサーフェイスがアスファルト。そう、道路と同じアスファルトである。グリーンにペイントでもしてあればそれっぽくもなるが、 そんな気の利いた処置は一切ほどこされてはいない。スーパー・マーケットの駐車場に線を引いてネットを立てて テニスをやっているようなものである。このサーフェースは別名ダイコンオロシと呼ばれ(当然イギリス人が名付けたものではない)、 ボールはすぐに毛羽立ち、シューズの裏はたちまちボウズになる。これは苛酷な不自然との戦いというべきか。 それで1時間1ポンド80>ペンス(約500>円)のコート・フィーが手頃な値段かどうかはわからないが、 まあ高くはないだろう。市内のパブリック・コートはどこもこんなもので、ここはちゃんとしている方だと思う。 デビッド・ロイド・クラブでのいたれりつくせりのテニスも悪くないが、たとえそれが見た目は安っぽくても、 この街に根付いている人達とこの街で培われた環境の中でするテニスの方が今の僕には贅沢に思える。 「じゃあ、軽くラリーでもやろうか。」 てなこと言っておきながら、身体を暖めるつもりで始めたラリーが、軽く打とうとすればすれほど球道が定まらず、 気まぐれな風も手伝って思いっきりヘビーなラリーになってしまい、お互い目の色が変わる。 それでもサウスポーのデイブはジョン・マッケンローを意識した独特のフォームで右へ左へとよく動く。 子供の頃からフットボールをやっていたというだけあって足が早い。テニスを始めて数年というラケットさばきはまだぎこちなくても、 もう決まったかと思うような難しいボールが戻って来たりする。 額に汗がにじみ、息も十分荒くなったところで一休みし、いよいよゲームに入る事にする。 ここでシュパッとニューボールの缶のふたを開ける。このシュパッという缶の中につまった空気が抜ける音は、 ノドがカラカラに乾いた夏の夕暮れに開ける缶ビールのシュパッと同類の爽快感である。いくらアスファルトのコートだとはいえ、 ゲームにはニューボールを使うくらいのこだわりは捨てたくないものだ。 突然巻き起こる強い風でサーブが思うように打てない。弱いボールは大きく変化をしながらネットを越えてくる。 僕は次第に集中力を失なって自滅を繰り返し、結局ゲーム・カウント6-6、両者スタミナ切れで引き分けという結果に終わった。 僕が持ってきたミネラル・ウォーター、ビッテル1.5リットル瓶を2人で回し飲みしながらコートを出る。 芝生が青々としている。日本の冬、どこの公園でも芝生は黄色く元気のないものだから、 この風景は奇妙にさえ思える。 「どうしてイギリスの芝生は冬だというのにこんな元気なんだ?」 「えっ?そりゃあ適度に雨が降って、適度に日が照る冬の方が芝生にはイイに決まってるじゃないか。 雨が少なかった去年の夏なんて、どこの公園も芝生も死にそうに擦り切れてかわいそうだったよ。」 そんなの当たり前じゃないかという顔でデイブは言った。芝の中に足を踏み入れるとじんわりと水が浮いてくる。 そんな状態だから人もあまり足を踏み入れない。夏場は人々の憩いのために人の重みに絶えなければいけない芝にとって冬は力を取り戻す絶好な気候のようだ。 デイブがふっと立ち止り、風で落ちたのだろうネコヤナギの枝を拾った。 50センチくらいの枝には毛玉のような小さな芽がいっぱいついていた。 芝生の間から、クロッカスの芽がツクシのように頭を出している。公園から出て住宅街を通ってデイブ宅に向かう途中の家の庭先に植えられた、 というより勝手に生えた木々の花が春の気配を匂わせている。暖冬とはいえ、これほど早く草花が色付くとは予想外だった。もっと、 暗くて長い冬が続くものだとばかり思っていた。いずれにせよ確実に季節が移ろうとしている。どうせ住むなら最低でも1年と思ったのは、 この季節の移り変わりを肌で感じてみたかったからだ。 デイブの家があるストリートには、2つの建物がくっついて建てられたセミ・デタッチド・ハウスが並んでいる。 このセミ・デタッチド・ハウスや長屋のようにつながって建っているテラスド・ハウス等、昔ながらの住宅は、 殊にロンドン市内ではその建物の内部だけが改造され、部屋ごとに分けて賃貸されたり、分譲されたりしていることが多い。 彼とレイコさんの部屋はグラウンド・フロアーから数えて3階建ての2階部分、ファースト・フロアーが2つに仕切られた南側で、 バスもトイレも完備された、日本風にいえば1LDKの分譲中古マンションである。 わざわざグラウンド・フロアーから数えて…”と言ったのは、 こういう住宅には必ずベースメント・フロアーという半地下の階があるからである。 この建物がひとつの家庭の物だった頃、ベースメント・フロアーは物置だったり使用人の住居だったりしたらしいが、 現在では立派な居住空間のひとつだ。階段を数段昇るとグラウンド・フロアー以上に住む人の玄関があり、 その階段の脇の階段を数段降りればベースメント・フロアーへの入り口がある。 玄関に立つと、レイコさんが弾いているピアノの音が聞こえた。階段を昇り、 デイブがドアの前で鍵をがちゃがちゃやっていると、ピアノの音がピタリと止り、ドアが開くとレイコさんが立っていた。 「どうだった、テニスは。」 「もう風が強くてめちゃくちゃだよ。でもデイブは悪くなかった。今日のゲームは引き分け。」 「ええっ、ウソッ!デイブ、なんかインチキしたんでしょう。」 先に部屋に入ったデイブが振り向かないままガッツ・ポーズを取っている。彼はそのままキッチンに入り、 拾ってきたネコヤナギの枝を水の入ったコップに差してテレビの上に置いた。 「さあ、ランチにしよう!」 パンとチーズ、茹でたソーセージ、それにミルク・ティーを部屋の床に広げたタオルの上に置いてランチが始まった。 和食で言えば、ゴハンにミソシル、シシャモにナットウってところか。このシンプルで気取りのないランチに加われる自分を幸せ者だと思った。 流れの速い雲には次第に切れ間が多くなり、太陽が顔を出す度に景色が春色になる。南向きの部屋からは、 この建物のベースメント・フロアーに住む人達の家の庭が、そこには大きな木が立ち、庭の向こう側には国鉄の線路が見える。 その庭は線路沿いということもあるのか、こういう形態の建物の庭にしてはかなり広い。 線路のおかげで向かい合う建物がないので余計にそう感じるのかも知れない。それで空も広い。 この線路はロンドンの南西にある巨大な公園、リッチモンド・パークに続いている。 もともと王室の狩り場だった公園に今も多く生息している鹿が、貨物列車とかに紛れてこのあたりまでやってきたこともあったという。 線路沿いに並ぶ建物と線路の間の庭はどれも、鹿が歩いていてもおかしくないような野原の風情がある。 この部屋の下の階は、ひと部屋分だけ庭側にせりだしていて、 その平たい屋根の部分がデイブ達の仮設ルーフ・バルコニーとなっている。そこでフトンを干したり日光浴をしたりするわけだ。 デイブがそこにパン屑をばらまくと、庭の茂みに潜んでいた小鳥達が飛んできて、 自分の頭より大きいようなパンの塊をくわえてまた茂みへと帰って行く。 「ほら、見てごらんよ。また片足のスターリングが来ている。」 パンを取り合いしている小鳥達のなかに片足のムクドリがいた。 自分がパンを食べる時には必ず小鳥達に分け前を与えるデイブは、近所の鳥のこともよく知っている。 折れたネコヤナギを拾ってきたり、小鳥にパン屑を与えたり、こういうつまらないことに気の配れる人に悪い人はいない。 初めて彼とテニスをした日、まさか彼と毎週テニスをするとは思わなかった。 僕のつたない英語のせいで、僕と彼の間では黙り込んだ時間が多かった。 最初は、こんな英語のヘタな奴とつきあうのに疲れているのだろうと勝手に思っていた。 けれど、ただ時間を繕うだけの意味のない言葉を投げかけたりしないだけ、ということにお互いが気づくのにさして時間はかからなかった。 なにげない態度は言葉以上にその人の本質を浮かび上がらせる。 「これから友達とパブで飲むことになってるんだけど一緒に行くかい?」 デイブの誘いは願ってもない話だったけれど、僕は着替えを持ってなかった。 僕が着ているのは薄紫色のアディダスのウォーム・アップ・スーツだった。 「こんな格好で行っても構わないかなあ」 「なかなかファンキーでいいんじゃないの。」 そういやあ、黒人の子供は普段からこんなの着て歩いているわ。 テニスボーイからファンキーガイに気持ちを入れ替えた僕は、 まだ寒いのに皮ジャンの下にTシャツ一枚、ブルー・ジーンズにウェスタン・ブーツでロンドン・ガイを気取るデイブと、 それにあきれているレイコさんと一緒にフラットを出て、うっすらと陽の光がもれる駅への道を歩いた。時折立ち止り、 誰かの家の庭先に花をつけた草木に春の訪れをかみしめたりしながら。時間が止ってしまった街。20年前もこんな風景だったに違いない。 10年後もきっと、こんな風景だろう。僕達は20分に1本しかない電車を待って、ホームのベンチに腰掛けた。 あいかわらずのんびりした時間が流れている。 今、僕の隣には友達と呼べる夫婦が座っている。友達と呼ぶことのできる人と出会える確率は実に少ない。 それは日本にいたとしてもだ。これまでにどれだけの人に出会ったのだろう。そして、その中で今でも友達と呼べる人は何人いるのだろう。 会社を辞める時、デスクの引き出しにゴッソリ貯まった名刺を整理したのだが、 これからも付き合いがありそうだなあと残した名刺の数はたったの数十枚、その中で友達と呼べる人、と思うと頭をひねってしまう。 「デイブ、来週もテニス出来るかい?」 なんの前触れもなく、独り言のようにそう言うと、空をボォッと見上げていたデイブはキョトンとした顔で僕を見た。 「もちろんさ、天気さえ良ければね。」 きっと次の週末、ちょっとくらいの雨なら僕達はボールをおっかけているだろう。 もちろんクィーンズ・パークのテニス・コートで。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
