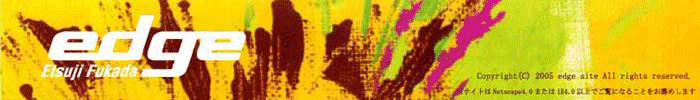同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #11 |
edge/Part 6/オペラ座の酔人 / The Freak Of The Royal Opera House |

「 セットが斬新で、演出も斬新で、プレヴューでブーイングが来て、評判があまりよくないオペラがあるから行かない?」
ロンドン市内の大学で舞台美術の勉強をしているナナちゃんと、日本人の若い俳優が主演しているアメリカ映画 “ ミステリー・トレイン ” をロンドンのレスター・スクエアーで見た後にイタリアン・レストランで食事をしていてら、彼女がそんなおかしな切り出し方で僕をオペラに誘った。
僕はオペラに関しては無知に等しかったが、なかなか興味をそそられる話だった。
由緒あるロイヤル・オペラ・ハウスでいかなる作品がブーイングを巻き起こしたか一見の価値がある。
出し物はモーツァルトのイドメネオ。
予習のために本で調べてみれば、 1781 年に初演されたこのオペラは、その時の歌手が良くなかったのと、モーツァルトの非凡さがゆえ当時の聴衆には耳新しすぎたのもあって初演後 100 年以上も忘れられていた作品であったという。
僕達は当日券を買うためにコヴェント・ガーデンにあるロイヤル・オペラ・ハウスのボックス・オフィス前に朝9時に待ち合わせた。
コヴェント・ガーデンは、以前は中央卸売り市場としてロンドン市民の胃袋を支えた場所だったが、市場の移転にともないショッピング・エリアに生まれ変わった地域だ。周辺には劇場も多く、市場の建物をそのまま使ったアーケードの一角ではいつも誰かがストリート・パフォーマンスを行なっていて、そこらじゅうからアミューズメントの匂いがする華やいだ場所だ。
その広場の一角にドッカーンとロイヤル・オペラ・ハウスがそびえ立っている。
通称 “ 天井桟敷 ” と呼ばれる3階席の最後列2列が公演の当日の朝 10 時から売り出される。
12 月の雨がそぼ降る中で1時間待った僕達は、 12 ポンド(約 3000 円)の天井桟敷のチケットを手に入れた。
立ち見席を除けば一番安い席で、すでに売り切れの人気のある出し物の時などは、このチケットを手に入れるために前夜から人の列ができるという。
金はなけれど時間はあるという学生や僕のような人種などに人気のチケットで、発売開始の 10 時に来たのでは手に入れられない事も多いという。
この日も、ボックス・オフィスが開く 10 時には、前から3、4人目の位置にいた僕達の後ろに長い列ができていた。
開演 30 分前ともなれば正面玄関のロビーには華やかな社交の花が開くロイヤル・オペラ・ハウス。
ドレス・アップした LADYS AND GENTLEMEN がワインなど片手に友人達との再会を喜んだり … 。
しかし僕達の “ 天井桟敷 ” へは、この華やかな正面玄関を通って行くことができない。
劇場サイドにある、 ” 天井桟敷 ” 専用の入り口から入り、赤と黒のストライプの壁に囲まれた薄暗い階段をせっせと昇って行くのだ。
当日券を手にいれた後、お茶を飲んだ僕達はいったん別れて開演 15 分前に、その “ 天井桟敷 ” 専用の入り口前で待ち合わせることにした。
部屋に戻った僕は、いつものようにとなりのアイルランド人の爺さんの様子をうかがいつつ歌の練習をして、簡単な食事を取って、服を着替えた。
部屋を出ようとして忘れ物がないかチェックしていたら、なんと今日のチケットが見当たらない。
朝着ていた服のポケット、カバン、サイフとひっくり返してみるがどこにもない。
そんなことしていたら時間はどんどん過ぎてしまって、オペラやクラシック音楽の場合、時間に遅れると次のインターバルまで場内に入れてもらえない。
ナナちゃんまで巻きぞえにするわけには行かない。
半ばオペラはあきらめて大急ぎでコヴェント・ガーデンに向かった。
「ゴメン遅れて。俺チケットなくしちゃったみたい … 。」
「えっ?何言っての?チケットは2枚とも私が持ってるわよ。」
「??!! … 。」
開演時間が迫っていたので、僕達は大笑いしながら赤と黒のストライプに囲まれた階段をせっせと昇った。
“ 天井桟敷 ” の席からのステージの眺めは、5階建てのビルのてっぺんから見下ろすようなものではあったが、広い視野でオペラを楽しめるという苦しまぎれの考え方もできなくはなかった。
月に何本も見たいというオペラ・フリークが集っているのもこのあたりらしく、最初に売り切れるのはこの3階席らしい。いってみれば “ 通 ” 、 “ 酔人 ” の集う場所なのだ。
場内の灯が静かにおとされ、場内が静まる。
まだ話を止めない人をたしなめるかのように “ ウホォ・ウホォ ” という咳ばらいが聞こえる。
指揮者がさっそうと現われると拍手が起こり、 “ 期待 ” の公演の幕が開く。
なにしろプレヴューでブーイングが起こったというプロダクションだ。
客席で何か起こるのではないかというのがナナちゃんの見解であった。
物語の舞台は、紀元前 1200 年頃、トロイ戦争直後のクレタ島、そこの王様がイドメネオさん。
海難事故で生き残ったイドメネオさんは海の神様との誓いに従って、助かった後に一番最初に出会った人をいけにえにしなければいけなかった。
そしたら、なんと自分の息子さんのイダマンテに会ってしまう。
ああ、なんと不幸な身の上か。
そして物語は第2幕へと進む。
予想通りに事件は第2幕の途中で起こった。
イダマンテさんに心を焦がす、戦争で両親をなくした悲しい運命を背負うトロイア王の娘イリアが、その切ない思いを可憐に唄う場面で、彼女は通りかかった子供が持っていたペンキのバケツを取り上げ、地面にピンクの文字で大きなハートを書き、その中にイダマンテのイニシャルと自分のイニシャルを書いた。
1席の値段が 80 ポンド近くするオーケストラ前のストール席の方々には、ここで何が書かれていたかは見えなかったであろう。
まあ、見えなくたって体勢には影響はないはずだ。
彼らの多くにとって大切なのはインターバルでの “ 社交 ” なのだから。
しかし、我々5階建てのビルの上から見下ろしているような天井桟敷の人々には、ハートやイニシャルはしっかり確認できる。
斬新といえば斬新な解釈とも言えるが、素人の僕さえも、なんだか話にそぐわない安っぽい演出だなあと首をひねった。
そしてさらにハートの真ん中に矢が書かれた時だった。
まだ唄は途中だというのに、僕らの斜め前あたりで誰かが大声で叫んだ。
「何だそれは、馬鹿にしてるのか、やめろ、やめろ!」
その怒鳴り声をあげた男には、そのハートを書いたりする演出がどうにも気にいらないらしく、叫んだあとも、なにやらひとりでブツブツうなっている。
静かな曲なので、その男の声が会場中に響き、まわりの人々が “ シッー ”“ うるさい、黙れ ” と応戦し、まもなく騒ぎは収まった。
一瞬、身体がビクっと震えたステージ上のソプラノ歌手も、そのまま取り乱すことなく、その場を唄い切ったが、天井桟敷あたりにはなんともいえない気まずいムードが流れたまま第2幕が閉じインターバルとなった。
場内に灯が入り、バーやトイレへとみんな席を立ち上がりだした時、叫び声をあげた男のまわりにいた人達が口々に、その男に非難の声を浴びせた。
叫んだ男は、 30 代のメガネをかけたヤング・エグゼクティブ風の白人で、非難されたことに顔を真っ赤にしてやりかえす。
「君たちはあんな演出を黙って見ているというのか。僕にはあんなのは許せない!」
「あんたが嫌でも、他の人は嫌じゃないかもしれないじゃないか。そんなに嫌なら目をつぶっていればいいんだよ。」
非難を浴びせかけた人々も、やってらんねえとばかりにみんな外へ出て行った。
その騒ぎが収まったと思ったら、今度はその ” 叫ぶ男 ” の連れの白人の女性と ” 叫ぶ男 ” の間で内輪もめが始まった。
「イヤならイヤでそれでいいけど、大声張り上げることはないじゃないの。そんなに気にいらないんだった黙って席を立てばいいのよ。」
「君までがそんなことをいうのか。わからないのか、このイドメネオという作品はだなあ … 」
「もういいわよ、我慢できない … 。私、帰る … 。」
すくっと女性は立ち上がり、うつむいたまま足早に出口に向かった。
ア然とした ” 叫ぶ男 ” は大慌てで荷物をかき集めて女性の後を追う。
「おい、ちょっと待てよ。なんで俺達が帰らなきゃいけないんだ。おーい … 」
僕が初めて目のあたりにしたオペラ・ハウスでの騒ぎも、本場イタリアや、その他フランスなどのラテン系民族の人たちが多い国ではさして珍しくもないらしい。
調子の悪い歌手などは歌の途中だろうがなんだろうが徹底的にヤジり倒されるという。
この作品の歌詞はイタリア語だ。
だからロンドンのオペラ・ハウスの舞台上の電光掲示板には英語の字幕が出る。
結局、ここに来ている人の多くは歌詞の大意しかわからずに聞いているのだ。
イギリス人がイタリア・オペラやドイツ・オペラを聞くのは、僕達日本人がブルース・スプリングスティーンが歌う “BORN IN THE USA” にイエッーと拳を振り上げるのに近いものがあるように思う。
たとえがあまりに極端か?
いずれにせよ自分達が普段使っている言葉を聞いて反応しているイタリア人とイギリス人と反応が違うのは当然である。
先日、やはりナナちゃんと見たアメリカ映画 ” ミステリー・トレイン ” で、日本人の若いカップルが日本語で話すのに英語の字幕が出ていたが、日本語を聞いて見ている僕達と字幕を読んで見ているイギリス人と、笑う場所やウケる場所にあきらかにズレがあることを発見した。
英語に訳された字幕が伝える意味は驚くほど平たい。
実際に言葉として発せられた台詞の意味は、字幕という枠の中では伝え切れていないのだ。
言葉の壁は思いのほか厚いのである。
もちろん言葉がわからなくたって楽しむことはできるだろうし、オペラなら歌手の善し悪しはわかるだろうが、言葉の持つ微妙なニュアンスとか深い所に立ち入るには、それなりの情熱と勉強を要するはずである。
そうやって頭を使って音楽を楽しんでいるうちは本物とは言えない。
観客の反応が舞台上の人間の出来不出来に微妙に作用する。
この場内の雰囲気こそ本場ならではと言える。
“ イギリス人はなんでもブラボーだ ” とイタリア人が嘲笑するという話を聞いたことがある。
日本におけるクラシック音楽が妙にかしこまった物になってしまうように、ラテン民族の人達から見たイギリスで上演されるオペラというのはまだまだ堅くてお高くとまった物なのだろう。
話がすべて極論になってしまったが、そうなふうにあれこれ考えると、思わず大声を張り上げてしまった “ 叫ぶ男 ” は真のオペラ・ファンだったに違いない。
この作品に大きな期待を寄せていたに違いない。
怒鳴ってしまったものの、最後まで曲だけでも聞いていたかったに違いない。
結局のその2人は、第3幕が始まっても戻ってこなかった。
ぽっかりとふたつ空いた席が物悲しげだった。
物語は、イドメネオが神託にそむいて息子を逃がそうとしたのに海の神様が怒り、それを鎮めようと自らいけにえになろうとするイダマンテに、代わって自分がいけにえに!と割って入ったイリアの愛に打たれた海の神様が彼らを許し、二人は結ばれ、メデタシ、メデタシという展開で幕を落とした。
ところが公演としては、その内容と凝ったセットのわりには最後まで観客席は盛り上がらず、フィナーレが豪華になればなるほどシラケテしまい、それでもカーテン・コールでのブーイングもなく、一番盛り上がったのは天井桟敷の人々の攻防という、我々の “ 期待通り ” の幕切れとなった。
ロイヤル・オペラ・ハウスを出た僕達はコヴェント・ガーデンを抜けてソーホーに向かって歩いた。
街はそこまで来ているクリスマスへの期待が満ち溢れている。
あの3幕を前にオペラ・ハウスを出て行った、本日のスターだったお騒がせのあの “ 叫ぶ男 ” は、今ごろ何処にいるのだろう。
なにしろ満員のロイヤル・オペラ・ハウスの観客の中で、たったひとり自己主張をして注目を集めてしまった勇気ある男である。
走り去ろうとする連れの彼女をぐいと引き寄せ、わめき立てる口を強引なキスかなんかで黙らせたりして、それですんなり仲直り。
それで今頃、何処かのレストランかなんかで肩をすり寄せながらワイングラスでもかたむけていたりするのかもしれないな、なんてことを想像した。
だとしたら、僕はサっと席から立ち上がり、大いに拍手を贈りながら、こう叫ばなければいけない。
“ ブラボー! ”
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|