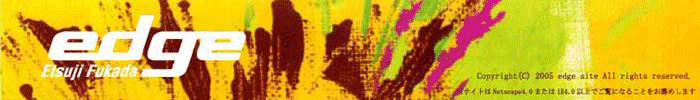
同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #12 |
Part 7/A Christmas Present From The Sky /空からのクリスマス・プレゼント |
時計の針が午前0時をまわり、12月24日になった。いよいよひと夜明ければクリスマス・イヴだ。 べつにクリスマスに特別な想いなどない。パーティーの予定もなければどこかに出かけるつもりもない。ただ、クリスマスを一番楽しみにしている国がクリスマスに向けてどう変わっていくのか見るのが楽しみだった。 1ケ月前あたりから、繁華街はクリスマスのデコレーションでライト・アップされ、大きなデパートのショウ・ウインドウはクリスマスにちなんだ幻想的なディスプレイがほどこされた。それだけなら日本だって毎年やっている。でも、当たり前のことだけれど気合いの入り方が違うし、街並みとデコレーションは見事にマッチしている。 そして、この2、3日、街のそこらじゅうで“メリー・クリスマス”という声が聞こえた。マーケットのレジのオバチャンも、レストランのウエイターも、タクシーの運転手も、別れ際には必ず笑顔で”メリー・クリスマス”だ。僕達日本人が年末に“良いお年を…”と声を掛け合うのと同じなんだろう。イギリスのクリスマスは家族単位の団らんで、離れ離れになっている家族が集まってくるという。ようするに日本のお正月だ。 さっき、大家のおばあちゃん、フィリスさんにクリスマス・プレゼントを渡した。日本から持ってきてもらった夫婦茶碗だ。だんなさんの看病で、今年はドアの飾り付けをする余裕もないとぼやいていたフィリスさんは、たぶん予期してなかっただろう僕からのプレゼントに、“THANK YOU”の後に“VERY”を4回繰り返してから“MUCH”と言う位喜んでくれた。プレゼントは25日にだんなさんと一緒に開けるのだと言っていた。この年老いた夫婦が一緒に迎えるクリスマスはあと何回あるのだろう。だからこそ、少しでもいいクリスマスになれば、とそう思う。 僕達が日本にいた時騒いでいたクリスマスは忘年会に赤い服を着せただけのものだったんだなあ、と思う。それをどうこう言うつもりもないけど、それにしても日本は平和だ。 ラジオからはイヤになるほど次から次へとクリスマス・ソングが流れてくる。“バンド・エイド2”の“Do They Know It Christmas Time”が流れてきた。この曲は5年前、エチオピア難民救済のためにイギリスのポップ・スターが集まってチャリティーのために唄った曲で、当時としてはセンセーショナルな試みとして大きな話題となったが、今流れているのは、その1989年版。現在のポップ・スターがこぞって集まり唄っている。ところがなんともインパクトに欠ける情けない出来栄えである。先日、どこかでこの曲のビデオ・クリップを見てなるほどと思った。痩せ細って涙を浮かべるアフリカの難民の子供の映像の次に、キャーキャーというファンの大歓声の中、リムジン・カーから降りてガードマンに守られてスタジオに入る若いポップ・スターの映像が重なる。いくらチャリティーが目的とはいえ、作る側の意志が安直過ぎて気持ちが悪い。偽善と言われてもしかたがない。どこの国にも、どこの世界にも素晴らしい人がいて、くだらない人がいるのだ。チャカチャカした重みのないサウンドが耳障りになりラジオを切った。 部屋が静かになると、隣の部屋でジャックがブツブツ言っているのが聞こえてきた。すでに仕事をリタイアし、独り暮らしのこのアイルランド人のジイサン、酔っ払って帰ってきた日には必ず独りでブツブツ言っている。 たとえ階段で会ったとしてもジャックは決して僕に言葉をかけようとはしない。へんくつといってしまえばそれだけの事だが、それ以上の哀愁が彼を取り巻いていた。大家のフィリスさんは“ジャックは変わってるからほっとけばいい”と言う。フィリスさんも変わってるけれども、その彼女が言うくらいにつかみ所がない。どういういきさつで彼が独り暮らししているのかは知らないが、60歳も越して、狭い部屋で独り迎えるクリスマスはさぞかし淋しいものだろう。僕には隣人として何かしてあげようにも何もしようがない、彼が心を開いてくれない限り。 テーブルの上に赤茶けた新聞が置いてある。今日の朝、いや、そうもう昨日になるのか、僕は屋根の修理の音で目が覚めた。さすがに古い家だけあってあちらこちらにガタがきていて、強い雨が降ると見事な雨漏りが始まる。2ケ月前から大家さんは直すと言っていたのに、やっと今日になって修繕に取り掛かったようだ。12月24日が日本で言えば大晦日みたいなもんで、23日は30日の仕事収めってところか。年末も押しせまったのでしょうがない、やっておきましょうかといった感じであった。そのテンポがイギリスらしいといえばイギリスらしい。 ベッドから抜け出し、トイレに行くために部屋のドアを開けると、踊り場にハシゴがかかっている。ハシゴつたいに視線を上げると天窓が開いていて、青い空が見えた。こんな所から屋根にあがるのだととは知らなかった。今度は視線を床に下げると、天窓の蓋を開けたときに屋根裏から落ちたと思われるススの塊の中に新聞が埋もれていた。古そうな新聞だなと思いながら、なんの気なしに拾い上げ日付を見ると“July 23、1945”となっている。一瞬目を疑ったが、間違いなく44年前の、まだ太平洋戦争が終結する前の新聞だった。古いとは思ったが、そこまで古いとは思わなかった。僕は考古学者が重大な発掘をしたような気になり、屋根の上で作業をしている修理屋に気づかれないように、新聞を持ってそっと部屋に戻った。こんな新聞、あきらかにゴミでしかないのだが、ひょっとしたら修理屋の連中も興味を示していたら面倒なことになる、なんて馬鹿なことを思ったほど、この新聞に興奮させられていた。 手荒に扱うとボロボロに崩れそうなので、そっと床に広げる。見開き4ページの“THE EVENING NEWS”という夕刊紙のようだ。僕が知るかぎりでは、今、こんな名前の新聞はないと思う。折り畳んであった折り目の部分が破れて、焼け焦げた紙のようにバラバラになっている。それをセロテープでつなぎあわせながら記事に目を落とす。“ジャップ、ビルマ戦線でで500人死亡。”という記事が目に入る。だが決して大きな記事ではなく、紙面からはあまり戦争の匂いがしない。今も存在している劇場の出し物の案内やデパートの夏のセールの広告が出ていたりして、たいした緊迫感もない。その頃の東京といえば、空襲につぐ空襲で焼け野原と化し、“欲しがりません、勝つまでは”といわなければならないほどの物不足だったというのに、ロンドンは余裕綽々である。太平洋戦争なんて遠い海の向こうの話だったのか、すでにヨーロッパ戦線は形がついていたからなのか、いずれにせよこんなやつらが肩を組んだ連合軍を敵に回していたのだから、とうてい勝ち目がなかったことがよくわかる。空襲で命を落としたという母方の祖父を始め、その戦争で命を落とした人達の事を思うと、戦争のはかなさを感じずにはいられなかった。この頃、日本でクリスマスを祝う人などほとんどいなかっただろうなあ。 ドライ・シェリーを飲みながら、彼女に手紙を書き始めた。僕の部屋にはまだ電話はない。どうしてもその新聞の事を”今日中に”彼女に伝えたかった。いつもどおり窓の外には、滑走路の誘導灯のように一直線に伸びる、乳白色の街灯の光が連なっていた。滑走路みたいな通りをラドブローク・グローブというバス通りが50メートルくらい先で横切る。独特な形をしたタクシー、夜中も走る赤い2階建てのバス。そこを走る車は、通りと通りが交差する建物と建物の間のほんの10メートルくらいの間だけ姿を現わし、消えて行く。言葉につまり、筆が止ってしまった僕は、しばらく車が見え隠れするその小さな交差点を見つめていた。 どこからかキキキキッーというタイヤのきしむ音が街の静けさを突き破って響き渡った。すると、次の瞬間、僕の見つめていた交差点の中に、完全にひっくり返った乗用車が飛び込んで来て、天井を道路に擦りつけながらギギギギッーというすごい音とともに止った。 ア然とした僕はペンを落として立ち上がった。 車が止ると同時に、ゴキブリ・ホイホイの中から一斉にゴキブリが這い出てくるように、サイドの4つの窓から4人の人間が大慌てで這い出てきた。どうやらスピードの出し過ぎかなんかで自らひっくり返ってしまったらしい。ここから見るかぎり大きな怪我をしている人はいないようだ。 まず、やじうまが現われ、パトカーがやってきて、救急車が駆け付ける。警察の取調べが始まり、車に乗っていた物同士が大声で罵り合う。救急車もやじうまもパトカーもいなくなり、ひっくり返った車がクレーン車で運ばれて行き、通りに静けさが戻ったのは午前4時近くだった。 それにしても壊れたのが車だけで本当に良かった思う。家族が一同に会するせっかくのクリスマスがすぐそこなのだから。ちょうど、その交差点の角は教会で、その脇には十字架にはり付けられたイエス様が立っていた。ほんの偶然なんだけど。 夜を見つめていた。クリスマスを待ちきれない街の夜をひとりで。 僕の会いたい人はそばにいない。明日会おうと思ってもそうはいかない。なんだかむしょうに淋しさがこみ上げてきた。 僕はギターを手に取り、作曲ノートを開いて、そしてつぶやくような押し殺した声で書き散らかした言葉を拾い上げてみた。 クリスマス・ライトが街に点り出した頃から書き出していた曲の、空白だった部分にどんどん言葉が埋まっていった。
“凍てついた12月の朝 独りの僕は 夜明け前の空の中に世界中の悲しみを見たような気がした…”
メロディと言葉が交わり音に生命が芽生える。出来上がってしまえば、もうずいぶん前からそこにあったように感じる曲も、作り上げる過程の心の動きをかえりみれば、とても神秘的だ。何が僕にこの言葉を選ばせたのか、何がこのメロディーを浮かび上がらせたのか。なぜ僕がこの世に生まれてきたのか、という命題に近い不思議さだ。 ギターを置いて僕のタメ息が消えると、再び夜明け前の静けさがこの部屋を支配する。 机の上の赤茶けた新聞をボンヤリとながめながら、ちょうどこの頃、10代の青春時代を送っていたオヤジとオフクロの事を想った。大学生だったオヤジはお国のために死のうと、神風特攻隊に志願したという。中学生だったオフクロは、空襲で爆撃を受けて行方不明になっていた父を探し、道端にころがっている死体をひとつづつ見てまわったという。偶然とはいえ今年は、あの戦争の傷跡のひとつであるベルリンの壁が崩れ、第2次世界大戦後のヨーロッパの地図に変化が起こり始めた年であった。 44年前の新聞。こんな物、手にいれようと思っていれられるものではない。 思いもかけないクリスマス・プレゼントが天から降ってきた。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
