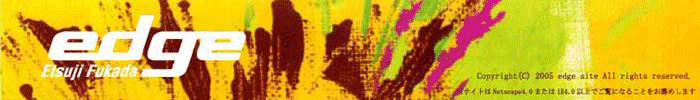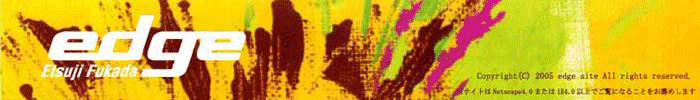同じ空なのに違う空の下 edge in London '89-'90 #16 |
Part 11/ MINI ミニ |

つぼみを膨らませた花に誘われるように休日を公園で楽しむ人達の数も増え、春らしい華やかさがロンドンの街を包み始めた。
僕とデイブの週末のテニスは、お互い用事でもない限り多少の悪天候ももろともせず続いていた。その合間に、最近見たばかりのコンサートや映画、舞台のこ ととかを話したりするのだが、会う回数が増えるにしたがって僕は遠慮なしの“英手話”とも“ジェスチャー・イングリッシュ”とも言えるひどい英語をデイブ に浴びせかけた。さすが大学を卒業してしばらく心に悩みをもつ人のためのカウンセリングを仕事にしていただけのことはあるデイブは、その忍耐力と洞察力と 想像力で、僕の言わんとすることを理解してくれた。
そしてレイコさんとは、彼女に誘われてクラシック音楽のコンサートに出かけるようになった。こちらに来て半年、かなりの数を見てきたポップスのコンサー ト、芝居、ミュージカルとかに比べ、興味があってもなかなか情報のソースがなく、何を見ればいいのかわからなかったのがクラシック音楽の世界。だから、ク ラシックのピアニストとして活動する彼女の情報とお誘いは願ったりかなったりだった。不思議に心の通じ合うこの夫婦の存在の出現で、今まで手をつけたくて も手をつけられなかった新しい世界に触れる機会が増え、僕にとっての新しいロンドンの地図が広がっていった。
英語学校の方も、あの台風の日のクリフとクリスティーンさんによる英仏決戦の数日後、なにもなかったかのようにクリスティーンさんが復帰し、クリフもわ ずかながらも姿勢を正したようにも見えるが相変わらずで、でもそれ以降これといったトラブルもなく安定した毎日が流れていた。
そんな中で僕は新たな刺激に向けて動き出そうとしていた。それは一度は手に入れそこなった車をGETすることだった。狙いは当然のごとくオースチン・ミ ニ。この世に出現して何十年と基本的なスタイルを変えず、ずっとイギリス人にとってのベスト・セラーであり続ける小型車である。ロンドンには駐車場という スペースがほとんどない。だから路上駐車が当り前のこの街では、その車体の小ささが大きな人気の秘密で、中古車の中でも他の車種に比べてあまり値段が落ち ないらしい。僕のようなあと数ヵ月でロンドンを去る人間には、帰るときに売りやすく損しないですむので持ってこいの車なのである。もちろん売りやすくする ためにもコンディションの良い車を選ばなければいけない。新車だったらまったく問題ないんだけど、そんなのは高くてオハナシにならない。かといってあまり 安すぎるのはなにかしら性能に問題がある証拠で、かえって売るときのリスクが大きく損をする可能性は高くなる。僕の手に渡る前日に事故で廃車になったベエ さんのミニは900ポンドで譲り受けることになっていて、雑誌や専門店で調べてみても、だいたいそのあたりが僕の財布の具合からしても適当な価格だった。 専門店の業者を通じて買うよりも個人売買のほうが値段的には安いのだが、相手が知り合いとかでない限り信用という部分でのリスクは大きい。デイブからもそ の車に過去事故とかの事実“history”があるかどうかをしっかり調べたほうがいいとアドバイスを受けたが、そんな交渉をする時に売り手の気持ちの裏 側を読もうにも僕の語学力はあまりに心もとない。デイブに助けてもらうことも考えたりもしたが、ここで人の力を借りて安易に車を手にいれても意味がない。 それを手にいれるためのプロセスを経験することに意味があり、そのためにあえて言葉が容易には通じない場所にやってきたのではないか。このロンドンで僕に いろんなことを教えてくれた人達、マリコさん、ベエさん、そしてデイブとレイコさん、みんな情報は与えてくれても実際の行動に対しては助けてくれようとは しない。それが本当の優しさなのだ。そんなことを考えていた矢先、学校からの帰り道のノッテング・ヒル近くの路上でFOR SALEの紙が貼られたベージュのボディに天井がこげ茶のオースチン・ミニを見つけた。紙に書かれた値段は1350ポンド。ちょっと見にはとても奇麗で、 年式もそんなには古くなさそうだ。これが1000ポンドくらいまで値切れたら“買い”かもしれないと、値段の下に書かれた電話番号と売り手の名前をノート にメモって急いで家に戻った。
さあ、ここからが大変である。相手の顔が見えない電話での会話は、それがたとえデイブだとしてもだ、それなりの心構えが必要だった。しかも今回は僕に とっては高額なお金が動く値段交渉もある。これから起こりうるであろう会話のシュミレーションをしておかなければいけない。ノートを開き、まず、自分が言 うべきことを書き出し、それに対して相手が言ってくるだろうことに対してのいくつかの答えのパターンを書き出す。この台本が出来あがったら、今度はリハー サルである。ブツブツひとり芝居が始まる。となりの部屋にひとりで住んでいるアイルランド人のジイサン、ジャックがよくブツブツ独り言を言っているのが壁 越しに聞こえてくるが、その怪しさは似たりよったりである。
何度かリハーサルをくりかえし、気分が高揚してきたところで受話器を取る。途中まで番号を押したあたりで、ちょっと待てよ、もしこう言ってきたらなんて 言えばいいんだと不安に襲われ、受話器を戻して、またあらたな書き込みを加えてリハーサルをする。このようなもどかしい作業を何度かくりかえして、ああっ もうどうにでもなれっと開き直ってやっと電話はつながる。こんな僕にもあきらかに中近東系の訛りとわかる言葉の男が出た。それが売り手だった。
「あのミニ、900ポンドだったら買いたいんだけど…」と単刀直入に切り出すと、その中近東訛りの男は、冗談じゃねえとばかりに、僕にはとても聞き取れな いスピードでなにやらあのミニがどれだけ価値の高いものなのかというようなことをわあわあ言い出した。まあ、こういう展開になることは想定通りで相手の一 方的な話がとぎれたところで、でも1350 ポンドは持ってないから残念だけど買えないとあきらめるような匂いを漂わすと、相手は即座に反応し、1200ならどうだと言ってきた。これなら1000ポ ンドくらいにはなるなと、1000ポンドはどう?と返してみると、またさっきと同じように冗談じゃないとまくしたててきたが、僕がしばらくウーとかムーと か言っていると、今度はあっさり自分のほうから1100ポンドが限界だと言ってきた。いや、1000しかないんだと食い下がってみたが、じゃあ売れないな あと向こうが話を打ち切ろうとする。ムード的に敵もここがボーダー・ラインのようだった。この100ポンドの差、日本円にして約2万7千円の差は、家賃 だって週40ポンドに押さえて生活している僕には大きな問題だった。いったん断わって後日再度交渉してみるということも考えたが、その間に売れてしまう可 能性だってある。どんでん返しが続いた、アパートを探していた時の苦労がふと脳裏をよぎった。まあ売るときに同じ値段で売れればいいかと、一度実物を チェックした上でという条件つきで1100ポンドで僕は折れた。
翌日、ハノーバー・スクエアにある東京銀行で1100ポンドを下ろし、約束の時間にミニが止めてあった場所に向かった。その持ち主の中近東系の男は、ミ ニの止まっていた脇にあるパブのバーテンダーらしく、僕が車の脇に立っているとパブの中から出てきた。ハイと無愛想に会釈しただけでドアの鍵を開け、エン ジンをかけて僕に助手席に乗るよう催促した。男はそのブロックを軽く一周車を走らせながらコンディションはバッチリだみたいなことをまた早口な訛りのある 英語でああだこうだ説明した。何か問題があればもっと値切ろうと思って、事故の経歴“history”とかはないのかと聞くと、そこまでとは微妙に違う間 があって“ない”と答えた。まああったとしても正直に答えるやつもいないだろうから間抜けな聞き方をしたものだ。すぐに前と同じテンポを取り戻した男は、 これは前のオーナーが大事にしていたのを譲り受けたものだから絶対大丈夫だとあまり表情も変えずに早口でまくしたてた。“前のオーナーから譲り受けた”と いう部分が気にはなったが、とりあえずきちんと走っている。もとの場所に戻り今度は実際自分で運転をしてみても、とりあえずきちんと走っている。その男の 雰囲気も含め全体的には怪しげな空気は漂ってはいたが、疑り出したらきりがない。ベエさんのミニより年式は新しく、その分値段が高いのはしょうがないかと 自分を納得させ商談は成立した。男に現金で1100ポンド手渡すと、少し怪しげな笑いを口元に浮かべながら握手の手を僕に差し伸べた。
その怪しげな空気が思い過ごしではなかったのが早くも証明されてしまったのは、その翌日の夜だった。友達のところに用事があるというデイブとふたりで、車の御披露目をかねたドライブにでかけた。デイブは車を持ってないので、いわゆるアッシー君だ。
行きはいたって順調だった。ところが帰り道、突如怪しげな音が車体の底の真ん中あたりからもれだし、その擦れるような金属音はだんだん大きくなってい く。そこまで軽快に続いていたデイブとの会話もそれでブツッと断ち切れた。やっぱりやられたか…と僕の気分は乱気流に巻こまれた飛行機のようにグググっと 落ち込んだ。あの調子良さそうな中近東訛りのニイチャンの別れ際の怪しげな笑いが脳裏をかすめ、もう少ししつこくチェックすべきだった、前のオーナーから 譲り受けたということがどういうことだったもっと突っ込んで聞くべきだったとか後悔したところでもうそれは後の祭。考えてみれば僕の語学力ではあれ以上の 駆け引きは無理だった。お互い立ち合いの上でチェックした時には何もおかしなことはなかったのだから向こうには非はないわけである。相手がちゃんとした自 動車屋だったら話は別だが、個人売買の場合は基本的には売ったもん勝ちである。まあ、ロンドンで生活し始めてから似たようなことはたびたびあったにしろ、 今回は払った金額が大きかっただけに、精神的なダメージは大きかった。まだその故障が大きいのか小さいのかもわからないのだからと自分を励まし、なるべく ゆっくりとごまかしごまかし走りながらまずデイブの家までたどり着いた。フウッと息をついた助手席のデイブは明日さっそく近くの修理屋に持っていったほう がいいな、まあしかたないよ、とさして同情するでもなく、そんなもんだよって小さく微笑んで“GOOD LUCK”ドアを閉めた。わざと同情したような素振りをみせないデイブの態度に感じた優しさにも励まされ、僕はクラッチをつなぎアクセルを踏み込む。神経 を逆なでする金属音に耐えながらなんとか自分の部屋までたどりつくことができたが、今度は駐車するスペースが見つからずイライラは増すばかりであった。
さっそく翌日、近所に修理工場を探しに出かけた。ポートベロー・ロードと交差し、市場が出る時もアフリカ食材の屋台や一番ガラクタに近い物が売られる通 りの一本裏側の路地に自動車の修理屋が軒を並べているのを見つけた。このあたりはアフリカ系とかのカラードの人達が多く住んでいるせいでほとんどが黒人の 人がやっている店だった。その修理屋が軒を並べる袋小路はmewsと呼ばれる通りで、どこの街にもある、かつて大きな屋敷に仕える馬車使いの家が集まって いた場所だ。2階建てで一階部分半分がガレージになっている特徴的な建物が並んでいる。ロンドンだけではなくヨーロッパの街の多くは古い景観を変えないた めに勝手には建物を建て替えることができない。通りに面した建物は公共物と考えられ、玄関の扉の色を変えるだけでも役所に届け許可が下りないとできない場 所も珍しくないという。そういう状況の中、このmewsに残っている建物はもともとは使用人のために建てられた物だから居住空間としては決して広くはない けれど、稀少価値なガレージがついていることから都心に行けば行くほど車を持っている人達の住居として人気がある。ここはそんなmewsの建物を利用した 自動車修理屋の集落のようで、特別看板を出しているわけでもないその中の一軒をたずねると、いろんな部品が雑然と並んでいる薄暗いガレージの中で、ラスタ な毛糸の帽子をかぶった黒人のおやじが暇そうに煙草を吸っていた。その格好からするとジャマイカ系か。何かブレーキが変だと症状を説明すると、そのおやじ はちょっとチェックするからと、店の前に止めたミニに乗り込み、そのままどこかに走っていってしまった。数分すると戻ってきて、たぶんサイド・ブレーキが 変で勝手にブレーキがかかってしまっているからその部分を全部取り替えなければいけないという。それはいくらいかかるのか聞くと、なんとなく僕の身なりと か品定めするかようにながめて、まあぜんぶで50ポンドくらいはかかるだろうと言う。ロンドンに来て最大の買い物をした興奮とそれがいきなり壊れた落胆が 入り交じった複雑な精神状態では、その修理代がが高いのか安いのか冷静に判断する余裕もなく、とにかく早く普通に走れるようになるのならと修理を頼んだ。 修理は半日で終り、僕の財布からはくしゃくしゃの10ポンド札が5枚消えていった。
そして可もなく不可もなくミニは走り出したが、どうもスタートに難があったのでどうしてもこの車を信用できないなあと思っていたら、ドアの内側に貼って ある人工皮革のシートに塗料を吹き付けた時に飛び散ったと思われる細かい点々があるのを見つけた。これはあきらかに塗装をし直した証拠である。趣味で色を 塗直したとは考えにくく、これは事故の後の修理の跡に違いない。まったく、遠めにはきれいなツラして、この売女めってつぶやいた後、あっ、これいいかもし れないと、この車の名前を“BITCH”と名付けた。好きだったローリング・ストーンズの曲の名前で、いわゆる汚い言葉なんだけど、悪い女ほどかわいいっ て話もよくあるし、こうなったらとことんつきあってやろうというなかばヤケクソな決意もこめてそう名付けた。
そしたらその数日後、その名前がうれしかったのかうれしくなかったのか、今度はマフラーが壊れ、暴走族の車みたいなボッボッボッボッというものすごいう なり声を上げ始めた。あんまり“BITCH”という名前がぴったりであきれて笑ってしまった。またラスタなおやじの修理屋に行き、マフラーが変だという と、オヤジは車の下をのぞきこみ、ウーンこれはマフラーが完全に破れている、ただこのミニは特別な形だからマフラーも普通のものじゃあわない、ちょっとそ れがあるかどうか確認してやる、とおもむろに電話をかけ、なにやら話し込んで電話を切り、マフラーはある、だけど120 ポンドかかる、なにせ特殊なマフラーだからなと得意げな顔で言った。タイヤもそろそろ替えたほうがいい…。なにか怪しい、そう思った。そうでなくても、こ の間の今日でいきなり120ポンドは大きすぎる。とりあえず車は走るのだから少し考えてまた来ることにして店を出た。そのままデイブの家の近くの美味しい パン屋さんでパンでも買って考えようと、歓喜の声とも聞こえなくもない排気音をうならせながら走っているとガソリンがないことに気がついた。それでふと立 ち寄ったガソリン・スタンドに併設された修理工場が目に入った。いわゆるマクドナルド的アメリカンな雰囲気の工場だ。僕がロンドンに来てから、こちらに住 むいろんな人から教わり、自分も思い込んできたことのひとつに、そのマクドナルド的アメリカンな修理工場みたいな店のものは値段が高く、個人の店のほうが 良心的で安くて良い品物が揃っているという固定概念があった。これはあきらかにイギリス的な物が良くてアメリカ的な物は認めたくないみたいなたぶんに感情 に支配された偏見に近い考え方であったが。再物利用の精神で成り立っているようなアンティーク市の街、ポートベローに住む人間のプライドからすると、この マクドナルド的アメリカンというかコンビニ的修理工場のお世話になってはいけないと普段なら考えるのだが、あまりにラスタのおやじの雰囲気が怪しかったの で、そのプライドを半分隠してコンビン的修理工場へ入ってみた。クレーンで持ち上げた車をいじっている白人のオニイチャンに“マフラーの調子が悪いんだけ ど…”と声をかけると、彼は作業の手を止めて僕のかわいい“BITCH”のお尻をのぞきこんだ。うん、マフラーがやぶれてるねというオニイチャンに、そ れっていくらで直るの?と聞くと、ン?これと同じのなら20ポンドくらいだと思うよと言った。なにそれ、20ポンドって…。
結局はすべて僕の世間知らずが呼んだトラブルだったけれど、僕が英語がよくわからないのをいいことにワケアリげな車を売った中近東系の男とブレーキの修 理もぼったくったのかもしれないラスタな黒人のおやじと続いたおかげで、僕の中で有色人種に対する懐疑心が確実に芽生えた。
マフラーは25ポンドであっさりと直った。そして数日後、ラスタな黒人のおやじの言った通りタイヤがパンク寸前の状態になり、今度はプライドもクソもな く迷わずアメリカンな修理工場でタイヤを交換をした。これでもまだトラブルは終りではなかった。ブレーキもOK、マフラーもタイヤも新品、エンジンも快調 なある日、僕はある目的地に向かってBITCHを走らせていた。その目的地が視界に入ってきたあたりから、運転している僕の意志とは関係なしにまるでイヤ イヤでもするようにグングンとスピードが落ち出した。あわてて道路端に寄った時には車は完全に前に進まなくなってしまった。進まなくなってしまったといっ ても、エンジンはちゃんと回っているし、なんか勝手にブレーキがかかってしまったって感じなんだけれど、最初のサイド・ブレーキの時のトラブルとはあきら かに症状が違う。いわゆるバッテリーが上がってしまったエンストでもなさそうだ。いったい何が起きたのかわからないまま、しばらく車を道路沿いに止めて呆 然としていたが、なんかこのトラブルはなんとかなりそうな気がしていた。そもそもがこのミニという車、東京で乗っていたような最近のハイテクカーに比べれ ば、まあゴーカートが立派になったようなもので、メカニックに強いベエさんはミニの故障ならほとんど自分で直せると言っていたくらいの、故障もなにもすべ てに身近な肌ざわりがあった。だからなんとなくだけどブレーキのトラブルではない気がした。とはいってもボンネット開けてみたところで何がなんだかわかり はしない。数分してエンジンをかけ直し、おそるおそるギアをつなぎながらアクセルを踏み込むと、何もなかったかのようにスムーズに走り出す。またすぐ止ま るかと思うとそうでもなく、しばらくは何もなかったかのように走っている。そして忘れた頃にまた同じ症状が起こり止まる。でも数分休ませるとまた走る。そ んなことが何回かあり、ふと、その止まり方に奇妙な共通点があることに気付いた。それは走り出した場所から車が走らなくなってしまった場所までの走行距離 とは関係なく、僕が目的地とする場所が僕の視界の中に入ってくるとその症状が始まるということだ。
デイブにこの車の奇妙な癖の話をすると、本当かよ?なんてやっぱり半信半疑に笑っていた。そんなある日、デイブとテニスをした後、彼が実家に帰るという ので、ロンドンの東側の玄関口、ユーストン駅まで送っていくことになった。最高にいい天気で窓から吹き込む春の風に上機嫌な2人は“彼女には目的地はナイ ショだぜ”なんて冗談を言いながらロンドンの街中を走り抜けた。そんな2人の視界にユーストン駅のレンガの壁が入って来た時、にわかにBITCHの動きに 変化が現われた。
「デイブ、来た来た!-DAVE! SHE'S COMIN'-」
助手席のデイブは現実に自分の目の前で起きた奇怪な事実に目を大きく見開いて驚き、そして完全に車が止まってしまうと手を叩いて笑い転げた。この愛敬の ある気紛れなトラブルは、その数週間後、イギリスでいう車検―といっても日本の車検のような大がかりなものではなく、免許を持っている民間の修理工場での 簡単なチェックを受けるだけで済んでしまう―のついでで診てもらったところクラッチのシリンダーのオイルがギトギトで、それでクラッチがつながらず時々空 回りしていたとわかった。シリンダーをクリーニングしてオイルを差し直してBITCHの小悪魔的なイタズラも終ったが、結果的には単なる偶然だったにし ろ、車が意志を持っているとしか思えないような奇妙な出来事だった。あれやこれやこの車に翻弄されることをどこか楽しみながら、でも確実に行動範囲が広が り、ロンドンの中のありふれた、でも僕には新しい風景を見つけながら春が過ぎて行った。
5月も半ばを過ぎ、どうせ毎週のようにテニスをするんだったら近所にメンバーフィーの安いテニスクラブがあるからそこに入ろうとデイブと盛り上がってい た矢先、デイブの1年間だけの香港転勤が決まった。最初の数ヵ月はレイコさんも一緒にいくことになり、二人からの申し出で、僕は日本に帰るまでの残り2ヵ 月を彼らの部屋に住むことになった。ロンドンでは長く部屋を空けると空き巣に狙われることが多く、前と同じ家賃でいいから住んでいてくれると助かると頼ま れて断わる理由は何もなかった。家というプライベートな場所をまかせてくれる程の友達と残り数ヵ月になったロンドンでの滞在を一緒に過ごせないのはやはり 淋しかったけれど。
セントローレンス・テラスの部屋は義理の弟の紹介で知り合ったロンドンにデザインの勉強に来たばかりの日本人女性、キョウコさんが住んでくれることに なった。僕が生き返らせた部屋が僕と同じようにこの街に何かを求めてやってきた人の役に立つことになったのはうれしかった。大家のフィリスさんも僕が部屋 を出ると言った時は後の事を考えたのか少し狼狽したようだったが、後釜がもう探してあり、さらには日本人の女性ということ聞いてほっとした様子だった。
デイブとレイコさんが急にいなくなり、学校も6月いっぱいで終って国籍も年齢もバラバラの見慣れた顔ぶれともサヨナラし、南向きでバス、シャワー、さらにはピアノ付きというフラットでひとり、1年前この街にやってきたのと同じ夏が静かに流れた。
8月に入り、このやっと肌に馴染んできた街ともそろそろ別れる準備も始めなくてはいけなかった。タクシーの運転手にだってなれるくらいの勢いでロンドン 市内や郊外を走り回った相棒のBITCHはレイコさんの友達で、やはりクラシックのピアニストのヨシコちゃんが買ってくれることが決まった。
帰国の準備、といっても一度広げたスーツ・ケースの中の荷物をまた押し込むだけの話だが、も順調に進み、明日BITCHをヨシコちゃんに渡し、3日後に は日本に帰るという日の午後だった。数日前、BITCHを買ってくれるのはいいのだけれど、マニュアル・ギアの車をほとんど運転したことがないというヨシ コちゃんと実地訓練をして、それからなんかギアが入りにくいなあと思っていたら、家まですぐのところの交差点でギアがすこんと抜けてしまったような感じで うんともすんとも動かなくなってしまい、またも立ち往生。明日、受け渡しなのになんなのよ、とほほ…。今までのトラブルとは違ってまったく動かないので、 いつものアメリカンな工場にも持って行けない。しかたないので日本でいうJAFのような組織“AA”に電話して修理に来てもらうことになった。もしやの時 のために会員にはなっていたが、利用するのは始めてことで、いやはや、今度はいくらかかるのやらと肩を落としていると、ラスタな黒人のオジサンが運転する 作業車がやってきた。ありゃ、こりゃまたラスタな人だ…、人種差別するつもりはさらさらないが、このBITCHの修理に関しては有色人種はどうも印象が良 くない。絶対にだまされないぞと、僕は思わず身構えた。ハーイとそのラスタなオジサンは笑顔で車から降りてきた。とてもいい人な感じだったが、まだやっぱ りしっかり僕は身構えていた。オジサンは症状を聞くとBITCHのボンネットを開けてなにやらごちゃごちゃいじっていたが、
「うーんギアのシリンダーが完全に終っているから交換しなきゃいけない。」
うぐっ、交換?またこの車は特殊だからとかなんとか言い出すのではとさらにガードを固める。
「この近くにミニの部品の専門店があるからそこまでオレの車でいっしょに行って部品を買ってこよう、さあ、乗りな。」
いたってなごやかな表情でそう言う。あくまでも直感だが、あまり怪しい感じがない。お店で部品を買うんだったらぼったくろうにもぼったくれないわな、ひょっとしてこの人、同じラスタマンでもいい人なのかな、と多少ガードを緩めながら作業車の助手席に乗り込んだ。
カーステレオからボブ・マーリィが流れていた。車は走りだし、僕はまだどこかに身構えている自分をほぐそうと何気なくボブ・マーリィの歌にあわせて軽く口ずさんだ。するとハンドルを握っているラスタなおじさんは言った。
「おまえはボブ・マーリィが好きなのか?」
「うん、好きだよ」
「おまえは日本人か?そうか、日本人でもボブ・マーリィのことがわかるやつがいるんだな。」
それはそれはうれしそうな顔になったオジサンもスピーカーから流れるボブ・マーリィに合わせて口ずさんだ。日本人だって音楽をかじったことのあるやつ だったらボブ・マーリィくらい知っているよ、と思いながら、僕がこうしてロンドンにいるということにボブ・マーリィの存在があながち関係なくないんだよな あってことが頭をよぎった。
1981年に36歳の若さでこの世を去ったレゲエの王様、ボブ・マーリィという存在を僕が知ったのは、多くの人がそうであるようにイギリスのロック・ギ タリスト、エリック・クラプトンによってだった。1970年代、まだジャマイカのローカル・スターだったボブ・マーリィーの曲“I shot the sherrif”をエリック・クラプトンがカバーし、これが世界的なヒットとなり、レゲエという音楽のスタイルとボブ・マーリィの名前が白人社会を中心と した意味での世界で認知された。そしてレゲエという音楽が世界の音楽シーンに大きな影響を及ぼすようになった1970年代後半、イギリスを吹き荒れていた パンク・ムーブメントのなか、ボブ・マーリィを心酔するイギリス人がレゲエとパンク・ロックを融合させたホワイト・レゲエで、世界のロックシーンに殴り込 みをかけた。現在もソロ・アーティストとして活躍を続けるスティングが率いていたバンド、ポリスである。初期の名曲“Walkin' on the Moon”は本家ボブ・マーリィも認めていたという。ブルースが出現して以降の現代のポピュラー音楽の基礎を作ったのは疑いなくアメリカ大陸に奴隷として アフリカから売られてきた黒人である。ビートルズ以降のイギリス人のミュージシャンたちは素直にアメリカ発のブラック・ミュージックに憧れ、その憧れで黒 人が創り出す自由で刺激的な音楽に自分達なりの解釈を加えた新しい音楽を創り出してきた。そのやり方は僕たち日本人にも共感できる部分が多い。ちょうどそ の頃20代に足をつっこみロック・ミュージシャンを目指して音楽にのめりこんでいた僕にはリアル・タイムでそういう新しい音楽を生み出そうとしていたポリ スの存在は大きかった。メタリックでスタイリッシュなポリスのレゲエにはボブ・マーリィのような土臭さと思想的な強さもなかったが、それゆえにまだ甘っ ちょろかった僕にはすごく理解りやすく刺激的だった。結局ロンドンに行こうと思ったのも、人権保護を訴えるアムネスティでの活動や熱帯雨林保護活動を積極 的に行なっていたそのバンドの中心人物、スティングに影響されてという部分が大きかったわけだから、僕がここにいるということにボブ・マーリィの存在は関 係なくもなかった。
思いがけないほど近くにミニの部品の専門店はあり、小さな店の壁や棚にぎっしりとありとあらゆる部品が並んでいた。これこそがこだわっていたマクドナル ド的アメリカンじゃないイギリス的な店だった。ラスタなオジサンは店員に必要な部品を伝えただけで代金は僕が直接支払ったから見事なまでの明瞭会計であ る。
道端に情けなさそうに止まっているBITCHの所へ戻り、オジサンは自分の車の開け放した窓から流れてくるボブ・マーリィのリズムで修理に取りかかった。
僕は何かこのオジサンとコミュニケーションが取りたくなって「ネエ、ジギー・マーリィはどう思う?」と最近ソロ・デビューして話題になっているボブ・マーリィの息子、ジギー・マーリィのことを話題に出したが、オジサンはちょっと首をかしげただけで何も言わなかった。
曲がフェイド・アウトして、次の曲が流れてきた。それまでのレゲエのリズムとは違う、カントリー・ブルースな生ギター一本の素朴なイントロだった。オジサンは急に修理の手を止め、僕の方を向いて言った。
「この曲には真実がある」
うんとうなずいてまたボンネットの中に頭をつっこんだ。それがどんな内容の曲なのか知らなかったが、聞いたことはあった。ロンドンに持って来ていたボブ・マーリィのベスト盤の中でも一番地味な印象の曲だった。しばらく僕は切なげなボブ・マーリィの声に聞き入っていた。
修理は終った。オジサンは車の中から書類を出してきてサインをしろという。結局AA の会員登録をしていたために、修理代はさっきの部品代だけ済んでしまった。ラスタなオジサンはオイルで汚れた手で僕の手をしっかり握りながら 「HAVE A GOOD TIME, BROTHER!」と言い、まだボブ・マーリィの歌声が響いている作業車に乗り込んで陽気に去って行った。お金とかそういうことではなくなんだか胸が暖か くなった。
すぐさま部屋に戻り、さっそくボブ・マーリィのCDをプレーヤーにかけ、さっきオジサンが真実があるといった曲を探した。その曲はボブ・マーリィが生 前、一番最後にレコーディングで残した「リデプション・ソング」という曲だった。略奪者によって奴隷商人に売り飛ばされてきた自分達の精神的奴隷の状態か ら自らを解放せよ、という激しいメッセージな詞の内容にもかかわらず、そのメロディは美しく、生ギター一本の響きの中でのボブ・マーリィの歌声は切なく優 しい。まだまだ日の入りまで時間のある夏のロンドンの夕暮れ時の風の中、今までなにげなしに聞いていたこの曲が強く僕の胸に響いた。南向きの窓の向こう、 ずっと昔からそこに立っているんだろう大きな木の青く繁った木の葉がさらさらと揺れていた。ロンドンに来て、特にこのBITCHとつきあい始めてから僕の 中にしみついてしまっていたカラードの人達に対する偏見、しこりみたいなものがすうっと洗い流された気がした。
2日後、僕は1年前と同じ、いやそれ以上になった石のように“HEAVY”なスーツケースとともにヒースロー空港へとタクシーに乗り込んだ。
僕が東京に帰るとすぐ、夏休みを利用したデイブとレイコさんが香港からやってきて、東京の僕のアパートに泊まりに来ることになっている。なんだか変な感 じだ。そんなんだったからあまりロンドンを去るという感慨もなく、ぼくの口元には2日前から何度も繰り返し聞いていた「リデプション・ソング」があった。
デイブとレイコさんのフラットをあとにしたタクシーがラドブローク・グローブを南に下る。まだ過去にはなっていない見慣れた風景がそこにある。運河に架 かる橋を渡り、ロータリー式の交差点“ラウンド・バウト”を越すと、消防所の向こうに教会の塔が見えてくる。その奥にあるセント・ローレンス・テラスのあ のフラットの、僕の部屋だった窓が一瞬目の前を横切る。あの部屋に引っ越してきた日、肌寒くグレイな空の下、この通り沿いの屋台で黄色い水仙の花を買った ことを思い出す。
そして頼んだ訳でもないのにタクシーはその先の交差点を右折し、ヨシコちゃんのフラットがある通りに入る。彼女のフラット前の路上に、半年かかってやっ と淑女に仕立て、昨日の夕方、無事にヨシコちゃんの所へ嫁入り?したBITCHの姿を見つける。アッと言う間にタクシーはその小さな車の横を通り過ぎ、あ わてて振り返ったリア・ウインドウの中の愛車がどんどん小さくなって行く。この瞬間に初めて、ああ、僕はこの街とさよならするんだという実感がこみあげ、 少し目頭が熱くなった。
タクシーが角を曲がり、完全にBITCHが見えなくなり、身体を前に向き直すと、ガラス窓の向こうには雲の白さとうまく混ざりあった夏の青い空があった。
同じなのに違う空。
ここに来た頃、いつもそうやって見上げていた空が当り前のようにそこにある。
これから10数時間後、東京に着いた時にもきっと僕は見上げるんだろう、同じなのに違う空を。
|
prologue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7| #8| #9| #10| #11|#12|#13|#14|#15|#16| |
|