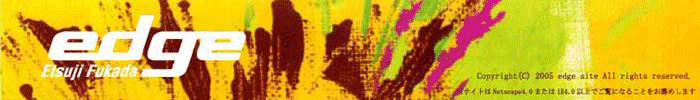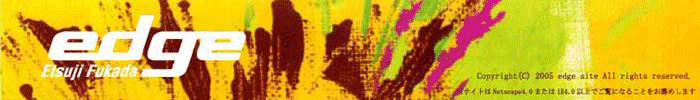カフェ*トレボのまわりの小さなオアシス。
カフェ*トレボのまわりの小さなオアシス。
まだ夕闇には遠い初秋の黄昏時。気持ちの良い風が流れて行く。
僕はいつもの場所、カフェ*トレボの脇、東西に伸びる緑道と
南からの道路がぶつかるT字路の角に立ち、演奏を始めていた。
唄いながら目に映る街の光景の片隅に、黒いパンツ・スーツに身を包み、
黒いブリーフケースを肩から下げた、すらりと背の高い女性の姿があった。
立ち止まって携帯電話で話しをする彼女のいる場所には、たぶんうっすらと
僕の唄が届いていたはず。でも言葉ははっきりとは聞き取れないだろう、
そんな距離。視界の中の彼女は、通り過ぎていくたくさんの人たちの中の
ひとりだった。
一期一会。
僕はフォーカスを手前に絞り、風景と溶け込むよう、音に集中する。
次に彼女の姿をとらえたのは、カフェ*トレボから道一本はさんだ
緑道のベンチ。
いつの間にか十分に僕の声が届く距離まで近づいていた彼女の姿は、
僕には背を向けていたけれど、横顔はわかる角度。
なにやら考え事でもしているようにぼんやりと座っていた。
僕は目を閉じてハーモニカを吹く。街の音が奏でるオーケストレーションを
バックに、ブルーノートなフレーズが空へ舞い上がる。
ハーモニカのソロを吹き終えて目を開けると、カフェ*トレボのカウンターの
前で飲み物を注文する彼女の姿があった。
笑顔で紙コップの飲み物を受け取った彼女は、そのまま僕の少し前を横切り、
唄っている場所の左前にある街路樹脇、
花壇の縁がベンチになったところに腰かけた。
さらに僕との距離は近づいたけれど、特にこちらを意識するふうでもなく、
宙を見つめながらコーヒーをすすり始める。僕も彼女を意識しないよう宙を
見つめながら唄い続ける。
曲が終わり、次の曲に使うハーモニカを取り替えながらベンチに視線を向ける。
すると彼女はパンプスを脱ぎ、ベンチの上で足を上げた横座り状態に
なっていた。そして膝の上に乗せたノートに何かを書いている。
彼女がしっかりと僕の音の中にいるのは確かだけど、
こちらに目線を送る訳でもなく、かといって拒絶するでもない。
僕の作り出そうとしている世界感を壊さないようにと気遣ってくれている
ようにさえ思える。ここで唄い始めて、初めて体験する送り手と聞き手の
関係だった。
いつも唄っている曲をすべて唄い終えた。
音はもう消えているのに、彼女にはまだ音楽が続いているかのように姿勢を
変えず、膝の上のノートに何かを書き込み続けている。
僕は、まだ彼女の頭の中で続いているかも知れない音楽がとぎれないように
そっと、カフェ*トレボのカウンターに移動した。
ギターをケースに入れ、カフェ・マキアートを注文し、ヒロミちゃんと
立ち話をする。最終的に街路樹脇のベンチまで移動してきた彼女のことを
話すと、ヒロミちゃんも“雰囲気のある、きれいな方でしたねぇ”と、
カウンター越しに接客した時の印象を語った。
ふと街路樹脇ベンチの方を見る。彼女はさっきのままの姿勢で、でもペンは
止まり、穏やかな表情で街をながめていた。
自然に僕の足は動き出し、出来立てのカフェ・マキアートを持ったまま彼女に
近寄り、声をかけた。
「あの、ひょっとして、ずっと聞いていてくれたんですか?」
初めて目と目が合った。とても透明感のある笑顔だった。
「ええ、次の仕事まで少し時間が空いて、喫茶店でも入ろうかなって
思っていたら音楽が聞こえてきたので、ずっと聞いちゃいました。
なんか、すっごく気持ち良かったですよ。」
そしてベンチから足を降ろしてパンプスを履き、姿勢を正して言った。
「ねえ、ひとつ聞いてもいいですか?
こういう場所で唄い出す時ってどんな感じですか?怖くありませんか?」
僕は立ったまま、彼女は座ったままで、
今度は僕が彼女の声を聞かせてもらう番だった。
彼女は会社とかで上に立つ立場の人たちや、個人で事業を起こしていたりする
人たちなどに自信を持たせ、仕事が潤滑に運ぶような心のアドバイスをする
「コーチ」という仕事をしていると言った。
僕はそんな職業があることさえ知らなかったけれど、お役所が認可した資格を
必要とするちゃんとした仕事で、カウンセリングのように
個別に対応することもあれば、企業などから呼ばれてセミナーのような形で
大勢の人たちの前でしゃべる時もあるそうだ。
「私、人に自信を持たせることを仕事にしているのに、
今だに人の前でしゃべるのが怖くって・・・。だから、もちろんあなたの
音楽も気持ちよかったんだけど、こんな場所で、しかもひとりで、
どんな気持ちで唄っているんだろうってことも気になって。」
人を安心させることのできる落ち着いた、豊かな声を彼女は持っていた。
かつてはモデルでもやっていたんだろうと思わせる容姿も、人の心を
つかまえる仕事には大きな武器になっているのだろう。だけど20代後半か
30代前半にしか見えない若さで、地位や意識が高い人たちと対するのは、
かなり勇気がいるに違いない。
僕だって、唄い出す瞬間まで怖くてしょうがない。家を出て、ここまでやって
来る間だけでも何度もやめて帰ろうかと考える。別に誰に頼まれてやっている
訳でもないし、もういいかって思っちゃえばそれだけのこと。
そんな瞬間瞬間に僕は試されているんだと思う、どれだけ僕が音楽に対して
本気なのかどうかを・・・そんなことを彼女に話した。
普段はカウンセラーのような立場にある人をカウンセリングしているような
雰囲気になっていたところへ、突然ドッカーンと爆弾が飛び込んできた。
りかちゃんだった。
「ねえ、おにーさん、うたを作ろうよお!」
「よし、じゃあ、りかちゃん。このおねえさんにさ、こないだ作った
“I LOVE YOU”を唄ってあげようか?」
「うたおう!うたおう!」
「よし、じゃあ、秘密基地に行ってうたうか!」
秘密基地とは、カフェ*トレボの裏側、フォルクス・ワーゲンのバンの
リア・ウインドウ側とビルの間に出来た小さなスペースのこと。
この場所にギターケースを置かせてもらっている。まあ僕にとっては
楽屋のようなこの場所をりかちゃんが気に入り、ここんとこの遊び場に
なっていた。
僕たち3人は秘密基地に移動して、ギターを持った僕と彼女は、ビルと通りの
境目の低い壁に腰掛け、りかちゃんは僕の正面に立った。
開け放したリア・ウインドウ越しで、キッチンに座ったヒロミちゃんが
笑顔で見ている。
そして僕とりかちゃんは向かい合い、目と目を合わせながら、
街角のオリジナルソングを熱唱した。
大声で唄ったりかちゃんは、それで十分に満足したのか、風のように街の中へ
消えて行く。その後ろ姿を笑いながら見ていた彼女は、ふと腕時計を見て、
“わっ”っと小さな声を出した。彼女も仕事に戻らなければいけない時間に
なったようだ。
「ああ、なんだか、すっごくやる気が出て来た。じゃあ、私もがんばって
自分を表現してきます。ほんとうにありがとう!」
彼女は黒いブリーフケースから、何かを取り出そうとした。きっと名刺でも
出そうとしたんだろう。でも手を止めた。
「また、いつかどこかでお会いできますよね。」
彼女は荷物を抱え、飲み干した紙コップをカフェ*トレボのカウンター前の
ゴミ入れに入れ、ヒロミちゃんに“ごちそうさま”と頭を下げた。
そして、もう一度僕の方を振り返り、最高の笑顔を投げかけ、
人ごみの中へ消えて行った。
一期一会。
お互い名乗りもせず、もうこれで2度と会うこともないのかも知れない。
それでいいと思った。
今日の、この自然な流れは、自然なまま流れていった方がいいと思えた。
僕の心には暖かいものが残った。