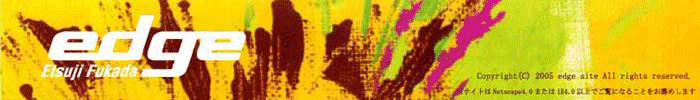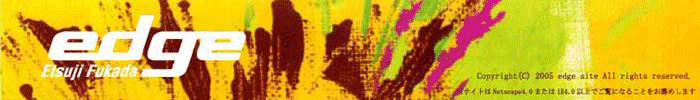6月、ギターを抱えた僕はロンドンにいた。
その12年前、それまでの仕事を辞め、新しい自分が見つかるかも
知れないと、ひとり、このロンドンで生活した。
あの、空ばかり見上げていた1年ちょっとの間、
確かに貴重な体験はいくつもあったけれど、結局、これが自分だと
言い切れるほどの何かを見つけることはできなかった。
この春からひとり、路上でギターを抱えて唄い始めた。
やはり、新しい自分を見つけるために。
雑踏の中で唄いながら、いつも脳裏をかすめるのは、
あの頃、このロンドンのあちこちで自然に響いていた
ストリート・ミュージシャン達の奏でる音、そんな情景の記憶。
12年たって、東京の空の下で響く音の中で、やっとつかみかけた
自分でしか奏でられない音楽を、あのロンドンの空にも響かせて
みたいと思った。
僕はギターを抱えてコヴェント・ガーデンに向かった。
ここはかつてロンドンの胃袋を支えた中央卸売り市場があった
ところで、周辺にはオペラハウスや劇場、ミュージアムなどが
集まり、かつての市場の建物にはカフェなどの店が入り、
それを中心とした広場はいつも観光客などで賑わっている。
そんな人の集まる場所には当然ストリート・パフォーマー達も
集まって来る。市場だった建物の中の、吹き抜けになった地下の
カフェ前のスペースでは弦楽四重奏の若いグループの演奏が
繰り広げられ、広場の一角ではチャップリンの格好の大道芸人の
パフォーマンスが笑いを呼ぶ。こんな風景は12年前となんら
変わってない。
ただ、あの頃と違っているのは、アコースティックギターを抱えた
弾き語りのミュージシャンがマイクを使ってスピーカーから音を
出して演奏していること。
地下鉄の駅から広場へ入る辺りの“一等地”で、発電機を回し
ギターアンプから出てくる音は、そばに近づいてみると
すこし割れているくらいデカイ。遠くまで存在をアピールするには
効果的だろうが、この風景に対してこの音量、音質は少々品に
かけるような気がした。あの頃、僕が好きだったのは、弦が切れた
ボロボロのギターを、まるでパーカッションのように弾きながら
唄う黒人のニイチャンの生の声が、自然な街のざわめきと
溶け合いながら響くこの広場の風景だった。
何周かこの広場を回ってみたが、他の場所にもやはりアンプを
使ったミュージシャンが演奏していて、彼らの音に支配されて
しまった広場に、僕が音を響かせてみたいとそそられるスペースは
残されてはなかった。
それでコヴェント・ガーデンを離れ、歩いてテムズ川に架かる
ウォーター・ルー橋を渡り、サウスバンクを目指す。
この橋の上からは、いわゆる絵葉書にでもなりそうなロンドンの
風景が見渡せる。ここに住んでいたあの頃も何度となくこの
ウォーター・ルー橋を渡り、サウスバンクへ行った。
サウスバンクとは、テムズ川沿いに大中小の3つの演劇用の劇場、
やはり大中小のコンサートホール、映画の博物館、ギャラリーなど
国立の芸術関係の施設が集まった場所だ。ちょうどこの6月は
デビッド・ボウイが芸術監督のイベント“MELTDOWN”の最中で、
大ホール、ロイヤル・フェスティバル・ホールを中心とした
各コンサート・ホールや屋外の特設ステージでデビッド・ボウイが
セレクトしたアーティストのライブが毎夜のように行なわれていた。
コンサートの開かれるロイヤル・フェスティバル・ホールの
2階部分のバルコニーも、開演前のひとときをビールとか片手に
楽しむ人達であふれていたが、さっきのコヴェント・ガーデン
とは違って、そこに流れる空気にはどこかゆったりとしたムードが
漂っていた。
僕はそのバルコニーの下の、川沿いの遊歩道の一角に立ち止まり、
回りの風景を見ていた。テムズ川の向こう側にはサヴォイ・ホテル
など重厚な建物が立ち並び、上流側の鉄橋の上を始発駅の
チャリング・クロスを出たばかりの列車がゆっくりと通り過ぎ、
川面を何槽かの遊覧フェリーが走り抜けて行く。
曇り空。
時折、川面を走る強い風が吹き抜け、半袖のTシャツだけでは
少し肌寒いけれど、ロンドンの夏としては悪くない陽気に、
遊歩道沿いに並んだベンチに腰掛けた人達の表情も柔らかい。
うん、ここかも知れない。ギターをケースから取り出し
チューニングをしてハーモニカホルダーを首にかける。
この街のこの風にはまずブルースかな、とキイがAのハーモニカを
ホルダーにはめる。ギターにストラップをつけ肩からかけて
立ち上がる。いつものように路上で唄い出す前の緊張感が全身を
包み、頭の中を一瞬真っ白にする。そして“パンジー”の
イントロのハーモニカのフレーズを吹く。
乾いた空気にハーモニカが、ギターが、そして声が思っていた
以上によく響く。目の前をいろんな人種のいろんな人が通り過ぎて
行く。彼らは聞き慣れない言葉の、僕の唄の中を通り過ぎて行く。
スケートボードに乗った若者が通り過ぎる。風が吹き、枯れ葉も
踊るようにカラカラと通り過ぎて行く。他にはない自分だけの音楽が
ロンドンの空に響く。
どこからか黒人の男性と白人の女性のカップルがやってきて、
少し離れたベンチの後ろの石段に腰掛け、ふと目が合った時に
とても素敵に笑顔を返してくれる。
次はレゲエだな、と “INDIAN SUMMER”を唄う。
ハーモニカのソロを目を閉じて吹く。
ソロを終えて目を開けると、いつの間にか、ここから一番近い
ベンチに座っていた白人の若いカップルが目の前に立っていた。
彼らは各々がポケットから取り出した小銭を、そんなつもりでは
なく僕の足元に横たえてあったギターケースの上に置き、
微笑みながら小さく手を振ってホールの方へ歩いて行った。
東京の路上でも週に一回位のペースで3ヵ月間唄ってきたけれど、
あえてそういうお金をもらうようなシチュエーションを作ったり
していなかったし、今回もそんなつもりだったので、なんとも
さりげない彼らのふるまいにグッと来て目頭が熱くなった。
音を奏でること、そしてそれを受け止めることの関係があまりに
自然に成り立っているこの街に改めて文化を感じた。
なんだかすっと肩が軽くなって、
僕はさらに“ズル休み”を唄った。
間奏の後、絶妙なタイミングでフェリーの汽笛が鳴った。
街もワルツを踊ってくれた。
ふと見上げると、ホールの脇に大きく掲げられた
“MELT DOWN”の看板があった。ひょとしたら僕は、
デビッド・ボウイのイベントに参加していることになるのかなぁ?
などというバカなことを考えたりした。
唄い終え、しゃがみこんでギターを片付けながら、
さっきのカップルが置いていってくれた小銭を数えると、
20ペンス玉が2個、5ペンス玉が4個、2ペンス玉が1個、
1ペンス玉が4個で合計66ペンスだった。
3曲唄って、たったの66ペンス。
たったの66ペンスなんだけど、この66ペンスが、
そのお金の価値では計れない大きなものをくれた気がした。
12年前、ここで僕が探していたのものは、
この66ペンスだったのかも知れない。
そう、ここからさ。さあ、この66ペンスから始めよう。
6月、ギターを抱えた僕はロンドンにいた。
その12年前、それまでの仕事を辞め、新しい自分が見つかるかも
知れないと、ひとり、このロンドンで生活した。
あの、空ばかり見上げていた1年ちょっとの間、
確かに貴重な体験はいくつもあったけれど、結局、これが自分だと
言い切れるほどの何かを見つけることはできなかった。
この春からひとり、路上でギターを抱えて唄い始めた。
やはり、新しい自分を見つけるために。
雑踏の中で唄いながら、いつも脳裏をかすめるのは、
あの頃、このロンドンのあちこちで自然に響いていた
ストリート・ミュージシャン達の奏でる音、そんな情景の記憶。
12年たって、東京の空の下で響く音の中で、やっとつかみかけた
自分でしか奏でられない音楽を、あのロンドンの空にも響かせて
みたいと思った。
僕はギターを抱えてコヴェント・ガーデンに向かった。
ここはかつてロンドンの胃袋を支えた中央卸売り市場があった
ところで、周辺にはオペラハウスや劇場、ミュージアムなどが
集まり、かつての市場の建物にはカフェなどの店が入り、
それを中心とした広場はいつも観光客などで賑わっている。
そんな人の集まる場所には当然ストリート・パフォーマー達も
集まって来る。市場だった建物の中の、吹き抜けになった地下の
カフェ前のスペースでは弦楽四重奏の若いグループの演奏が
繰り広げられ、広場の一角ではチャップリンの格好の大道芸人の
パフォーマンスが笑いを呼ぶ。こんな風景は12年前となんら
変わってない。
ただ、あの頃と違っているのは、アコースティックギターを抱えた
弾き語りのミュージシャンがマイクを使ってスピーカーから音を
出して演奏していること。
地下鉄の駅から広場へ入る辺りの“一等地”で、発電機を回し
ギターアンプから出てくる音は、そばに近づいてみると
すこし割れているくらいデカイ。遠くまで存在をアピールするには
効果的だろうが、この風景に対してこの音量、音質は少々品に
かけるような気がした。あの頃、僕が好きだったのは、弦が切れた
ボロボロのギターを、まるでパーカッションのように弾きながら
唄う黒人のニイチャンの生の声が、自然な街のざわめきと
溶け合いながら響くこの広場の風景だった。
何周かこの広場を回ってみたが、他の場所にもやはりアンプを
使ったミュージシャンが演奏していて、彼らの音に支配されて
しまった広場に、僕が音を響かせてみたいとそそられるスペースは
残されてはなかった。
それでコヴェント・ガーデンを離れ、歩いてテムズ川に架かる
ウォーター・ルー橋を渡り、サウスバンクを目指す。
この橋の上からは、いわゆる絵葉書にでもなりそうなロンドンの
風景が見渡せる。ここに住んでいたあの頃も何度となくこの
ウォーター・ルー橋を渡り、サウスバンクへ行った。
サウスバンクとは、テムズ川沿いに大中小の3つの演劇用の劇場、
やはり大中小のコンサートホール、映画の博物館、ギャラリーなど
国立の芸術関係の施設が集まった場所だ。ちょうどこの6月は
デビッド・ボウイが芸術監督のイベント“MELTDOWN”の最中で、
大ホール、ロイヤル・フェスティバル・ホールを中心とした
各コンサート・ホールや屋外の特設ステージでデビッド・ボウイが
セレクトしたアーティストのライブが毎夜のように行なわれていた。
コンサートの開かれるロイヤル・フェスティバル・ホールの
2階部分のバルコニーも、開演前のひとときをビールとか片手に
楽しむ人達であふれていたが、さっきのコヴェント・ガーデン
とは違って、そこに流れる空気にはどこかゆったりとしたムードが
漂っていた。
僕はそのバルコニーの下の、川沿いの遊歩道の一角に立ち止まり、
回りの風景を見ていた。テムズ川の向こう側にはサヴォイ・ホテル
など重厚な建物が立ち並び、上流側の鉄橋の上を始発駅の
チャリング・クロスを出たばかりの列車がゆっくりと通り過ぎ、
川面を何槽かの遊覧フェリーが走り抜けて行く。
曇り空。
時折、川面を走る強い風が吹き抜け、半袖のTシャツだけでは
少し肌寒いけれど、ロンドンの夏としては悪くない陽気に、
遊歩道沿いに並んだベンチに腰掛けた人達の表情も柔らかい。
うん、ここかも知れない。ギターをケースから取り出し
チューニングをしてハーモニカホルダーを首にかける。
この街のこの風にはまずブルースかな、とキイがAのハーモニカを
ホルダーにはめる。ギターにストラップをつけ肩からかけて
立ち上がる。いつものように路上で唄い出す前の緊張感が全身を
包み、頭の中を一瞬真っ白にする。そして“パンジー”の
イントロのハーモニカのフレーズを吹く。
乾いた空気にハーモニカが、ギターが、そして声が思っていた
以上によく響く。目の前をいろんな人種のいろんな人が通り過ぎて
行く。彼らは聞き慣れない言葉の、僕の唄の中を通り過ぎて行く。
スケートボードに乗った若者が通り過ぎる。風が吹き、枯れ葉も
踊るようにカラカラと通り過ぎて行く。他にはない自分だけの音楽が
ロンドンの空に響く。
どこからか黒人の男性と白人の女性のカップルがやってきて、
少し離れたベンチの後ろの石段に腰掛け、ふと目が合った時に
とても素敵に笑顔を返してくれる。
次はレゲエだな、と “INDIAN SUMMER”を唄う。
ハーモニカのソロを目を閉じて吹く。
ソロを終えて目を開けると、いつの間にか、ここから一番近い
ベンチに座っていた白人の若いカップルが目の前に立っていた。
彼らは各々がポケットから取り出した小銭を、そんなつもりでは
なく僕の足元に横たえてあったギターケースの上に置き、
微笑みながら小さく手を振ってホールの方へ歩いて行った。
東京の路上でも週に一回位のペースで3ヵ月間唄ってきたけれど、
あえてそういうお金をもらうようなシチュエーションを作ったり
していなかったし、今回もそんなつもりだったので、なんとも
さりげない彼らのふるまいにグッと来て目頭が熱くなった。
音を奏でること、そしてそれを受け止めることの関係があまりに
自然に成り立っているこの街に改めて文化を感じた。
なんだかすっと肩が軽くなって、
僕はさらに“ズル休み”を唄った。
間奏の後、絶妙なタイミングでフェリーの汽笛が鳴った。
街もワルツを踊ってくれた。
ふと見上げると、ホールの脇に大きく掲げられた
“MELT DOWN”の看板があった。ひょとしたら僕は、
デビッド・ボウイのイベントに参加していることになるのかなぁ?
などというバカなことを考えたりした。
唄い終え、しゃがみこんでギターを片付けながら、
さっきのカップルが置いていってくれた小銭を数えると、
20ペンス玉が2個、5ペンス玉が4個、2ペンス玉が1個、
1ペンス玉が4個で合計66ペンスだった。
3曲唄って、たったの66ペンス。
たったの66ペンスなんだけど、この66ペンスが、
そのお金の価値では計れない大きなものをくれた気がした。
12年前、ここで僕が探していたのものは、
この66ペンスだったのかも知れない。
そう、ここからさ。さあ、この66ペンスから始めよう。