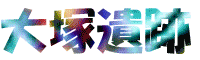
| 表 紙 | 大塚・歳勝土 遺跡 |
大塚遺跡 説明 |
歳勝土遺跡 説明 |
横浜市内 史跡めぐり |
リンク |
|---|
![]()
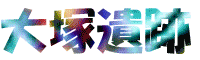
| 項 目 | 説 明 |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市都筑区大棚西1番 |
| 国史跡指定年月日 | 1986年(昭和61年)1月31日 |
| 開園年月日 | 1996年(平成8年)3月23日(大塚・歳勝土遺跡範囲) |
| 遺跡公園全体 | 1997年(平成9年)3月29日(遺跡公園全体) |
|
大塚遺跡の名の由来 |
『都筑郡中川村全図』記載の「大塚」という字名によっていますが、その由来は『新編武蔵風土記稿』の巻之八十七都筑郡之七の大棚村に「大塚二ヶ所村ノ北ノ方ニアリ」と記述され、調査時には遺跡内に中世の塚が確認されました。 |
| 施設内用 | 弥生時代復元竪穴式住居・弥生時代復元掘立柱建物(高床式倉庫)・型取復元住居跡・復元環濠、土塁、木柵・再現木橋 |
| 時代背景 | 弥生時代は、人々が収穫物や水田や用水などのムラの財産をめぐって争いをはじめました。又集団と集団の争いをもはじめるようになった時代でもあります。 |
| 環濠集落 | 環濠集落は、水稲農耕技術やその道具などとともに、大陸や朝鮮半島から伝わってきたあたらしい村の形です。 |
| 集落 | 東西220m・南北130mの範囲に広がります。 |
| 軒数 | 竪穴住居跡85軒(住居の建替え等を含め延べ115軒)掘立柱建物跡(高床倉庫)10棟、新旧環濠2条、柱穴列4基、溝7条 |
| 竪穴住居跡 |
85軒で、一辺4〜5mの小型のものから、8〜9mを測る大型のものもあります。平面形は楕円形あるいは小判形をしています。集落の中央部には10m近い大型のものが3軒。これらの住居跡は、遺跡の北部・東部・南西部・の3ヶ所にまとまっていることから、これらの場所を占有する3つのグループによって集落が構成されていたと考えられます。 |
| 集落の変遷 | 集落全体の存続が数十年で、その間段階的に最低でも5回の住居の変遷があったと想定されます。 |
| 同時に建っていた住居の数 | 20〜30軒、100人余りの人々が生活していたと考えられます。 |
| 火災の跡 | 39軒が火災にあったと考えられる跡が発見されました。 |
|
掘立柱建物跡 (高床倉庫) |
全体で10棟発見されました。3つのグループの各住居跡郡に付随する形で、その外周寄りに建てられています。6〜8本の柱が対をなし長方形に配置された高床式の建物で各くグループがそれぞれ保有していた倉庫と考えられます。 |
| 環濠 |
環濠は、全長で約600mに及び、新旧の2本の濠が台地の縁を地形に沿って全周しています。古い段階のものは、北側の谷頭をまわって中ほどがくびれた繭方をしています。新しい段階のものは北側の谷を横切る形で廻っています。濠の規模は、最大幅4.5m、深さ2.5mほどでその断面は逆台形で、上部に開き、下部は垂直に近い形になっています。濠は切れ目なく廻っています。集落への出入りには木橋が使われていたものと考えられます。全体的に集落のある内側のほうが急な傾斜になるように作られています。掘りあげた土は、環濠の外側に積み上げて土塁状のものを設けていた可能性があります。濠は空濠であったようです(水はけの良いローム土) |
| 土器 |
弥生時代中期後、葉の宮(ようのみや)ノ台式土器で、環濠の中からは380点を超える完形・半完形の土器と、26,000点以上の破片が出土しています。煮炊きに使用する甕、甕は文様のないものが大部分です。貯蔵用の壺、壺には文様や赤彩が施されています。 |
| 石器 |
磨製石斧(石を磨いて形を整え、刃をつけた斧です)木を切り倒し、削り、彫るための木工具として使用された(多数発見されました)。 |
| 石器品・土製品 | 管玉や丸玉などの装身具、糸を紡ぐための紡錘車などが発見されました。 |
| 炭化米・桃の種子 | 火を受け、炭化した状態で住居跡や環濠の中から発見されました。 |