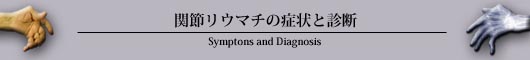
関節リウマチは、歴史的にはヒポクラテスの時代から関節の痛みを起こす病気として記述されていました。しかし、いろいろな病気がごちゃこちゃになっていて、病気として独立した概念にまとめられたのは20世紀になってからのことです。今でも、ロイマチスと呼んでいろいろな関節痛疾患を同じに考えている医者も少なくありません。以前は慢性関節リウマチと呼ばれていましたが、急性関節リウマチというのは無いので慢性という接頭語が取れたのはほんの数年前のことです。
関節リウマチ (Rheumatoid arthritis) とは、症状から一言でいえば多発性に関節の炎症を起こし、破壊された関節の変形が次第に進行していく病気です。 関節が痛いだけであれば、リウマチ以外の原因のことが多いのですが、関節炎症状となるとリウマチの可能性が高まります。関節炎といえるのは、痛みに腫れと発赤・熱感を伴う場合です。
原因は? 明解な原因は不明ですが、自分で自分の体に対してアレルギー反応を起こしてしまう病気の一つと考えられています。このような病気を自己免疫疾患と呼び、特に結合組織(内臓や器官ではない部分)に対してアレルギーを起こすものを膠原病と呼んでいます。関節リウマチは膠原病の中の代表的な病気です。
有病率は0.5〜0.8%程度といわれており、日本だけでも70万人の患者さんがいます。そのうち80%以上が女性です。
典型的には40歳代に、手足の関節の腫れと痛みで発症します。しかし近年高齢発症も少なくなく診断・治療上、問題になっています。指のような小さな関節を中心とする場合と、膝などの大きな関節を中心とする場合があります。手のこわばり、特に朝に強いというのがよくいわれます。ただし、注意すべき症状ではありますが、こわばりがあるからといって必ずリウマチというわけではありません。
診断は一般的にはアメリカリウマチ学会が作成した基準を使用して判断します。
アメリカリウマチ学会分類基準(1987)| * | 1 | 少なくとも1時間以上の朝のこわばり |
| * | 2 | 3ヶ所以上の関節の腫脹 |
| * | 3 | 手関節または指の関節の腫脹 |
| 4 | 左右対称性関節炎 | |
| 5 | 手の周辺のレントゲン異常 | |
| 6 | 皮下結節 (皮膚の下に小さなしこりを触れます) | |
| 7 | リウマトイド因子陽性 (血液検査で判断) | |
| [判定]上記の4項目以上を満たせばリウマチとする | ||
| *印は6週間以上持続していること |
この基準によれば、確実度は高いのですが、早期の診断をするには問題があります。診断を確定できる状態は、すでに病気が進行しており、少なくとも6週間以内の診断は不可能です。レントゲンの変化は、実際には骨の形状の変化であり、基本的には不可逆性であるので、その前に診断し治療を開始できることが大事です。
そこで、日本リウマチ学会では早期診断のために、基準を緩和したものを策定しています。
関節リウマチの経過は、大きく分けると関節破壊が進み(1)骨が欠損して不安定になっていくもの、と(2)骨癒合により関節が強直していくものに分けられ、その程度は人によって様々です。関節は場所によって、多少のぐらつきがあっても困らないことがあります。また固まってしまっても支障がないこともあります。その逆に、少しの不安定性でも大きな問題になったり、大きな可動範囲がないと困る関節もあります。罹患した関節の数によっても違ってきますので、なかなか予後を予想していくことは困難です。また、一般的には数週間から数ヶ月間の大きな症状の波があり、次第に悪化していくことが多いのですが、このパターンにもいろいろあり、なかなか一定の経過というものがありません。早期からしっかりと病気の勢いを抑え込んでコントロールしていかないと、最悪寝たきりも珍しくありません。
主な血液検査
● リウマトイド因子 (RF,RAT,RAHA,RAPA)
自分の免疫グロブリン(免疫反応の主役)に反応する自己抗体の一つで、通常IgMと呼ばれるものを測定します。発症早期の陽性率は40%、進行しても80%といわれ、リウマチなら必ず出るわけではありません。重症の場合、高齢者では高値になりやすく、リウマチ以外でも膠原病や肝疾患、慢性感染症、さらには数%の健常者でも陽性になることがあります。したがって、これだけでリウマチの診断を下すことはできません。経過観察をしていく上でのリウマチの病勢を判断する材料として注目します。同様のもので、IgG型のリウマトイド因子はよりリウマチの関連が高いと考えられています。また、抗ガラクトース欠損IgG抗体は、リウマチでの特異性が高いといわれています。
● 抗CCP抗体
冠状シトルリン化たんぱんと呼ばれる物質に対する抗体で、リウマトイド因子よりも疾患特異性が高いため注目されています。このたんぱくは炎症滑膜組織に存在し、リウマチの発症にも関与していると考えられています。リウマチ患者での陽性率は約70%ですが、陽性者がリウマチである確率は98%と大変に高く、リウマトイド因子とあわせることで診断の精度が高まることが期待されています。ただし逆に治療効果による低下は不明で、リウマチの勢いの判定には使用できないかもしれません。日本では2007年春に保険適応となる予定です。
● マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)
滑膜や軟骨から分泌されるタンパク分解酵素で、リウマチでは滑膜炎組織から産生され、直接軟骨の破壊に関与すると考えられています。滑膜炎の程度に依存するため、リウマチの勢いを判断する指標になり、高いほど関節破壊の進行が早いといわれています。ただし、ステロイドの影響で増加したり、ほかの疾患でも高値になるので診断のためには特異的ではありません。
● 補体価 (CH50, C3, C4)
補体は免疫反応の過程で使われるたんぱく質です。免疫反応の異常を伴う疾患では、産生低下・消費増大による低補体となることがあります。自己免疫疾患の多くがこれにあたりますが、リウマチでは急性期炎症性反応物質としてむしろ高値になることが一般的です。低下している場合は、膠原病の合併やより重篤な状態を考慮します。
● C反応性たんぱく (CRP)
急速炎症の代表的なマーカーです。疾患特異性はありませんが、関節症状しかないCRP高値はリウマチを疑う根拠になります。採血をした数時間前の状態を鋭敏に反映しますので、リアルタイムなリウマチの活動性を判定するのに用いられます。
● 血清アミロイドA (SAA)
慢性炎症性疾患に続発する内臓を中心とした異常たんぱく蓄積の病態をアミロイドーシスと呼び、リウマチもアミロイドーシスを起こす代表的な疾患の一つです。CRPと高い相関をしめし、CRPが陰性の場合でもSAAは検出される場合がしばしばあります。アミロイドーシスは生命予後に影響するため、長期間の炎症状態を極力回避することが重要であり、SAAの測定はそのモニタリングとして有用です。
● 赤血球沈降速度 (赤沈、血沈、ESR)
血液を試験管に入れ1時間でどのくらい上澄みが出てくるかを見るもので、古典的な炎症の程度を知るための検査法です。いろいろな影響を受けやすく、また実際の病態よりも遅れて異常が出てくるために、CRPなどが一般化した現在ではあまり使われなくなりました。しかし、リウマチでは炎症の上下があるために、CRPだけでは異常を捕らえられないこともあるためCRPとあわせて測定することは意味があります。