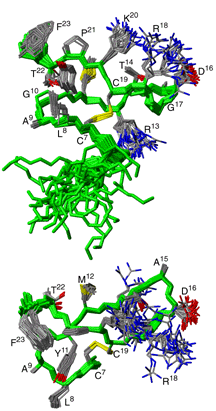リウマチの勉強をしていると、サイトカインということばが頻繁にでてきます。特に最近は、直接治療に利用されるため、サイトカイン抜きでは話が進まないという状況になっているのです。ところが、サイトカインの研究というのは1970年代に始まり、1980年代以降になって急速に進んだものですから、私たちのような昭和生まれの医者は、実は医学部の授業ではほとんど教わっていない。いやー、年をとってから新しいことを勉強するのはつらいですよね。そんなわけで、今回は自分の勉強だと思って少しわかりやすくまとめてみようという試みです。
そもそもサイトカインって何? それがわかけば苦労しない。簡単に一言で言うと、細胞から出てきて他の細胞の生き死にや働きの調節をするタンパク質でできた物質ということになります。この調節のことを、もう少し難しい言葉で言うと「細胞間の情報伝達」となり、伝達された情報により主として炎症・免疫・アレルギーなどの生体防御系に影響するということです。サイトカインの働きに異常が生じると、様々な病気の出発点になってしまうのです。
ひとつのサイトカインは複数の機能を持ち、かついくつものサイトカインが同じ機能をもっているという特徴があります。またサイトカイン同士が互いに影響してサイトカインの産生を調節することもあるのです。関節リウマチの話に登場するインターロイキン1(IL-1)やインターロイキン6(IL-6)、あるいは腫瘍壊死因子α(TNF-α)といった物質がこのようなサイトカインと呼ばれる一群に含まれています。
そもそも関節リウマチでは、最初に何らかの原因(まだ解明されていません)により血液中の白血球が関節の中に進入し、滑膜組織の炎症を起こしています。この滑膜炎組織からは、IL-1やTNF-αが産生され、さらにIL-6やその他のサイトカインの産生を引き起こし、これらが複雑に絡み合って、関節病変が進んでいくことがわかってきました。ただ、この複雑な仕組みを簡単に理解することは大変に困難です(一番重要なところですが・・・)。
そこで関節リウマチの治療を考えてみましょう。これまでの免疫調節剤あるいは免疫抑制剤とよばれている抗リウマチ薬というのは、生体防御システムとしての免疫反応全体を抑え込んでしまう働きがあり、これが薬としての薬理作用でした。その分、多彩な副作用はつき物で避けて通ることはできません。サイトカインはタンパク質です。正常の免疫反応ではタンパク質レベルの大きさの分子は異物として認識され、抗原というラベルが貼られます。これに対して異物を特異的に除去しようとして出現するものが抗体です。通常の免疫は、この抗原抗体反応の上になりたっています。そこでサイトカインに特異的な抗体が使えれば、異常に増加したサイトカインを抑制して病気の治療につながると考えられたのが抗サイトカイン療法なのです。2003年に日本で最初に実用化したのがインフリキシマブで、これは抗TNF-α抗体です。またサイトカインが細胞に付くのを邪魔する作用を持ったエタネルセプトが2005年発売されました。今後も抗IL-6抗体の薬をはじめ各種の抗サイトカイン治療薬が開発され準備段階に入っています。
これらの薬剤は強力にリウマチの病勢を抑制し、場合によっては破壊された骨組織の修復作用も期待されることがあり、将来的にはリウマチ治療の主役となっていくのかもしれません。しかし現状では大変高価で誰でも気楽に使えるとはいえませんし、まだ長期的な効果の報告がないため重大な問題を引き起こす可能性も否定はできません。まだまだしばらくは、十分な検討を重ねる必要があるでしょう。